2022年度の入学試験が一段落し、指定規則の改正を受けた新しいカリキュラムのスタートが、いよいよすぐそこまで迫ってきている。地域に必要とされる学校とは何か、地域とどうつながれるのか、そして学生たちに何を教えるべきなのかと、教員間で議論を重ねた日々。それは同時に、自校の理念や教員一人ひとりの教育観を改めて見つめ直す機会になったことだろうと思う。
本企画では、その結晶として構築された貴重なカリキュラムの実例を紹介する。地域医療構想、地域包括ケアといったテーマだけでなく、各校の特色を踏まえた取り組みから、よりよい教育実践のためのヒントを感じ取っていただければ幸いである。
企画:片野 裕美(東京警察病院看護専門学校)
近森病院附属看護学校の紹介
近森病院附属看護学校(以下、当校)は2021年度で開校7年目を迎えた比較的新しい3年課程の看護学校(1学年定員40名)である。社会医療法人近森会グループの附属校として設立され、JR高知駅から歩いて5分ほどの高知市中心部にある。当校は、近森会グループ理事長の「全国水準よりも高齢化率が高い高知県で質の高い看護師の育成を行い、高知県の保健医療に貢献したい」という熱い思いを背景に開設された。
近森会グループには、急性期を担う近森病院(精神科・総合心療センターを有する)をはじめ、回復期リハビリテーション病院、訪問看護ステーション、就労支援に携わる社会福祉法人の施設があり、母性看護学と小児看護学以外の領域について、グループ内で対象者各ステージに応じた臨地実習が可能である。
教育理念である「近森病院附属看護学校は、変貌する社会・医療・福祉の状況に対応するために、近森会グループと連携し、高知県の保健医療福祉に貢献する看護師を育成することを使命とします。社会医療法人近森会のシンボルであるFreedom(自由)とFlexibility(柔軟さ)をコンセプトとし、学生がもっている資質を十分に引き出し、一人ひとりのもつ可能性が最大限に開花することができるように自由な発想で何事にも柔軟に、積極的に対応できる人材の育成を目指す」をもとにカリキュラムを作成している。図1は、2022年度からの当校の新しいカリキュラムマップである。

現行カリキュラムの課題
当校では、2018年よりカリキュラム検討委員会を立ち上げ、カリキュラムについて検討を重ねてきた。当初は、「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」と当校のカリキュラムとを比較し、不足している内容の抽出を行うとともに、教授方法についても検討を行った。そこで抽出された現行カリキュラムの課題として最も頭を悩ませたものは、「学生が、解剖生理学、病態生理学、看護をそれぞれ関連づけ、1人の人間に起きていることとして統合して理解できるための仕組み」をどうつくるかであった。他にも、各科目で重複して教授している内容があり、科目間の関連性等が大きな課題として示唆された。
新カリキュラムの科目設計
当校の教育課程は、看護実践能力を身につけるための「基礎分野(科目)」、看護の専門知識・技術の基礎となる「専門基礎分野(科目)」、看護の定義や看護の鍵概念、看護に重要な知識・技術、学修した知識・技術を統合、展開する「専門分野(科目)」で構成している(図1)。
1)基礎分野
人間と社会を幅広く理解し、生命の尊厳や倫理観を養うために必要な知識を身につけ、科学的思考およびコミュニケーション能力を高め主体的な判断と行動を促す内容とした。新たな科目として、専門職としての基本的なマナーを基盤としたコミュニケーションの基礎を学ぶために「社会人基礎力」(1単位)、および高知県の暮らしと文化を学ぶ「生活と文化」(1単位)を設けた。また、情報通信技術(ICT)を活用するための基礎的能力を養う必要があることと、便利に情報が使える反面、SNSや個人情報(電子カルテの取り扱い含む)など倫理的な課題も多いことを受け、「情報科学演習」のみであった科目に新たに情報倫理を主とした「医療と情報科学」(1単位)を追加した。さらに、専門基礎分野の基盤となる内容として「生物学入門」(1単位)を設けた。
2)専門基礎分野
看護学の視点から人体を系統立てて理解し、健康・疾病・障害に対する観察力、判断力を強化し、臨床判断能力の基盤となる内容とした。まず、「解剖生理学・病態生理学」を新しいシステム系に大分類した(表1)。また、臨床判断能力の基盤となる「臨床推論」(1単位)を新たな科目として設定した。
他にも、医療安全の観点から、地域で生活している人の安全を医療者としてだけではなく生活者として考えることができるよう、虐待や性犯罪、地域での災害対策などを学ぶ「健康生活と安全」(1単位)の科目を設定した。
| Ⅰ | 【消化器】 | 個体維持のための物質産生とエネルギー産生を担う消化・吸収・排泄システム |
| Ⅱ |
【呼吸・循環・脈管系1】 |
酸素を取り入れるシステムと細胞代謝に必要な各種物質を循環させるシステム1 |
| Ⅲ | 【内分泌・代謝】 | 体の恒常性(ホメオスターシス)を担うシステム1 |
| Ⅳ | 【腎・泌尿器】 | 体の恒常性(ホメオスターシス)を担うシステム2 |
| Ⅴ | 【感覚器・脳神経】 | 情報取得、統合・判断、目的行動のシステム1 |
| Ⅵ | 【運動器(整形外科)】 | 情報取得、統合・判断、目的行動のシステム2 |
| Ⅶ |
【皮膚・免疫系】 |
体を守るシステム
|
3)専門分野
看護の定義や家族の特徴および健康の考え方などの看護実践の基盤、および科学的根拠に基づいた看護技術の知識・技術・態度を養う内容とした。とくに、「成人看護学」「老年看護学」「小児看護学」「母性看護学」「精神看護学」の各看護学領域では、専門基礎分野の臨床判断能力につながる内容として、事例を用いたアクティブラーニングを取り入れた授業展開とした。臨地実習は、1年次は主に“生活する人”の視点で計画し、2年次から“病気・障害をもつ対象者の看護”を各領域別に体験し、3年次には、精神看護学領域および2年次までの学びを統合させ看護を深化させる内容として、「クリティカルケア看護実習Ⅱ」「地域・在宅看護論実習Ⅱ」「統合看護実習Ⅰ」を設定した。また、3年間の最後となる実習は、医療チームの一員となり、多重課題をこなしながらメンバーシップ、リーダーシップを学ぶ新人看護師を想定した経験ができる内容として「統合看護実習Ⅱ」を設定した。
以上のように、改正された「看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン」の「教育課程の編成にあたっては102単位以上の講義、実習を行うようにすること」を受けて、当校では看護実践力の育成のため104単位の構成とした。
新カリキュラムを構築するにあたり大事にしたこと
1)母体病院の特徴を活かし急性期看護を支える
当校の母体施設である近森病院は急性期医療に特化しており、高知県の地域医療を支えている。その母体病院の特徴を最大限に活かし、急性期看護に特化した内容を充実させ、ERや重症集中治療部、手術室での実習を含む周手術期をメインとした「クリティカルケア看護実習Ⅰ・Ⅱ」を設定した。これに付随して、1年次から臨床判断能力の育成を念頭に置き、3年次まで各科目でアクティブラーニングを積極的に取り入れ、アセスメント能力を育成することを目指した。科目としては、臨床判断能力の基盤となる「ヘルスアセスメント」や「臨床推論」の設定を行った。
2)解剖生理学・病態生理学から看護へのシームレスな科目設定
解剖生理学、病態生理学の課題に関しては、まずは人間の体の全体を総論的にとらえるために1年次の初期の段階で「生物学入門」を学び、続いて「解剖生理学・病態生理学」を学ぶ流れとした。前述のとおり「解剖生理学・病態生理学」は、新しいシステム系に大分類し(表1)、看護までがシームレスにつながるような科目設定とした。
3)対象の理解及び看護職の多様性を体感する
人間の多様性を理解することを目的とした科目設定を次のように行った。
生活体験が乏しいといわれる現代の学生に対して、早期から地域で生活している人の暮らしに触れ、その後の教育の中で地域の特性や個別性を活かした看護実践までがイメージできるようにしたいという思いから、「生活と文化」の科目で高知県における人々の暮らしを理解し、また1年次の5月初めより地域に出向き人々の生活を知ることを目的として「地域・在宅看護論実習Ⅰ」を設定した。他にも、地域・在宅看護論の各科目の講義・演習でも、地域での生活や行政の仕組みなどを知り、看護実践に活用できるようにフィールドワークを多く取り入れる予定である。
そして2年次からの各看護学領域の実習を経て、3年次には「地域・在宅看護論実習Ⅱ」で、訪問看護ステーションや居宅介護支援事業所、身体障害者リハビリテーションセンターなどでの実習を行い、「統合看護実習Ⅰ」では、中山間地域で生活している人の健康をどのように守るのかを、退院支援・継続看護の視点から理解できる内容とした。
加えて、2年次の「成人看護学実習」では、成人期の働き盛りの人の健康をどのように守っているのかを考え、0(ゼロ)次予防から看護職としてかかわることの必要性が理解できるように、保健所で行っている検診や健康教育、産業保健の実際から、慢性疾患をもつ患者への継続的な看護まで、成人期の対象の多様な生活の視点を学べる内容とした。
4)地域に根付いた看護学校としての存在価値を育む
今回のカリキュラム改正では、開校時からの構想であった“地域に根付いた看護学校”への取り組みも同時進行できるよう準備をしている。学校行事(防災訓練、学園祭)など地域への学校開放や、実習施設と連携した地域でのボランティア活動を推進し、実際のフィールドワークをきっかけとして看護学校の存在を発信することで、地域社会に貢献できる看護学校を目指している。現在は新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のため、学校行事がほとんど中止となっているが、できる限り感染対策を講じて地域社会とつながっていきたいと考えている。
以上のことをふまえ、看護の対象者を唯一無二の存在として理解し、ライフサイクル、病期、多様な生活背景に応じて必要な場所で必要な援助を提供できるように、Freedom(自由)とFlexibility(柔軟さ)の精神のもと、看護を創造できる看護師の育成を目指しカリキュラムを構築した。
今後の課題
新カリキュラムの成否には、いかに学生の思考過程をつなげてゆくか、教員一人ひとりが新カリキュラムのねらいと構造を理解し、教育内容をつなげてゆくことが重要となる。さらに現在設定しているアセスメント・ポリシー(表2)による評価を効果的に実施し、評価修正を加えカリキュラムの内容に反映させたい。
|
入学前・入学直後 |
在学中 |
卒業時・卒業後 |
|
| 教育機関レベル | ・入学試験 ・調査書等の内容 ・応募者数・入学者数 ・合格辞退者率 ・現役・社会人比率 |
・授業評価(学生による) ・入退学率 ・休学率 ・課外活動状況 ・各科目の成績(GPA) ・習得単位 |
・専門士授与率 ・卒業者数、卒業率 ・就職率・進学率 ・国家試験合格率 ・卒業時・卒業後アンケート ・就職先アンケート |
| 教育課程レベル | ・入学試験 ・入学試験科目平均値 ・入学時面接評価点 ・入学前課題達成率 ・入学前学習テスト |
・GPA ・修得単位数 ・退学率・休学率 ・授業評価アンケート |
・専門士授与率 ・GPA ・就職率・進学率 ・国家試験合格率 |
| 科目レベル | ・入学前学習 ・入学後プレテスト ・基礎学力強化対策結果 |
・客観的評価 ・修得単位数 ・OSCE ・小テスト ・実習評価 |

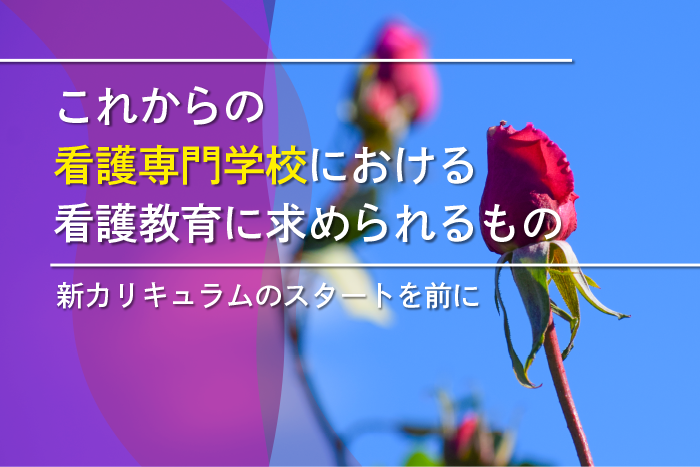
_1642387672049.png)
」サムネイル2(画像小)_1650874098963.png)

