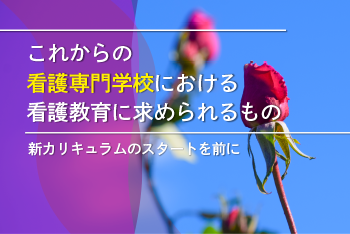第4回は、クリティカルケア看護と在宅看護のトランスレーショナル教育の実際について、クリティカルケア看護からのアプローチをご紹介いたしました。第5回では、在宅看護の教育の中にどのようにクリティカルケア看護の教育をトランスレーショナルしているのか、在宅看護からのアプローチをご紹介します。
在宅看護技術演習におけるトランスレーショナル演習の位置づけ
はじめに、本学の在宅看護技術演習の科目「看護の基本技術11(在宅看護技術)」の全体像をお示しします(図1)。

本学の在宅看護技術演習は3年次春学期に開講します。授業では、これまで学んできた知識・技術を、目の前にいる「療養者と家族」のその時々の状況に即して、「生活する場」で実践するための思考過程・工夫を学ぶことを目指しています。具体的には、訪問技術、日常生活を支える技術、医療的ケアを学修し、これらを統合した模擬訪問演習を実施します。また、リアルな模擬訪問を実施したあと、紙面を用いて疾患別事例展開を行うことで、思考の整理につなげる構成にしています。
在宅看護、すなわち自宅を訪問して行う看護技術の最大の特徴は、療養者と家族が生活する場に「訪問すること」です。演習の中でも「訪問技術」を学ぶことは大きな特徴と考えています。本学では、第3回でご紹介したように、はじめは写真を用いて訪問看護場面での観察を学び、次に実際に「訪問して観察する」ことを学ぶために、80歳代女性が一人暮らしをする部屋を再現した演習室を用いて、模擬訪問演習を実施します。模擬訪問演習では、初回訪問・服薬支援と、病状悪化時の対応を学びます。トランスレーショナル演習は、病状悪化時の模擬訪問演習に該当します。
ここからは、学生がはじめに取り組む模擬訪問演習(初回訪問・内服管理)と、クリティカルケア看護とのトランスレーショナル演習となる、病状悪化時の模擬訪問演習をご紹介します。
一人暮らし高齢女性の日常生活を再現した、居宅型演習室を用いた模擬訪問演習
初回訪問・内服支援目的の模擬訪問演習は、2日間に分けて実施します(図2)。事例の療養者は佐田米子さん、85歳女性、高血圧・糖尿病があり要介護2、夫に先立たれてから一人暮らし、娘(綾さん、60歳)は近隣に住んでおり、土曜日には必ず訪問し、薬のセットを手伝っています。綾さんは、米子さんの薬の飲み忘れがあることを心配し、訪問看護サービスを利用することにした、という設定です。

訪問時の課題は、米子さんと家族の困りごと、大切にしていること、服薬状況に関するアセスメントです。学生は、事例概要や訪問看護指示書の情報を基に、作戦会議を行ってから7分間の模擬訪問に臨みます。
模擬訪問時の様子は、居宅型演習室内に設置した①定点カメラ、②訪問看護師役の学生の手持ちカメラ、③訪問看護師役の学生が装着したアイカメラで撮影し、①定点カメラと②手持ちカメラの映像は全学生にリアルタイムで共有することで、模擬訪問ができなくても、模擬訪問の実際を追体験できる工夫をしています。
2日目冒頭では、訪問看護師役の学生から捉えた③アイカメラの映像を用いて、学生の注視点を示し、「ここを見ていた時には何を考えていたのか?」と質問をしながら、訪問時の振り返りを実施します。実際の注視点を提示することで、注視点がない箇所からは、観察できていなかった場所を明確にできます。また、注視点はあったけれども「ただ見ていただけで何も考えていなかった」「薬カレンダーがあるなと思っただけでそれ以上のことは考えていない」というように、物の確認だけにとどまっている箇所からは、「米子さんの困りごと、大切にしていること」にどのようにつながるのかを考えます。たとえば薬カレンダーをしっかり見ている学生が、そこから何を観察し、米子さんの内服状況についてどのようなアセスメントができるのかということなど、自宅の生活環境の中にあふれる情報を意味づけすることで、より米子さんの生活を理解することを目指しています。
このように、はじめの模擬訪問演習では、療養者の自宅にはじめて訪問する初回訪問と、訪問看護内容として頻度の高い内服支援に焦点を当てて訪問技術を学びます。そして、クリティカルケア看護と在宅看護のつながりを考える模擬訪問へと進みます。
クリティカルケア看護と在宅看護のつながりをイメージできる演習の設計
クリティカルケア看護と在宅看護のつながりを考えるとき、「病院から自宅への退院」というイメージがあるのではないでしょうか。しかし、「地域・在宅看護論」の基本は、「自宅から病院へ」の流れであり、日常生活が出発点です。また、クリティカルケア看護は『あらゆる治療・療養の場、あらゆる病期・病態にある人々に生じた、急激な生命の危機状態に対して、専門性の高い看護ケアを提供することで、生命と生活の質(QOL)の向上を目指す』1)とされています。定義にある「あらゆる療養の場」には自宅も含まれます。加えて図3に示されているように、クリティカルケア看護がもつ「連続性、継続性、生活の質の向上を目指す看護」は、在宅看護とも共通しており、在宅看護においてクリティカルケア看護の割合が大きくなる場面は、日常生活の中で生じる「病状悪化時」であると考えました。

在宅看護からのアプローチでは、「クリティカルケア看護と在宅看護のつながりは、自宅が起点となる」ということを強調したいと考えました。そのため、第4回でご紹介したように、「クリティカルケア看護学のシミュレーション演習」実施前の2コマを使って、在宅看護演習を行うことにしました。これによって、学生は自宅で生活していた療養者の入院を、自宅を起点とした時間の流れで理解することができます。さらに、生活の中で生じる病状悪化への対応を通して、この時の対応が療養者の生活の継続性や連続性、生活の質の向上に影響することの理解を目指しました。
在宅看護において、看護師が療養者の病状悪化に直面する場面はさまざまです。模擬訪問前には、病状悪化時の対応の流れを整理し(図4)、病状悪化に気づいた時のポイントとして「いつ対応するのか」、主治医に「いつ、何を報告するのか」の2点を挙げ、演習時のポイントにしました。

病状悪化時の模擬訪問演習
事例は、「クリティカルケア看護学のシミュレーション演習」で提示した石川平蔵さんです。
<事例概要>
石川平蔵さん(76歳)、要介護2、富子さん(妻・76歳)と二人暮らし。
内服確認と呼吸リハビリテーションのため訪問看護サービスを利用中です。
2月の寒いある日の訪問時(14時)、平蔵さんはいつもいる居間のソファではなく、ベッドのある寒い部屋で横になっていました。いつもそばにいる妻もいません。
来訪を告げると「いつもより息が苦しい」と返答がありました。
3日前に妻と外出した後から、夫婦そろって体調があまりよくないようです。
平蔵さんは、妻と二人で外出することが楽しみです。
なるべく自宅での生活を続けたいと思っていますが、
昨年の2月頃にも、COPDの急性増悪により緊急入院となったことがあります。
平蔵さん(76歳)が「いつもより息が苦しい」と訴える原因を考えて下さい。
在宅看護演習の事例では、胃がんの手術前、自宅での生活の様子、介護保険サービスの利用状況を追加しています。学生は個人ワーク、グループワークを通して、平蔵さんが「いつもより息が苦しい」と訴える原因を考え、そのことを確かめるための観察項目、必要な看護の内容を考えます。模擬訪問では、教員が平蔵さん、富子さん役を演じます。学生は演習室に訪問し、事前に考えた原因を確認するための観察を行います。
平蔵さんが「いつもより息が苦しい」と訴える原因を考える思考は、クリティカルケア看護で学修している「臨床推論」の思考過程に該当します。学生が思考過程を記載する記録用紙は、クリティカルケア看護領域の教員とともに作成し、項目を「①原因として考えられること」「②確かめるために観察する項目:平蔵さんの身体状況・富子さんへの確認事項・その他の確認事項」「③必要な看護の内容:主治医に報告する情報とそのタイミング(いつが適切か?)」と設定しました。また、事例設定と模範解答は、在宅看護実習でご指導いただいている訪問看護ステーションの所長や、訪問看護認定看護師の方からアドバイスをいただきました。その結果、その場ですぐに主治医に報告する内容のみならず、「効果的な吸入ができていない」「気温と湿度が低い」など、生活に即した内容を含むことができました。
今回の演習には、「療養者が療養の場を自宅から病院へと移行する」という場面におけるクリティカルケア看護と在宅看護のつながりだけではなく、在宅看護の中にクリティカルケア看護の考え方を取り入れる、という意味を込めました。加えて、実際に即した内容を取り入れたことで、看護基礎教育と実践場面とのトランスレーショナル教育にもつながると考えています。
本トランスレーショナル演習から学生が学んでいること
学生は、平蔵さんの息が苦しい「①原因として考えられること」として、「COPDの急性増悪」「酸素流量が守られていない」「酸素チューブが絡まっている」「便秘の悪化」などを挙げました。そしてこれらを観察することを念頭に、模擬訪問を行いました。
模擬訪問を終え、学生は「息苦しさ」を訴える療養者の体調に合わせた観察の難しさを実感したようで、「息苦しさを訴える患者を目の前にすると頭が真っ白になる」「まず患者が訴える症状に寄り添うことが大切であり、現在の体調を観察することが大事だ」という感想を持っていました。また、「息苦しいという訴えの原因を観察していくには、療養者やその時、その場に合わせて観察方法を考えることが大切だ」「療養者が苦しそうな時は、本人に話を聞くだけではなく、家族から情報収集したり、生活環境を観察することも必要だ」「家族からも話を聞くことや、その方の性格に合わせた対応が必要になる」などの感想が寄せられ、その時の療養者に合わせて考えることや家族からの情報の重要性を学んでいました。これらから、本演習において学生が、「療養者と家族」のその時々の状況に即して「生活する場」で思考することができたと評価できるのではないかと思います。
おわりに
学生は、クリティカルケア看護と在宅看護のトランスレーショナル演習において、「同一人物に対して学びを深めたことで、患者の生活に繋がった看護をイメージできた」「同じ患者で地域から病院まで繋げる視点で考えることができた」との感想を述べていました。
今回ご紹介した、在宅看護からアプローチしたトランスレーショナル演習は、クリティカルケア看護の要素を取り入れたことにより、看護の対象者の主体性がもっとも発揮される自宅を起点に、療養者の気持ちや状況に即した看護の重要性が強調され、それを実践できるための看護教育につながったと考えています。
次回、最終回では、クリティカルケア看護学と在宅看護学における分野横断の共同研究活動についてご紹介します。
1)井上智子:設立記念講演 蓄積から挑戦へ.日本クリティカルケア学会誌 1(1):15-19,2005

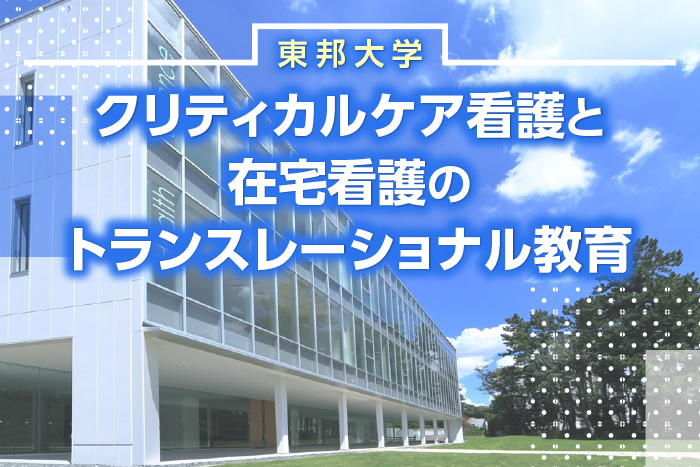

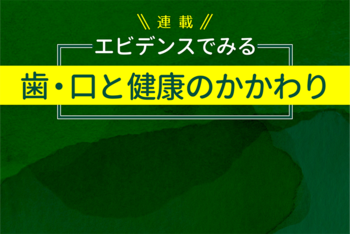
_1642387672049.png)