はじめに
2022年度から始まる新カリキュラム1)では、臨床判断能力等に必要な基礎的能力の強化のため、「専門基礎分野」の「人体の構造と機能及び疾病の成り立ちと回復の促進」についての単位が1単位増える1)。そこでは、留意点として「看護学の観点から人体を系統だてて理解し」、「臨床判断能力の基盤となる演習を強化する内容と」し、「アクティブラーニング等」を「活用することにより、主体的な学習を促す」1)とある。なかなか高いハードルではあるが、今回ご紹介する教材がその一助となり、同じ立場にある方々とともに成長していければ幸いである。
前編では、AR(augmented reality、拡張現実)アプリ「Holoeyes Edu」の誕生と導入手順、オンライン演習例について記す。
.png)
立体のものは立体で観察したい―ARアプリ「Holoeyes Edu」の誕生
私が看護学部に着任し、人体の構造と機能(解剖生理学)を教え始めたころ、せっかくの立体構造を二次元の教材(教科書等)で教えるのはもったいないと感じていた。教え方が未熟なこともあるが、今でも、二次元教材の図は、どうしても奥行きや視野が限られるため、小テストの結果1つをみても、学生に臓器の位置や大きさ、質感を伝えきれていないと感じている。
立体のものは立体で観察したい。この思いを汲んでくださったのがHoloeyes社創業者の谷口直嗣氏である。Holoeyes社は当時、臨床医療の現場で撮影されたCTやMRIなどの医療画像を三次元に再構成し、カンファレンスや患者向け説明等で利用できるバーチャルリアリティソフトウェアを提供していたが、その後の興味として、教育事業を考えているところであった。谷口氏に初めてお会いした時に、実在する人物(後にもう一人の創業者 杉本氏であると知る)のCT画像から再構築された腹腔臓器を、VRで観察したときの感動は今でも鮮明に覚えている。その後3年をかけて2020年12月に発売されたARアプリが「Holoeyes Edu」である。
「Holoeyes Edu」導入へのスリーステップ―もしも導入するとしたら
「Holoeyes Edu」の導入はシンプルである。学生たちが自分のスマホにアプリケーションをインストールし、メールアドレスでユーザー登録をしたのち、使用料を支払ってIDとパスワードを得るだけである。本稿では、せっかくの機会なので、「もし、導入するとしたら」という視点で、実際に読者の皆様にもご自分のスマートフォンでサンプルコンテンツを体験していただきながら、「Holoeyes Edu」を紹介していきたい。
ステップ1 サンプルコンテンツを使って「Holoeyes Edu」を体験する
準備するものは、スマートフォン、簡易VRゴーグル、ARマーカーである。
「Holoeyes Edu」を体験するための手順
①スマートフォンへ「Holoeyes Edu」をインストールする まず、自分のスマートフォンにて、Google PlayもしくはApp Storeから「Holoeyes Edu」を検索し、ダウンロードとインストールする。
②スマートフォン用VRゴーグルを購入する(立体視を体験したければ必須だが省略可能) 市販のスマートフォン用ゴーグルでよく、紙製だと税込110円から購入ができ(図1a手前)、ヘッドマウント型でも1,000円以内である(図1a奥)。紙製の場合は、スマートフォンのカメラが隠れないよう、左1/3を切り落としておく(図1a赤丸)。
③ARマーカーをプリントアウトする 「Holoeyes Edu、ARマーカー」で検索すると、以下のサイトからダウンロードできるので、A4用紙にプリントアウトする。https://eduholoeyes.blob.core.windows.net/maker/marker-A4_200_landscape.pdf
④アプリを使って観察する ①でインストールしたアプリを開き、サンプル教材の中からAR教材をダウンロードする。再生ボタンを押すと、「ARモード」のゴーグルあり・なし、「VR(動画)モード」のゴーグルあり・なしの4種類の観察方法があるので(図1b~e)、それぞれの長所(表1)を味わいながら観察する。
.png)
| ゴーグルに装着して観察 | 観察方法別 | スマホ等の画面上で観察 |
|---|---|---|
| ・モデルの立体視が可能 ・同じマーカーを複数人で使用すればグループ観察が可能である |
ARモード ・マーカーの大小でモデルの大きさを調節できる ・マーカーを回すとモデルを回転できる ・酔いにくい |
・モデルの拡大縮小・回転がしやすい ・ARマーカーをとらえやすい ・タブレットを用いると、同じ画面を共有し複数人で観察することができる |
| ・モデルの立体視が可能 ・背景が黒く没入感が大きい ・教員の視点から、解説つき動画の視聴が可能 |
VRモード ・ARマーカーが不要 ・没入感が大きい ・動画を視聴できる ・比較的酔いやすい |
・モデルの拡大縮小・回転がしやすい ・画面の一時停止・再生がしやすい ・教員の視点から、解説つき動画の視聴が可能 |
ステップ2 「Holoeyes Edu」を本格導入する
もし、さらに本格的に使ってみようと思ったら、Holoeyes社に連絡するとよい。
「Holoeyes Edu」を本格導入するための手順
①教員がHoloeyes社に連絡して導入の意向と使用人数を伝える。
②次に、使用予定者(学生)のメールアドレスを登録し、半期使用料税込3,300円/人を支払う。
③IDやパスワードが送られてくるうちに、学生は、前述のステップ1の①〜③を行っておく。
④登録したメールアドレスにIDとパスワードが送られてきたら、学生はアプリケーションを開き、送られてきたIDとパスワードを入れる。
(価格等は令和3年時点)
以上の手続きにより、学生はアプリ内にあるすべてのAR教材を使用することができる。「Holoeyes Edu」には、人体の構造の系統別に一通りのARコンテンツがそろっているので、講義目的に合わせて必要な教材をダウンロード再生し、好みの観察方法を選べばよい。
ステップ3 「Holoeyes Edu」の活用例―オンライン演習
ここでは、「Holoeyes Edu」に入っている「サンプル教材>静止モデル(人体・基礎解剖)>injection _01」を用いて、実際に行ったオンライン演習の例を紹介する。ワークシート例も本稿用に作成した(図2)。
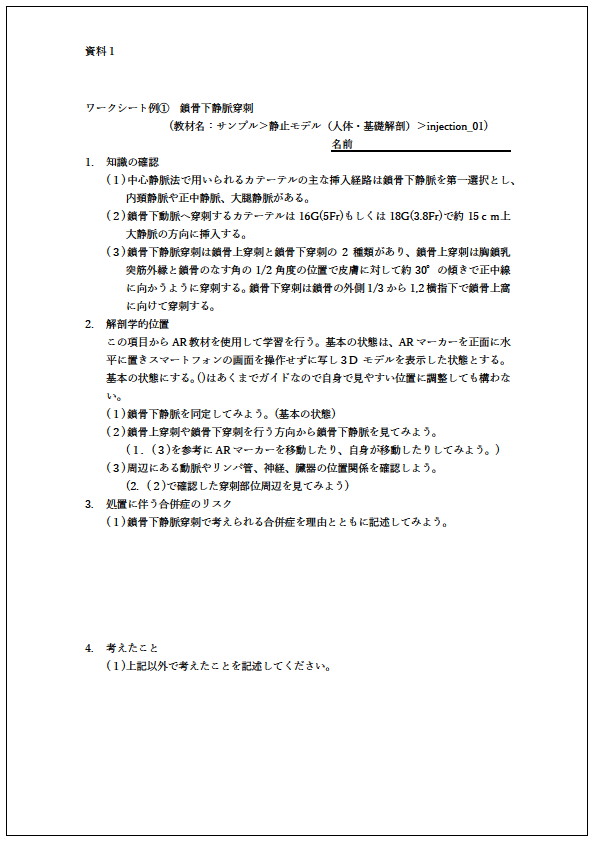
「Holoeyes Edu」を用いたオンライン演習の手順
①ワークシートを作成する 既習内容の確認や看護の視点に基づく課題を記した(図2)。
②動画で事前学習を行う(20分) グループでの観察演習時間を確保するため、観察ポイントを説明した(図3)。
③オンライン演習を行う(90分) 前半75分間は、グループに分かれて、ワークシートに沿ってオンライン演習を行い、後半15分間は、全体会とし、演習で学んだことや演習の進め方の振り返りを行った。

「Holoeyes Edu」を本校で初めて導入したのは、2020年度入学の1年生に対してである。この学年は、入学式も、解剖体観察実習も、標本室実習も、緊急事態宣言で中止され、オンライン授業が中心であった学年である。その中で、「Holoeyes Edu」を用いた「人体の構造と機能」のオンライン演習は、学生にとって、自宅で人体を立体的に観察することのできる貴重な機会を生み出したように感じている(詳細は文献2を参照)。
後編では、臨床現場において3D医療画像が普及していくなかで、「Holoeyes Edu」をどのように発展的に活用していけるかについて紹介したい。
1) 厚生労働省:看護基礎教育検討会報告書,2019年10月15日,https://www.mhlw.go.jp/content/10805000/000557411.pdf,アクセス日:2022年2月12日
2)本間典子:看護学部におけるARアプリ"Holoeyes Edu"を用いたオンライン解剖生理学演習,第26回日本VR学会大会論文集,1C2-3,2021






