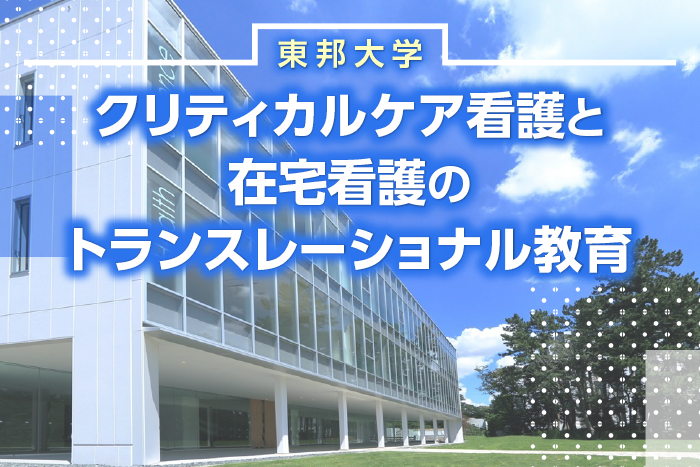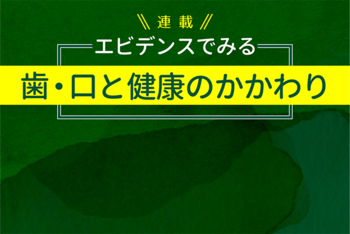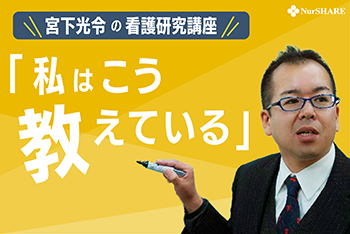連載もいよいよ最終回となりました。今回は、本学がトランスレーショナル教育の理念のもとに実施している研究や取り組みをいくつかご紹介します。
本学のトランスレーショナル教育の基盤となっている考え方
はじめに、本学のトランスレーショナル教育の考え方と、研究や地域貢献とのつながりについてご説明させていただきます。
本学の推進するトランスレーショナル教育は、これまでご紹介してきた「分野・領域の知識を橋渡しし、領域を超えた連携のもとで行う」という教育的側面だけでなく、「看護学の知識・技術・態度を臨床に橋渡しし、研究により得られた成果を看護学のエビデンスとして臨床実践へ活かす」活動、つまり「トランスレーショナルリサーチ」の推進を包含しています。文部科学省は、2040年頃の社会に必要とされる人材像を「予測不可能な時代を生きる人材」と明確に示し1)、高等教育に対し「時代の変化に合わせ、論理的思考力をもって社会を改善していく資質を有する人材の養成」を求めています2)。さらに、こうした人材養成を可能にするための高等教育と社会の関係として「知識の共通基盤」を挙げ、教育と研究を通じて、新たな社会・経済システムを提案し成果を還元する必要性を示しています。つまり、大学には、トランスレーショナルリサーチの視点が求められているといえます。
図1はトランスレーショナルリサーチの文脈で用いられる、反復的なトランスレーショナルの概念図です。基礎科学の研究が臨床応用につながり、その後、普及活動が続くことによって、最終的に臨床実践や政策に影響を与え、医療提供者と医療受給者の両方に変化をもたらすことを示しています3)。さらに、この図がサークルになっていることは、基礎研究の臨床応用を示すいわゆるBench to Bedsideだけでなく、臨床現場での観察や未解決の課題を新たな基礎研究のテーマとしてフィードバックするBedside to Benchによって科学が発展することを示しています3)。本学の推進するトランスレーショナル教育は、こうしたトランスレーションを意識した教育、研究、地域貢献活動といえます。

トランスレーショナルリサーチを推進する「訪問研究員制度」
本学では、基礎教育と継続教育のトランスレーション推進の一環で、付属病院の看護師が「訪問研究員」として、学部教員の指導の下で研究活動を行える体制を整備しています。訪問研究員は研究者としての身分を持ち、科学研究費助成事業の研究課題の分担研究者として、自律性と責任をもって研究活動に参加できます。さらに、研究代表者として科学研究費助成事業に応募することもできます。現在登録中の訪問研究員は学部教員とともに研究活動に従事し、研究課題に対する重要なブレインになっているだけでなく、対象者選定や病院との調整なども担い、研究の推進力として大きく貢献しています。
こうした体制には、臨床看護師への教育的意義もあります。臨床の第一線でとらえた研究課題は、看護学の発展のために貴重でありながらも、臨床看護師は研究活動に苦手意識や負担感情を持ったり、研究手法に精通していないために研究を諦めたりしているという報告もあります4)。一方で、看護研究者である看護系大学教員は、臨床実践に携わる機会が少なくなるために、リアルワールドの研究課題への反応性が鈍くなったり、基礎研究の臨床応用が遅れることがあります。本学の訪問研究員制度は、このような大学と臨床の谷間をつなぐための一方策になっています。こうした体制整備には大学と臨床、とくに看護部との教育・研究支援ついての相互理解が必須であり、平素からの大学と臨床の間の情報共有や連携もトランスレーショナルリサーチの推進の一部であるといえます。
本学で実施しているトランスレーショナルな取り組みの一例
多領域によるブレインストーミングから始める領域横断研究
領域横断研究の実践例として、ここでは集中治療後自宅退院患者の移行期のケアおよび在宅医療・在宅ケアに関する研究的取り組みをご紹介します。
集中治療後の患者に生じる身体的・精神的・認知的機能障害は、集中治療後症候群(PICS:Post Intensive Care Syndrome)として、救命後の患者を年単位で苦しめることが知られています。しかしこの問題は集中治療領域ではホットな話題でありながら、関連する学問領域の研究者との間の認識には差があるといわれています。
この背景に注目し、本学では、第44回日本看護科学学会の交流集会において、「集中治療後患者の在宅ケアへの移行」という共通問題をテーマに、各領域の教育研究者および実践家がそれぞれの専門的見地から意見交換する場を持つことに挑戦しました。現場の第一線で活躍する救命センター看護師、訪問看護師より情報提供を得た後、クリティカルケア看護領域、在宅看護領域、精神看護領域、老年看護領域、家族看護領域、リハビリ看護領域、がん看護領域、慢性看護領域の教育研究者が参加しました。この集会では、たとえばがん看護領域においては歴史の長いピアサポートの取り組みがPICSケアの可能性として紹介されるなど、異領域の研究知見が集中治療後患者の在宅移行ケアの問題解決のヒントとして投入されたことで有意義な集会となり、参加者からは領域横断によるブレインストーミングの手法に対する肯定的な評価を得ることができました。
複数の専門分野・領域による継続的多職種フォローアップシステムの構築
看護を超えた分野横断的研究の例として「集中治療後患者の機能回復を目指した継続的多職種フォローアップシステムの構築」研究をご紹介します。この研究は、集中治療患者の回復過程にかかわる医師、看護師、薬剤師、理学療法士などの医療者に情報科学研究者と統計の専門家が加わり継続的多職種フォローアップシステムの開発と効果検証を行うもので、本学が主管となって実施中の10機関による多機関共同ランダム化比較試験です(jRCT1032230546)。フォローアップシステム構築にあたっては、患者、家族のニーズ調査、全国の医療者の認識調査も実施し、専門家会議を繰り返し、臨床現場の課題や臨床負担を軽減した持続可能なシステム設計を目指しました。本研究の遂行においては、東邦大学が自然科学系の総合大学であり人的資源が豊富であることや、付属病院における看護師の研究意識が高いことが研究推進として働いており、研究環境がトランスレーショナルリサーチを推進する例といえます。
基礎看護領域と地域・在宅看護領域の協働による地域住民の健康生活向上支援
領域横断で実施している地域貢献活動の研究的取り組み例として、「骨の健康」をテーマとした「骨コツ倶楽部(骨密度計測を含む身体測定会)」をご紹介します。これは約500名の地域住民を対象とした「地域貢献活動ニーズ調査」の結果に基づいて開始した地域貢献活動です。ニーズ調査の結果、地域の高齢者から「骨密度の測定を通して、自分の健康状態を知りたい」という希望が挙がりました。骨密度は骨の強度を示すものであり、とくに高齢者においては転倒による骨折から要介護状態へとつながる例が多いため、骨密度の低下は住み慣れた地域での健康な生活の継続を脅かす原因となりかねません。
「骨コツ倶楽部」は、基礎看護領域と地域・在宅看護領域の教員が中心となって運営し、すでに2回実施しています。今後はこの計測会を通して地域在住高齢者の骨密度に影響を与える要因を縦断的に調査し、地域住民の生活の質の向上のための方策を検討する予定になっています。地域に実在する課題の把握に基づいているからこそ、この取り組みへの地域住民の主体性は高く、参加者の高い満足度が確認されています。本研究は、転倒予防に関する基礎研究や眼球運動に基づき、看護実践を明らかにする研究を継続的に行ってきた異領域の研究者が領域を超えて地域住民の健康の維持向上に努めるものであり、計測に基づいた基礎研究の臨床応用に挑戦するトランスレーショナルリサーチの一例といえます。
本学がトランスレーショナル教育を推進することの意義
最後に、本学が「トランスレーショナル」を意識し、教育、研究、地域貢献活動を推進することの意義について考えてみたいと思います。
看護職はトランスレーショナルリサーチの推進に寄与する存在である
1点目に、看護職は、その立ち位置と職務そのものがトランスレーショナルリサーチの推進に寄与する特徴を持つ点が挙げられます。トランスレーショナルリサーチは「研究室、診療所、地域社会での観察結果を、診断や治療から医療処置や行動の変化に至るまで、個人や公衆の健康を改善する介入に変えるプロセス」と定義されています5)。看護職は、患者や地域住民のような臨床現場や地域医療の変化に影響を受ける人々に最も近い立ち位置にあります。そのため、臨床現場の課題や対象のニーズを特定し研究テーマとして取り上げたり、研究成果の実装として新しい知見をケアに取り入れ、患者の回復促進やQOL向上を図るうえでは強みといえます。また、研究の臨床応用や普及においては、当事者参加が研究の妥当性、受容性、実用性を高め、患者の行動変容やアウトカム改善につながるといわれますが、看護職は研究への患者エンゲージメントを高めるうえでも寄与できるでしょう。さらに、研究参加の機会を、患者自身が自分の疾患や治療を理解し、自己管理能力を高める機会にして患者エンパワメントにつなげることができるという点では、研究活動がそのままケアになるともいえます。
看護職が日常的に多職種調整役割を担っていることも、トランスレーショナルリサーチの推進者として適任である理由として挙げられます。分野・領域横断研究においては、専門分野間の知識体系や研究方法論、研究文化や価値観の相違、コミュニケーション・リーダーシップの欠如が研究の障壁になるといわれます。看護職は、日常的に患者と医療チームの間でチーム調整役割を担っていることから、分野間、領域間の連携を促進しトランスレーショナルリサーチを推進する可能性があるといえます。
看護分野において「トランスレーショナル」という概念を推進する
2点目に、本学が教育・研究・地域貢献の方法の特色として「トランスレーショナル」という言葉を使用していることにも意義があると思います。創薬や医学研究では盛んなトランスレーショナルリサーチは、看護ではまだまだ発展途上であり、研究知見の社会実装を推進する必要があります。海外には、トランスレーショナルリサーチの連続体に存在する課題を克服するための、科学的および運用上のイノベーションを生み出す分野として「トランスレーショナルサイエンス」という概念があります6)。これは、基礎科学の知見を健康改善に変換するプロセスに注目し、トランスレーションを効率化、加速化するための科学的なアプローチを考えるものです。高等教育の中で「トランスレーショナル」という概念を打ち出すことによって、図1のように円環しながら発展していくトランスレーションのプロセス全体を教育や評価の対象にするという視点を持つことができます。この視点を持てばこそ、教育も研究も地域貢献も、対象や社会のニーズ志向、臨床アウトカム志向になり、つまりトランスレーショナルサイエンスの推進につながります。
おわりに
6回にわたり、本学のトランスレーショナル教育をご紹介しました。本学のトランスレーショナル教育はまだまだ発展途上ですが、8年間の経験の中で意義と効果が少しずつ感じられてきています。自然科学系総合大学の持つ資源を有効活用しながら、今後も「トランスレーショナルな挑戦」を追究していきたいと思います。
(なお本稿は、東邦大学健康科学ジャーナル第7巻(2024)の掲載した原稿の一部を修正したものです)

1) 文部科学省:今後の大学教育の振興方策について,p.1,2023,〔https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000212170.pdf〕(最終確認:2025年2月26日)
2) 文部科学省:【概説】2040年に向けた高等教育のグランドデザイン(答申),2018(https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2018/12/17/1411360_9_1_1.pdf〕(最終確認:2025年2月26日)
3) Mulnard RA:Translational research: Connecting evidence to clinical practice. Japan Journal of Nursing Science 8(1):1-6,2011
4) 市川光代, 白木沙知. 臨床看護師が看護研究を負担に感じる要因 看護研究支援に向けた文献研究からの示唆. 三育学院大学紀要 13(1), 53-61, 2021
5) National Center for Advancing Translational Sciences:About the Translational Science:About Translational Science, [https://ncats.nih.gov/about/about-translational-science] (最終確認:2025年2月26日)
6) Austin CP:Opportunities and challenges in translational science. Clinical and Translational Science 14(5): 1629-1647, 2021