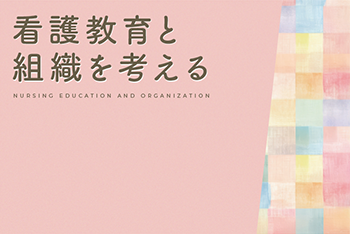看護の世界は、人種・宗教・信条・言語・文化・価値観・貧富・老若男女にかかわりなく、すべての人々に平等に向き合おうとするケアの領域です。ケアには、互いに脆弱な人間同士であるという前提で、目的に向かってさまざまな違いがあっても尊重し合い、役割を果たし合うパートナーシップを組むことが必要です。
今回は、チームを組んでパートナーになるためのヒントを考えます。『看護学への招待』(ライフサポート社・2015年)の第1部6章の一部を改変の上転載します。
「患者」から「市民へ」
「患者中心の医療」「患者中心の看護」は、言い続けられているキャッチフレーズです。あるべき理念として、多くの医療者も理解しています。しかし、患者中心と言いながら患者と医療者のパワーがアンバランスになって、医療者主導になってしまうのはなぜか、という疑問がありました。
聖路加看護大学(当時)で、2003年から5年間、この疑問を解明すべく、大がかりな研究を行いました*1。その時、まず「患者」という言葉を再考しました。「patient」 は、形容詞では、1)辛抱強い・耐える・我慢する、2)勤勉な・精を出す、3)許容すると言う意味があり、名詞では、患者・病人を指します。このpatientの意味合いからは患者は、耐える人―病苦に耐える人、医療に耐える人、不便な入院生活に耐える人だと言われているように思われます。日本語の「患者」には、医療の管理下にある病人、医師から病気の治療を受ける人と言う意味があります。「患者」という言葉がそもそも耐える、管理を受けるというニュアンスを持っており、そのために患者中心にならないのではないか、と話し合いました。では、代わる言葉があるでしょうか。
「client」には、1)依頼人(弁護士にとっての)・患者(医師にとっての)、2)顧客・お得意様という意味があり、保護すべき人というニュアンスがあります。「consumer(消費者)」はどうでしょうか。医療は営利事業ではないので、単に消費者と言っていいのか疑問が残ります。では「user(使用者・利用者)」でしょうか。訪問看護や介護では、「利用者」が使われていますが、ピタリとしませんでした。
そこで使った言葉が、「people(市民)」でした。管理される人、保護される人というニュアンスがない中性的な用語で、住民とすると地域性を伴うので、「市民」を使うことにしました。
*1 2002~2006年度聖路加看護大学21世紀COEプログラム「市民主導型の健康生成をめざす看護形成拠点」の研究です。研究成果報告書は聖路加国際大学図書館のリポジトリで公開しています。
市民が自分の健康の主人公でいるために
市民の健康はその人のものであって、誰も代わることはできません。 自分の健康は自分のものであり、各人がその主人公です。それなのに医療・保健機関に足を踏み入れたとたん、 主人公が医療者に逆転しがちな理由を考えました。
1つは情報量の差です。情報量が多いほうがパワーを持つのは、どの世界でも同じです。医療者が健康や病気・治療に関する情報をたくさん持っており、そのためにパワーを持ってしまうのです。もう1つは、医療を求めて来ているのだから、今は医療を受けることに第一の価値を置いているはずと医療者が思い込み、市民がどう考えているかを聞くより前に、医療者が考える必要な医療を提示していくからではないでしょうか。
病気・治療に関する情報を医療者が持っている一方で、具合の悪さ、病気であることの不安や心配、痛み、苦しさ、不便さ、今の状況に対する思いなどの情報は、本人や家族のほうがずっとたくさん持っています。その人の生活の状況に関しては、本人のほうが情報を持っているのです。その人の健康課題を考えるには、その情報は不可欠であるのに、伝える機会がなかったり、伝えても取り上げてもらえなかったりするのでは、市民中心にはならないのです。
医療機関を訪れる市民には、この痛みをとにかく取って欲しいと切望している人もいるし、具合が悪くなってから躊躇してやっと来たという人もいます。治療が必要とわかっても、もっと気になること、たとえば小さい子どもがいる、介護する人がいる、仕事があるといった事情を抱えている市民もいます。医療を求めていても、そこに第一の価値を置いていない、あるいは置けない市民もいるのです1)。
医療者は、患者は治療に専念する人とみなし、医療の管理下で治療に邁進してもらうことが当たり前と思ってしまうのですが、個々の事情や状況に注目し、可能な治療を選んでいければ、市民は主人公でいられるはずです。
健康情報量の差を埋める取り組み
市民と医療者の、健康に関する情報量の差がパワーの差を生む一つの要因だとすると、その差を小さくすることが、市民中心に近づく一つの方法です。健康情報の差を埋めることを目指して、前述した聖路加看護大学における研究の中で、私は2つのプロジェクトにかかわりました。1つが市民向け健康相談と健康情報探索を市民と共に行う活動、もう1つは子どもに体のことを教える活動です。これらは研究活動であると同時に、看護活動でした。5年間の研究期間が終わった時点で、市民と医療者の健康に関する情報量の差を埋めるという目標には、まだまだ至りませんでしたので、その後も実践と研究がずっと続いています。
1)市民向け健康情報提供の場「るかなび」
自分の健康に主体的にかかわり、主人公でいるためには、健康に関することを自分で決める必要があります。何であっても、事を決めるには判断材料がいりますが、保健・医療に関しての判断材料は、体(心身)の仕組み、病気と治療法、生活がどうなるか、病院、地域資源等に関する情報です。市民がその人に必要な健康情報を、的確に手にする支援をしようというのが、「るかなび」*2のねらいでした2)。
情報を提供するだけでなく、情報の探し方を知ってもらいたいと考え、看護職と図書館司書が協力して、通りに面した大学校舎の1階に「るかなび」を開き、健康チェック、健康相談を開始したのが2004年です。健康相談は、医療専門職のボランティアと大学スタッフの看護職が担いました。
開設後、近隣住民のAさんが「るかなび」の宣伝に協力してくれるようになりました。開設の翌年、行政主催の健康福祉祭りに出展した時、Aさんが友人を誘って運営に参加してくれました。地域住民にとって、大学スタッフは顔がわからない、いわば “よその人”でした。しかしAさんたちは顔見知りがたくさんで、ブースへの集客に圧倒的な強みを発揮しました。市民につながるには、市民に聞き、市民と手を組まないとならないと実感しました。そこで翌年は、企画からAさんたちと一緒に進めることにしました。Aさんたちが活動に加わったことで、専門職が必要と考えたことではなく、市民が知りたいことに応えるのでなければ意味がないこと、市民のニーズに応えるには、場と時間を共有して専門職が市民の声を真摯に聞くことが第一歩であるという、当たり前のことがわかってきました。
そこで開設3年目に健康ボランティア養成講座を開催し3)、講座を受けた人々に市民ボランティアとして「るかなび」に参加しませんか、と呼びかけました。4年目となった2007年に、市民ボランティアが来訪者への案内、ティータイムの運営、図書の整理・案内等、運営スタッフとして活動を始めました4)。
2)子どもに体を教えよう「からだフシギ」
私たちは体という実体を持って生きていますから、最も基本となる健康情報は、体のことだと思います。腎臓の具合が悪いようですね、と医師に言われてから、腎臓がどこにあって何をしているのかを調べるので は、病気や治療法に行き着くまでに時間がかかります。“体の知識をみんなのものに”をスローガンに、市民が体のことを知っている社会を目指し、まず子どもに教えよう、ということになりました。子どもとは、幼稚園・保育所の年長児、5~6歳児です5)。
教えるために教材作りから始めました。ここに携わった教員の中に、看護師・保健師・助産師、養護教諭、医師がいました。5~6歳の親という立場の人もいました。さらに、この活動に関心ある人を募ったところ、学生をはじめ、市民、保育士、幼稚園教諭などが集まったのです。何を子どもに伝えたいかは5~6歳児の親、どのように伝えたら伝わるかは幼稚園教諭や保育士が持っている情報でした。 医療職だけでないさまざまなメンバーと共に、絵本、からだTシャツ(下記参照)、紙芝居を作り、「からだフシギ」のテーマソングと踊りも作り、それらをもって、幼稚園や保育所に出かけて行きました6)。

子どもたちは集中して話を聞き、実によく理解していました。市民中心を追究していなかった頃の研究でしたら、医療者が必要と思うことのみから絵本を作って、実演してみて修正が必要と気がついたことでしょう。でもこのプロジェクトでは教材を作る段階で、市民の意見が入りました。作成にはとても時間がかかりましたが、様々なメンバーの貢献のもとにできた絵本は、子どもたちが前のめりになって聞いてくれるものに仕上がったのです。
子どもに体を教えるプロジェクトの活動は、研究期間終了後2014年にNPO法人を立ち上げて継続しています*3。
*2 聖路加健康ナビスポット、通称「るかなび」は大学名の聖路加のルカとナビゲーションのナビから名付けました。「るかなび」については聖路加国際大学ホームページをご覧ください。
*3 活動内容については、NPO法人からだフシギのホームページで紹介しています。
<後編へ続く>
引用文献
1)高橋恵子:生活者として壮年期・中年期にある女性が入院治療を余儀なくされた際に抱く気がかり.聖路加看護大学大学院博士論文,2012
2)菱沼典子,川越博美,松本直子ほか:看護大学から市民への健康情報の提供;聖路加ナビスポット「るかなび」の試み.聖路加看護大学紀要31:46-50,2005
3)Okubo N,Hishinuma M,Takahashi K, et.al.:Evaluation of Health Education Program for Active Citizens.聖路加看護大学紀要34:66-61,2008
4)高橋恵子,菱沼典子,山田雅子ほか:看護大学が開設している市民のための聖路加健康ナビスポット「るかなび」の活動評価.聖路加看護大学紀要39:47-55,2013
5)菱沼典子,松谷美和子,田代順子ほか:5歳児向けの「自分のからだを知ろう」プログラムの作製;市民主導の健康創りをめざした研究の過程.聖路加看護大学紀要32:51-58,2006
6)菱沼典子,白木和夫:子どもに聞かせるからだの話;「自分のからだを知ろう」プロジェクトの活動から.子どもと発育発達8(1):37-41,2010