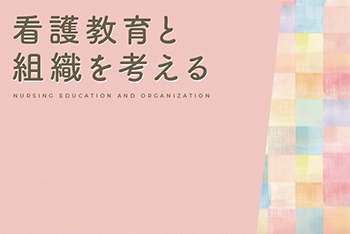<前編はこちら>
活動を通してわかった、市民が中心になること
2つの研究・実践活動を通して、市民が中心になるということは、市民と医療者が互いに人として対等な立場で、同じ目標に向かって協力し、努力することだと学びました。目標を共有し、その目標達成に向けて協力する人々の集まりはチームです。サッカーチーム、野球チーム、そして医療チーム、看護チームをイメージして下さい。チームがうまくいっている時、メンバーは互いにパートナーであり、その関係はパートナーシップと言われています1)。パートナーシップを結んだ関係は、協働 (コラボレーション) と同義だと考えていますので、協働するといってもいいと思います。市民中心を実現するには、市民とチームを作る必要があること、それには互いがパートナーと呼べる関係になることが求められることを学び、またそれは可能だということも学べました。
と言っても、市民と医療者は、はじめからパートナーになれたのではありません。私自身、持っている情報を使って表現したものが、市民から「通じない」と正面から投げ返されて、戸惑いました。逆に言えば、情報量の差からくるパワーゆえに、市民に通じていてもいなくても、通じたことにしていた現実を突きつけられたのです。医療職がこれでいいのだと言い張ったら、そのままになったでしょう。しかし市民と共に行う研究では「これで通じない?」「こうしたらどう?」と聞き続けることができました。市民とのパートナーシップを築くには、医療者が自らが持つ情報を市民の理解を得られるまで、言葉を変え、説明を変える努力が必要でした。また市民も、わかるまで聞き返す努力が必要でした。
パートナーシップを成立させる2つの土台:「垣根モデル」と「餅は餅屋モデル」
「るかなび」で市民ボランティアと専門職ボランティアと大学スタッフが混在するようになった時、市民と専門職との間に戸惑いが生じました。たとえば市民は専門職に敬語を使い、昼食を同じテーブルで取らないなど両者の間に隔たりができていったのです。それは1枚の壁ではなく、それぞれが持つ2枚の頑丈な高い壁でした。初めは両者の壁を取り払おうと思ったのですが、双方に壁で守られている領分があることに気がつきました。
人は他者に侵されたくない自分の領分を持っています。人はそれぞれの領分を持ち、その領分を囲って自分を守っているのです。その囲いの壁を取り除いてズタズタ入って行こうとしてはだめなのです。侵害されると思えば、自分を守るために壁を高くして囲っていきます。領分を囲む壁は、相手の姿が見えて話ができ、必要があれば乗り越えて助けにいけるくらいに低いものでなければいけません。高く囲っては、パートナーシップは結べません。
パートナーシップを築く過程では、囲いの壁を放っておけば伸びる生垣にし、双方が互いに超えられるように、常に低く刈り込む努力を続けることが必要でした。相手が見え、相手からも見えるよう、また安全を確認できるように足下まで見えて、声をかければ答えられ、必要があれば垣根を越えてきてくれるけれど、節度なく踏み込んでくることはないことを、互いに保証する必要がありました。領分が守られ、脅かされていないとき、人は自分を解放し、実力を発揮できます。領分を持ち囲いは低く保つ関係性を「垣根モデル」と名付けました。
パートナーシップを成り立たせるには、もう1つの土台がありました。垣根は、その内側に、役割を持っている人がいて意味を成すということです。 役割は、目的に向かって集まった人々すべてが持っているものでした。それぞれが持っている情報や経験、能力は特異です。そして、その力を目標に向けて発揮することが大切でした。役割はそれぞれ特異的であるからこそ、どの人に任せるかも大事でした。例えば絵本を作るとき、正確な体の仕組みに関しては看護職が、言葉使いは保育の専門家が、絵はイラストレーターが、という具合です。
1つの目的に向かう時、役割のない人、あるいは役割を果たさない人はパートナーになれませんでした。互いがその役割を期待し、目標達成に向けて互いに役立つことが必要でした。パートナーにはそれぞれの役割があること、その役割を互いに認めて任せること、その信頼に応えて役割を果たすことを「餅は餅屋モデル」と名付けました。
「あなた(私)の餅は何か」を常に問いかけ、餅屋に任せること、任されたものはその役割を全うすること、そしてそれぞれの領分を示す垣根が低くなっているかを常に確認することで、パートナーシップの構築を具体化できると考えています2)。
医療は問題解決技法を用いるチームプレー
医療は、医療を求めてきた市民・家族と、さまざまな専門職から作るチームで行われます。そのチームの主人公は、医療を求めてきた市民(個人またはコミュニティ)です。チームの目標は市民の健康の回復やQOLの向上であり、目標達成のために、チームメンバーそれぞれが固有に持っている知識・技術をどのように提供すれば最もよいかを話し合い、合意の上で決定し実行します。
医療・看護に限らず、何か問題が起きたときの解決方法には、問題解決技法(Problem Solving)と呼ばれる4段階のプロセスがあります。何が問題なのかを調べて、解決すべき問題を抽出し、どのような状態になることを目標にするのかを定めます。その目標に到達するための方法を選び、実行します。実行したあと、目標にどれくらい近付いたかを調べます。目標への到達状況によって、方法を見直す、あるいは目標を変える、場合によっては問題のあげ方が適切でない可能性もあるでしょう。このプロセスを繰り返して問題を解決する技術です。組織の生産性管理ではPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルと呼び、計画し、実行し、評価をし、その評価結果からさらに改善する計画へと回っていくものと説明されています。看護ではこれを看護過程と呼び、アセスメント(査定)―計画―実施―評価の4段階で、看護上の問題に対する解決目標の達成を目指します。
消失(解決)することのない健康課題を抱えている人も多くいます。その場合は、なくならない問題はそのままでも、そこから派生する困難に対し、どういう工夫を身につければ生活の質を上げられるかが解決の目標になります。たとえば糖尿病があって、食事制限をして暮らすという時、食事制限ができていないならば、それは看護上の問題として取り上げます。食事をコントロールできるようになることが目標になります。糖尿病を持っているということ自体を問題に据えると、糖尿病が治癒するという達成できない目標を掲げることになってしまいます。看護上の問題は、本人が参加しているチームで解決可能なことを抽出し、チームで共有するものです。
チームは作るもの
チームは、ただメンバーが集まっただけでは成り立ちません。「垣根モデル」で示したように、低い生け垣にして自分をオープンにし、また相手を侵害しないことを示す必要があります。自分の意思を伝える、他者の意見を聞く、率直な話し合いをするコミュニケーション能力がいります。話し合いによって、主張を引っ込める、変える柔軟性がないと、合意のもとで決めていくことができません。そして、各自がチームの目標に価値を見出していること、何のために集まっているのかがわかっていることも重要です。知恵を出し合う時、実行する時には「餅は餅屋モデル」で示したように、自分の役割を明確にし、その役割を果たすことが必要です。
集まったメンバーが互いにパートナーとなった時、チームの活動はすべてのメンバーに成長をもたらし、互いに信頼できるようになります。目標が達成された時には、全メンバーが達成感を味わい、チームは役目を終えて解散します。
パートナーシップを築くことは、医療に限らず、人間のありようとして求められるものではないでしょうか。信頼する・信頼される関係、相手を思いやる関係、自分は役に立っていると感じる関係は、ケアの本質に共通しています。医療・保健の領域で、看護職は、ことのほか人と人との関係に力を置いている職種です。看護職はチームづくりの要となり、PCC(People-Centered Care)を推進する一番の旗手だと思います。
PCC(People-Centered Care)
市民の健康課題には、市民が中心となって医療者がチームを組み、その健康課題の解決、あるいは健康課題による生活の不便を少なくすることを目標に取り組みます。チームを組むには、市民と専門職のパートナーシップが不可欠です。PCC*4は、この全体像を図に示すように説明ができます。

PCCの研究に取り組む中で、PCCの概念化を試みてきました3)4)。その結果、市民と専門職のパートナーシップの構成要素が8点抽出されています。「互いを理解する」「互いを信頼する」「互いを尊敬する」「互いの持ち味を生かす」「互いに役割を担う」「共に課題を乗り越える」「意思決定を共有する」「共に学ぶ」の8項です。そして、PCCの活動の流れは、問題に気づく→共に目標を定める→共に計画する→共に実施する→共に評価する→成果を共有するというものです。PCCにより、定めた目標の達成のみならず、メンバー個々に力がつき、社会の変容も期待できます。
看護職は、PCCを実践し、市民の健康をサポートする職業です。自分の垣根を低く保ち、看護の専門性をしっかり発揮して欲しいと思います。蛇足ですが、People-Centered Careも、Patient centered Careも、Person centered Careも略語にすると皆PCCです。3者とも健康課題を抱えた人を中心に考えるという思想は同じだと思います。
引用文献
1)ビッシュ SA:女性の健康と開発への看護の貢献;国を超えたパートナーシップ.看護51(5):111-116,1999
2)菱沼典子:パートナーシップを具体化するために;「垣根モデル」と「餅は餅屋モデル」. 日本看護科学学会誌30(4):3-5,2010
3)Kamei T,Takahashi K,Omori J,et.al.:Toward Advanced Nursing Practice along with People-Centered Care Partnership Model for Sustainable Universal Health Coverage and Universal Access to Health.Revista Latino-Americana de Enfermagem25,2017
4)高橋恵子,亀井智子,大森純子ほか:市民と保健医療従事者とのパートナーシップに基づく「People-Centered Care」の概念の再構築.聖路加国際大学紀要4,9-17,2018




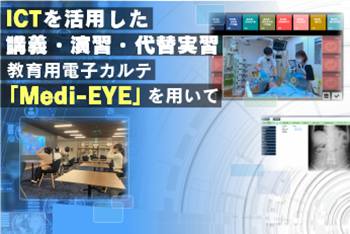
_1647426327768.png)