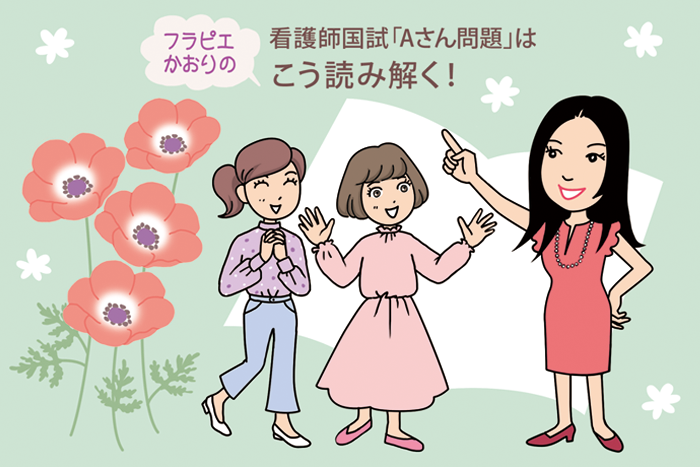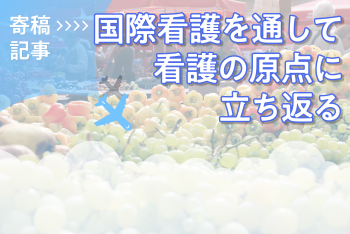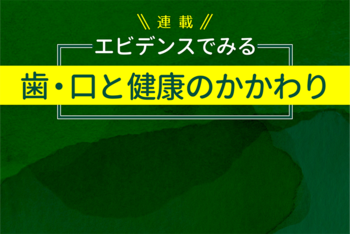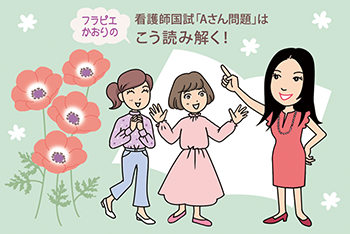はじめに:本連載をご活用いただくために
この連載では、看護師国家試験問題のなかでも長文で出題され、学生にとって難度の高い「Aさん問題」を題材として、問題を解くにあたり何に着目させ、どう理解させ、そして正答へとたどりつかせるのかを、学生(看護専門学校2年生のさくらさん、看護大学3年生のあおいさん)との対話をとおしてご紹介します。日々の指導のヒントとしてお役立てくだされば幸いです。
さくら、あおい:先生、今回もよろしくお願いします!
フラピエ:はい! ではさっそく問題をみていきましょう。
次の文を読み問1、問2に答えよ。
Aさん(23歳、女性)。両親と21歳の弟との4人暮らしである。6か月前から疲れやすく、頭痛、耳鳴、めまいがあった。1週間前から37℃台の発熱が出現し、歯磨き時に歯肉出血もみられ入院した。体温38.5℃。脈拍数100/分。赤血球180万/mm3、Hb6.8g/dL、Ht 16.8%、網赤血球1 ‰、白血球1,300/mm3、血小板16,000/mm3。骨髄穿刺液は脂肪に富み、有核細胞数17,000/mm3。再生不良性貧血と診断された。両親の動揺は大きく、本人の前で涙を流す場面がみられた。
問1 入院時のアセスメントで適切でないのはどれか。
1.出血傾向がある。
2.日和見感染を起こしやすい。
3.活動制限が必要である。
4.無効造血がみられる。
問2 免疫抑制療法を行ったが無効であった。幸い、弟とHLAタイプが一致したので骨髄移植を行うことになった。
患者への説明で正しいのはどれか。
1.全身麻酔をしたうえで移植を受ける。
2.同胞間の移植では生着不全はない。
3.2~3週間は無菌室から出ることができない。
4.無菌室では安静臥床が必要である。
[第88回(1999年) 一部改変]
さくら:今回は、また一段と難しそうな問題ですね…(*_*)
あおい:たしかに…。
フラピエ:そう、今回もあえて難しい問題を選びました(^^)
さくら:えぇぇ(-_-;)
あおい:(=_=)
フラピエ:2人ともそんな顔しないで(^^;) 今回は血液細胞(血球)のはたらきを改めて見ていこうと思います。大切な知識が身に付きますよ!
さくら、あおい:はいっ! よろしくお願いします!
この問題の評価領域分類(taxonomy)
【問1】Ⅱ型:与えられた情報を理解・解釈してその結果に基づいて解答する問題
【問2】Ⅲ型:設問文の状況を理解・解釈した上で、各選択肢の持つ意味を解釈して具体的な問題解決を求める問題
この問題を指導する際のポイント
■“貧血とは?”を復習し、貧血の種類をおさえる
■再生不良性貧血の「汎血球減少」を理解する
■Aさんの情報から、再生不良性貧血の病態をおさえる
■病態を踏まえて、入院時のAさんの状態をアセスメントする
■骨髄移植のポイントを理解する
“貧血とは?”を復習し、貧血の種類をおさえる
さくら:Aさんは[再生不良性貧血と診断された]とあります。
あおい:再生不良性貧血って、重篤なイメージがあります。
さくら:たしか、指定難病の一つだったような記憶が…。
フラピエ:2人ともいいですね。でも念のため、再生不良性貧血を詳しく勉強する前に、貧血について復習しておきましょう。貧血とは末梢血中の赤血球成分が不足した状態で、赤血球数やヘモグロビン(Hb)濃度、ヘマトクリット(Ht)値が低下します。指標となるWHOの基準がありましたよね? 覚えていますか?
あおい:はい! ヘモグロビンの値が、男性で13g/dL未満、女性で12g/dL未満です。
フラピエ:すばらしい! 赤血球成分が減少して全身への酸素供給量が不足するので、息切れ、めまい、顔色不良、易疲労感、頭痛などの症状がみられます。また酸素不足を補うために、心拍出量を増やそうとして心拍数が増加し、動悸もみられます。
さくら:Aさんは、[6か月前から疲れやすく、頭痛、耳鳴、めまいがあった]というのは、まさしく貧血の症状が出ていたんですね。
フラピエ:そうですね。これらは、すべての貧血に共通する症状です。では次に、貧血の種類を確認しておきましょう。必ずおさえておきたい種類は、「再生不良性貧血」のほか、「鉄欠乏性貧血」「溶血性貧血」「巨赤芽球性貧血」「腎性貧血」です。それぞれの特徴を表1にまとめました。
| 種 類 | 特 徴 |
|---|---|
| 鉄欠乏性貧血 | ・ヘモグロビンの合成に必要な鉄の不足によって生じる ・貧血のなかで最も頻度が高い ・舌炎、口角炎、匙状爪、嚥下痛などがみられる |
| 再生不良性貧血 | ・造血幹細胞の傷害によって骨髄での造血不良(骨髄低形成)が生じる ・末梢血では汎血球減少=赤血球、白血球(とくに好中球)、血小板の減少がみられる ・骨髄では有核細胞数の減少、脂肪髄がみられる ・貧血症状、出血(点状出血、紫斑、鼻出血、歯肉出血など)、易感染が生じる ・難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)に基づく指定難病である |
| 溶血性貧血 | ・赤血球の破壊亢進によって生じる ・網赤血球増加、黄疸、胆石、脾腫がみられる ・「自己免疫性溶血性貧血」は難病法に基づく指定難病である |
| 腎性貧血 | ・腎機能低下により腎臓でのエリスロポエチン産生が低下して貧血をきたす ・何らかの基礎疾患に続発して生じる二次性貧血(症候性貧血)の一つ |
| 巨赤芽球性貧血 | ・ビタミンB12や葉酸の欠乏によりDNA合成が障害され、赤血球の産生が阻害されて巨赤芽球が出現する ・末梢血では汎血球減少(正常赤血球、白血球、血小板の減少がみられる ・骨髄では骨髄過形成、巨赤芽球の存在がみられる ・貧血症状、味覚障害、食欲不振、ハンター舌炎、亜急性連合脊髄変性症が生じる ・胃粘膜の萎縮などによる内因子の欠乏でビタミンB12の吸収が障害される病態を「悪性貧血」という |
あおい:なんとなく、全部の名前は聞いたことはある気がします。
さくら:でもそれぞれがどんな病態なのかあやふやだったので、ちゃんと勉強します!
フラピエ:えらい! では、今回のテーマの再生不良性貧血について解説していきますね。
さくら、あおい:お願いします。
再生不良性貧血の「汎血球減少」を理解する
フラピエ:再生不良性貧血では、表1に示したとおり、造血幹細胞の傷害によって骨髄での造血が十分にできないために、末梢血中の汎血球減少をきたします。この「汎血球減少」とはどんな状態でしょう?
さくら:すべての血球が減少してしまう状態です。
フラピエ:そうですね。では、すべての血球とは?
あおい:ええと、赤血球、白血球、血小板です!
フラピエ:白血球は、もう少し詳しく挙げられますか?
さくら:好酸球、好中球、好塩基球と…。
あおい:あと、単球、リンパ球(T細胞、B細胞)です!
フラピエ:すばらしい! すべての血球は、骨髄にある造血幹細胞から分化・成熟して造られますから、その造血幹細胞が傷害されると、血球の分化・成熟が正常に行われない、ということがイメージできると思います。
さくら:赤血球も白血球も血小板も、とても大事な役割を担っていましたよね。
フラピエ:そうですね。これらのすべての血球が減少するということは、全身への酸素の運搬(赤血球)も、生体防御や免疫のはたらき(白血球)も、止血作用(血小板)も、十分に機能しない状態になってしまう、ということですね。
あおい:Aさんの状態が心配ですね…。
フラピエ:そうですね。それでは状況文を分析してAさんの状態を詳しく確認しましょう。
Aさんの情報から、再生不良性貧血の病態をおさえる
フラピエ:状況文中には症状や所見、データがたくさん出てきていますね。表2を参照しながら確認しましょう。
|
1.臨床所見として、貧血、出血傾向、ときに発熱を認める。 |
[再生不良性貧血の診断基準と診療の参照ガイド 改訂版作成のためのワーキンググループ:再生不良性貧血診療の参照ガイド,令和1年改訂版,p.2,2020年3月 より一部抜粋]
さくら:[赤血球180万/mm3][Hb 6.8g/dL][Ht 16.8%]というデータは、どれも基準値*よりかなり低いと思います。診断基準1の「貧血」に該当します。
あおい:[脈拍数100/分]も、貧血時の心拍数増加による影響ですよね?
フラピエ:すばらしい! ほかはどうですか?
さくら:[歯磨き時に歯肉出血もみられ]とあるので、出血傾向があります。[血小板16,000/mm3]というデータも、基準値*よりかなり低いです。
あおい:[1週間前から37℃台の発熱が出現]、入院時は[体温38.5℃]と、発熱の情報もあります。
フラピエ:診断基準の1も2も満たしていますね。Aさんの好中球の値は情報がありませんが、[白血球1,300/mm3]もかなり低い値*です。易感染状態にあります。
さくら:赤血球も白血球も血小板も、すべて下がっているので汎血球減少ということですね。
*基準値(目安):赤血球=男性435万~555万/μL・女性386万~492万/μL、血小板=13万~36万/μL、白血球=3,300~8,600/μL
あおい:先生、[網赤血球1‰]というのが、単位も難しくて…。
フラピエ:「‰(パーミル)」は千分率を表します。1‰=0.1%と置き換えて考えましょう。網赤血球の基準値は0.5~1.5%(5~15‰)が目安です。
あおい:そうすると、Aさんは網赤血球も値が低いですね。
さくら:網赤血球が低いというのは、どういう状態なのですか?
フラピエ:赤血球の分化・成熟の過程で、赤芽球から脱核する(核がなくなる)と「網赤血球」になります。網赤血球は骨髄から末梢血に入ったばかりの幼若な赤血球で、成熟した赤血球の一つ前の段階にあたります。末梢血中の網赤血球数を調べることで、骨髄での赤血球の産生の状態を知ることができます。この網赤血球が少ないということは、骨髄内での幼若な赤血球が少ない、つまり、赤血球の造血が低下している状態を示唆します。
さくら:ううう、難しいけど、なんとなくは理解できました…!
あおい:先生、[骨髄穿刺液は脂肪に富み、有核細胞数17,000/mm3]というのはどう考えればよいのですか?
フラピエ:これは骨髄穿刺によって、骨髄での血球産生、造血の状態を調べた結果です。[脂肪に富み]は、骨髄の組織が脂肪に置き換わっている、つまり血球産生が正常に行われていない、ということです。
あおい:わかりました!
フラピエ:さきほど説明した、核をもたない赤血球に対して、核をもっている細胞のことを有核細胞といいます。骨髄液中の有核細胞の基準値は10万~20万/μL(mm3)です。
さくら:Aさんは有核細胞数もかなり低いということですね。
フラピエ:そうですね。正常な造血がしっかり行われていないことがわかると思います。
病態を踏まえて、入院時のAさんの状態をアセスメントする
フラピエ:ここまで整理した病態を踏まえて、問1をみていきましょう。
さくら:選択肢1[出血傾向がある]は○です!
あおい:選択肢2[日和見感染を起こしやすい]というのも、Aさんは易感染状態にあるので○です!
さくら:選択肢3[活動制限が必要である]も、貧血の状態がかなり悪そうだし、[疲れやす]さや[めまい]もあって、ふらついて転倒する危険性もありますよね。だから○でいいと思います!
フラピエ:すばらしい!
あおい:ただ先生、選択肢4の[無効造血がある]はまったく想像がつきません…。
フラピエ:無効造血というのは、骨髄での造血は亢進しているにもかかわらず、血球の分化・成熟の過程で異常が起こり細胞死(アポトーシス)を起こしてしまって、正常な血球を産生できない状態です。血球の分化・成熟の途中で、細胞が壊れてしまう、ということです。
さくら:再生不良性貧血は、造血幹細胞が傷害されるのでしたよね?
フラピエ:そう、よく気がつきましたね。再生不良性貧血では、血球の分化・成熟のスタートの時点でもうダメになってしまっているのですね。
あおい:だから無効造血は当てはまらないということですね!
フラピエ:そのとおり! なお、この無効造血は巨赤芽球性貧血でみられます。
骨髄移植のポイントを理解する
フラピエ:さて、問2は再生不良性貧血の治療についてです。
あおい:Aさんは、[免疫抑制療法を行ったが無効]で、[骨髄移植を行うことになった]とあります。
フラピエ:免疫抑制療法は、免疫抑制薬(抗胸腺細胞グロブリン〔ATG〕やシクロスポリンなど)を用いて、造血幹細胞を傷害しているリンパ球を抑えて造血を回復させる治療法です。近年では、免疫抑制療法の成績は向上してきている1)とされますが、Aさんの場合は無効だったようですね。
さくら:だから骨髄移植をするんですね。
あおい:骨髄移植って、術後の免疫反応が出てしまったり、けっこうハードな治療というイメージがあります…。
フラピエ:そうですね、決して簡単な治療ではありませんね。ただ、再生不良性貧血はこれまで説明してきたとおり、造血幹細胞の傷害によって起こりますから、重症例ではとくに、造血幹細胞の補充療法である同種造血幹細胞移植の適応となります1)。ガイドラインに基づくと、重症度stage 2b以上(表3参照)の場合、年齢によって治療選択が異なってきますが、40歳未満で同胞(きょうだい)のドナーがいる場合には、骨髄移植が選択されます2)。好中球の情報がないのではっきりとは言えませんが、Aさんは少なくともstage 2b 以上ではあると考えていいでしょう。
さくら:Aさんは23歳で、[弟とHLAタイプが一致し]ているので、条件に当てはまりますね!
| stage 1:軽症 | 下記以外 |
| stage 2:中等症 | 以下の2項目以上を満たし、 ・網赤血球 60,000/μL未満 ・好中球 1,000/μL未満 ・血小板 50,000/μL未満 a. 赤血球輸血を必要としない b. 赤血球輸血を必要とするが、その頻度はひと月に2単位未満である |
| stage 3:やや重症 | 以下の2項目以上を満たし、定期的な赤血球輸血を必要とする ・網赤血球 60,000/μL未満 ・好中球 1,000/μL未満 ・血小板 50,000/μL未満 |
| stage 4:重症 | 以下の2項目以上を満たす ・網赤血球 40,000/μL未満 ・好中球 500/μL未満 ・血小板 20,000/μL未満 |
| stage 5:最重症 | 好中球200/μL未満に加えて、以下の1項目以上を満たす ・網赤血球 20,000/μL未満 ・血小板 20,000/μL未満 |
あおい:ぴったり合うドナーを探すのも大変そうですが、よかったです!
フラピエ:そうですね。ところで「HLA」とは、なんでしょう?
さくら:えぇっと…、人それぞれの白血球の、その、何か、で…す。
フラピエ:当たらずといえども遠からず、という感じね(^^;) HLA(human leukocyte antigen)は「ヒト白血球抗原」といって、これは白血球の型・タイプというふうに考えてください。自己と非自己を区別して認識しています。骨髄移植の際は、このHLA型が一致していればしているほど、移植後の移植片対宿主病(GVHD)や生着不全などを起こす可能性が低くなります。
あおい:では、選択肢2[同胞間の移植では生着不全はない]というのは○ですか?
フラピエ:残念ながら、完全に「ない」とは言い切れないと思います。ドナーから提供を受けた造血幹細胞が、患者さんの骨髄で造血を始めることを「生着」と言い3)、この生着がうまくいかないことが生着不全です。移植後、生着までの約2~3週間は、白血球がほとんどない状態が続きますので、感染予防のために患者さんは無菌室で過ごします。
さくら:では選択肢3[2~3週間は無菌室から出ることができない]が正解ですね!
フラピエ:すばらしい!
あおい:選択肢4[無菌室では安静臥床が必要である]は、×ということですか?
フラピエ:そうですね。血球の産生が不完全なので当然、活発に動くと危険ですが、必ずしも安静臥床じゃないといけないわけではありません。
さくら:先生、選択肢1[全身麻酔をしたうえで移植を受ける]ですが、これは全身麻酔をするのは患者さんではなくてドナーだから×、ということですか?
フラピエ:そのとおりです! はやとちりせずに冷静に考えられましたね。ドナーの骨髄液は、手術室において全身麻酔下で採取します。患者さんへの骨髄液の投与は、点滴静脈注射で行いますので、麻酔は不要ですね。
さくら:ふう、なんとか解き終わりました (‘ω’)
あおい:今回もめちゃくちゃ勉強した気がします!
フラピエ:それはよかった! 難しいところもあったと思いますので、しっかり復習しておいてくださいね。
さくら、あおい:もちろんです !(^^)!
フラピエかおりの、国試指導ワンポイントアドバイス!
■今回も古い国試から問題を取り上げました。血液・造血器疾患は、状況設定問題では白血病や悪性リンパ腫の出題が主流ですが、必修問題や一般問題では貧血の病態を理解しているかを問うものが出題されます(99回AM31、102回PM12・PM83、111回PM16など)。今回の問題は、血球の分化やそれぞれのはたらきを理解してもらうためにはよい題材となると思います。
■再生不良性貧血といえば汎血球減少が特徴的ですが、「再生不良性貧血=汎血球減少」を強調しすぎてインプットさせてしまうと、汎血球減少がみられるその他の病態に出会ったときに学生は混乱するようです(実際に、筆者のもとにもこの点の質問が学生たちから多く寄せられます)。血球の分化・成熟の過程をイメージしながら、同じ汎血球減少でも何が違うのかを踏まえたうえで説明するとよいです。
1)日本造血細胞移植学会:造血細胞移植ガイドライン;再生不良性貧血(成人),第2版,p.1,2019年9月
2)前掲1),p.5
3)日本造血・細胞免疫療法学会:生着不全・生着症候群,https://www.jshct.com/modules/patient/index.php?content_id=71,アクセス日:2022年2月22日