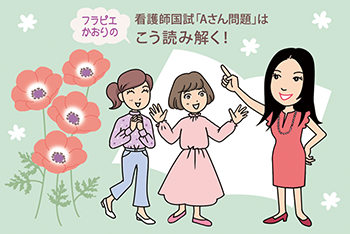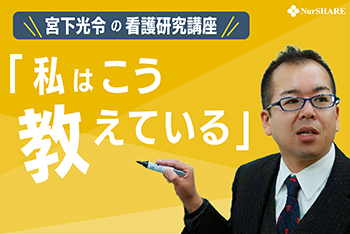はじめに
当校は鹿児島県医療法人協会を設置主体とする3年課程全日制の看護学校です。鹿児島県医療法人協会はかねてより「鹿児島県内の地域における保健・医療・福祉を支える看護師の人材教育」を目指し、1964年(昭和39年)より准看護師教育課程を開校し、1997年(平成9年)にこの中山の地に移転、2002年に3年課程全日制に課程変更となりました。
地理的には鹿児島市の南部に位置し、学校の東側にある永田川(二級河川)と、西側の小高い山に挟まれた標高18mの地にあります。開校当初の学校周囲は、畑と数件の住宅という静かな環境でしたが、ここ数年で永田川周辺および学校周辺に住宅地が立ち並び、人口が増えてきました。そのようななか、学校周辺の住民から、当校を避難所にしてほしいとの要望が市によせられ避難所となりました。
当初は台風の際に数名避難があるという程度でしたが、2019年7月に大雨による鹿児島市全域避難指示が初めて発生した際、想定を大きく超える避難者が殺到し、本来の避難場所である当校多目的ホールを越え通路や学生玄関にまで人があふれました。全国放送でも映像が流れ、災害時の恐ろしさや切迫性、避難所の必要性を実感する経験となりました。
カリキュラムの変遷と新カリキュラムにおける災害看護
第4次カリキュラム改正を受けて、本校でも「看護の統合と実践Ⅱ」のなかに災害看護を設置しました。実習施設の災害訓練に学生が避難者役で参加したり、教員が鹿児島市の桜島災害避難訓練にボランティア参加するなどして、災害看護の理解を深めながら図上シミュレーションを行う学習内容を検討しました。
今回の第5次カリキュラム改正では、この図上シミュレーションをよりタイムプレッシャーがかかるような状況とし、スピーディな判断につながるよう4時間での設計にしました。
科目名は「国際化する看護の広がりと災害看護」で1単位30時間、そのうちの4時間を「図上シミュレーション」の単元としています。ここでの学習目標は「1.既習の知識を活用し、避難所運営について考えることができる」「2.時間の流れとともに起こるさまざまなことに臨機応変に対応する臨床判断の基礎的能力を養う」「3.チームおよび地域住民等と協力をする姿勢を養う」としました。
学習の実際について
ここからは、主に「図上シミュレーション」について、その実際をご紹介します。
実施にあたっては、災害看護の講義の中で、折に触れ事前にシミュレーションについて説明します。2024年8月には本校多目的ホールで実施しました。外部講評者として参加してもらうため、鹿児島市の地域福祉課と連携をとり、当日は3名の方が学生の様子を参観されました。
実施には半日を要します。朝9時から7グループに分かれた学生が、教員より災害について最初に提示された情報をもとに、学校を避難所としてどう運営するか話し合い「どこでもシート」に記載します(図1)。決定する内容は、組織の結成、避難所のトリアージ方法、救護対策、環境整備、必要となる物的・人的資源、生活支援についてなどです。

その最中、各グループのパソコンにグーグルフォームで「付与カード」が表示されます。付与カードには、避難者の個別情報が記載されており、「精神疾患を有する人」「足を負傷した外国籍の人」「妊婦」など、本校の周辺状況を加味した人物設定や避難者の状況を科目担当の教員が作成しています。その状況にどう対応するか話し合い、5分の制限時間内に対応の内容をメールで教員に送ります。旧カリキュラム時は紙に書いたものをグループで選ばせたのですが、今回はタイムプレッシャーを意図して、計5個の付与カードを時間をおいて提示しました。私たちの想定ではグループ全員が付与カードの内容を読むと思っていたのですが、パソコン前に座った学生だけが送られた文章の一部を省いて読み上げていたため、結果的に対象の心情や状況を示唆する言葉を省くことになっており、これは想定外でした。
11時からは「どこでもシート」を用いてのグループ発表になります(図2)。さらに、付与カードの状況への対応について、全グループ分集約した資料を教員側で配布しました。1グループ5分での発表としましたが、各グループとも「感染症のリスク配慮」「家族ごと、性別ごと、年齢ごとの配慮」「ペット同伴の対応」「授乳環境」「子どものストレス対応」を考えたスペースの配置、導線などを考えていました。また「市職員との連携」「支援物資への対応」「避難者が敷地に入ってから学校を出るまでのルートの安全確保」なども考慮していました。

その後、地域福祉課の方々から、「よく避難者のことを考えている」とお褒めの言葉をいただきました。そして、「住民との連携、行政との連携が重要であること」「実際に災害があった避難所の状況の説明」、さらに「災害対応に女性目線の支援が求められており、そのために鹿児島市は女性職員が加わったこと」などを話していただき、学生は自分たちの学びが現実に必要なものだと実感していました。
学生の反応
シミュレーション終了後、学生から以下のような意見が寄せられました。
- 実際にどのような設備がどのくらいあるのかなども踏まえた上で、設営や対応の演習もしたいと感じた
- 男女それぞれの視点や一人ひとり・家族への配慮を考えながら、避難所設営案を書くのがとても難しかった
- 授業で学んだ時よりさらに深く考えることにつながった
- グループで協力してレイアウトの作成や発表することができた。また市役所の方や他のグループから他の視点でのアドバイスなども聞けてよかった
- 避難者の特徴やニーズを即座にアセスメントし避難所の配置や配慮をすることが大切だと感じた
おもに、「知識のより深い理解」「グループの協力の重要性」「視野の広がり」「即時的な判断の難しさ」が学びとして得られていました。
また、「夏休みなどに地域の小学生を対象とした避難所運営のワークショップなどをできたら地域の防災にもなる」「今回は急性期だったが、亜急性期や回復期まで視野に入れて考えていく必要がある」など、主体的に地域における災害看護の活動について考えた意見もありました。
今後に向けて
今回、できるだけリアルに学生がイメージできることを意図してシミュレーションを設計してきましたが、とくに付与カードの活用については課題があると考えます。グループの学生が付与カードの全文を読み上げなかったことや、付与カードへの対応について発表時間内にグループ間で協議ができなかったことは教員間でも検討しています。さらに、リアリティを向上させるための工夫として、今後は映像で付与カードの人物の状況を見せること、発表内容の工夫などをしていきたいと考えています。