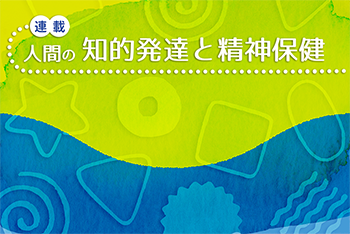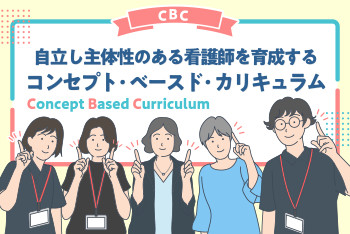はじめに―本校の概要とカリキュラム改正への対応
函館看護専門学校は、北海道の玄関口である道南函館市に位置し、学校法人野又学園が擁する9校のうちの1校として設置されました。地域社会の発展に貢献しうる人材育成を目的とし、「報恩感謝」「常識涵養」「実践躬行」の学園訓条3ヵ条*を基本に、知情意のバランスの取れた人間教育を第一目的とし、職業教育を通じてその実現を図ることを教育理念としています。
本校では、カリキュラム改正を機に教育課程を見直し、学生の課題として「世代を越える人々とのコミュニケーションスキル不足」「主体性や自主性に欠け消極的である」などの傾向が課題として挙がりました。また、以前より地域貢献としてさまざまなボランティア活動に学生が参加する機会があり、学校所在地担当の地域包括支援センターが実施する認知症カフェにも5年間ボランティアとして参画してきました。
このような背景から、2024年より新設科目として「認知症カフェ」を地域・在宅看護援助論Ⅲとして、さらには地域内をめぐる「フィールドワーク」を地域・在宅看護援助論Ⅳとして科目内に配置しました。いずれも「保健医療福祉の連携の実際を学び、企画運営に携わることで主体的に学ぶ姿勢を身につけ、また地域とともに歩む姿勢を身につけること」を目的に準備を進めていきました。
本稿ではこの新設科目について、「認知症カフェ」を中心にご紹介いたします。
地域・在宅看護援助論Ⅲ『認知症カフェ』の取り組み
事前準備(告知~実施内容の検討)
本科目の実施時期は、領域別実習期間の5月第3土曜に設定しました。ゴールデンウィーク明けにオリエンテーションを行い学生主体でグループ分けをし、地域住民への周知のためポスターを作成することから開始しました。近隣の商業施設やコンビニエンスストア、町会館へアポイントを取り、開催目的を説明した上でポスター掲示の許可をいただくため、学生たちが依頼に回りました。快く賛同してくれる事業所とのご縁を通して、学生の士気が高まりました。日頃から地域の人々との関係づくりを大切にしている地域包括支援センター職員の存在の大きさを感じました。その反面、事業所との交渉が成立しないこともあり、周知の難しさも実感したようでした。
次に、学校周辺の地域の状況を知るため、地域包括支援センター職員が講師となって、地域診断(地域の健康状態や生活環境の特徴・課題を分析すること)の結果についての講義を実施し、認知症カフェ開催へ向けた事前学習としました。その翌日には、地域包括支援センター主催で地域ケア会議を学校で開催し、学生も参加させていただきました。「認知症があっても暮らしやすい街づくり」をテーマに、参加者は学生・教員のほか居宅ケアマネジャーやグループホームの職員、町会の役員、在宅福祉委員などで、学生のグループに1~2名のファシリテーターとして加わっていただきグループワークを行いました。結果、ケアマネジャーがかかわっている利用者の支援経過や町会役員さんの見守り活動の実際など、体験談や困難なケースについて生の声を聴かせていただくことができました。
これまで学生がかかわってきた老年期の対象は病院で療養している高齢者でした。そのため生きがいを持って地域のためにアクティブに活躍している姿は新鮮で、学生への刺激になりました。同時に、地域の実情を知る機会にもなりました。
これらの体験をもとに学生中心に企画会議を行い、実施にあたりその目的や根拠を考えながらカフェの内容やスケジュールを立案して、約10日間で準備を進めました。来場者の動線を考え、学内の場所を選択し、来場者の好みで回れるようブースを用意することとしました。また、当日後半には全体での集合イベントを企画し、寸劇のテーマや内容が目的である認知症の正しい理解から逸れないように内容の検討を重ねました。学生は主体的に役割分担をしてスムーズに進めていました。
「認知症カフェ」当日の内容と行程
ブースでの開催
当日は10時~11時を前半とし、本校の講堂と教室(実習室、視聴覚室)を開放して各イベントのブースを設置しました。
講堂には、「手作りモルック(図1)」「クイズ」「奥さんお絵描きですよ(お題に沿って絵を描き、そのお題を当てるゲーム)」「折り紙」「絵合わせ(図2)」のブースを置きました。モルックはフィンランド発祥のスポーツで、木製の棒(モルック)を投げて得点が設定された12本のピンを倒し、ちょうど50点を目指すゲームです。2024年に函館で世界大会が開催されたため、地域で知名度が高まりました。しかし道具のレンタル費が高価なため、ホームセンターで建材を購入し、男子学生が中心となって道具を手作りしました。絵合わせは昔の有名人のカードをトランプの神経衰弱のように合わせる遊びで、そのカードも学生が作ったものです。そのほか同じフロアの空き教室には飲み物を用意し、休憩できるようにしました。また、会場では認知症予防の普及啓発のパンフレットや掲示を行い、来場してくれた方に見てもらえるようにしました。


実習室にはハンドケアのブースと、計測ブースを設けました。ハンドケアは手浴やハンドマッサージ、ネイルなどを実施しました(図3)。計測ブースではバイタルサイン、握力、5m歩行の速度を測定し(図4)、来場者の方々に自分の身体機能や健康状態について知っていただく機会としました。開催前日には全員で各ブースを回り、他の学生のブースを体験できるよう総練習を行いました。この練習が効果的で、当日は大きなトラブルなくスムーズに来場者をもてなすことができました。


全体開催
後半の全体開催では、高齢者を狙ったリフォーム詐欺をテーマにした寸劇、コグニサイズ(国立長寿医療研究センターが開発した、運動と計算などの認知課題を組み合わせた認知症予防を目的とした取り組み)、認知症予防クイズ、函館市が作成した「はこだて賛歌de若返り体操」を実施しました。11時から30分ほどの時間の中にこれらのプログラムを盛り込み、当日まで準備や練習を重ねました。
「認知症カフェ」を実施して
当日は学生の家族なども含めて23名の地域の方々が来場してくださり、みなさまに喜んでいただけました。以下に、来場者と学生それぞれの感想(いずれも一部抜粋)をご紹介します。
【来場者の声】
・ハンドケアは上手で気持ちよかった。ネイルもしてもらえて嬉しかった。
・若い人とのコミュニケーションで若返りました。若い人と会話をして刺激をもらい、元気をもらいました。健康体操は体を動かしながらとても楽しめました。劇では分かっていても詐欺にあうこともあると思うので気を付けないといけないと思いました。
・学生さんと話すことで若いエネルギーをもらえて楽しい。
・生徒の皆さんが地域の方に親身にアドバイスしている姿が印象的でした。
【学生の声】
・ネイルをつけた後、手を合わせて喜んでくれた姿を見てやって良かったと思った。涙を流して喜んでくれる姿を見て感動した。健康相談は高血圧のご主人への食事内容の質問などが寄せられ、地域の方がほしい情報に応えるには具体的で幅広い知識が必要だと思った。
【参加した後輩学生の声】
・先輩の手浴をしている様子を見て、これまで練習を積み重ねてきたのだと感じることができました。自分も3年生になったら先輩のように上手にできるよう沢山練習しようと思いました。
実施したのが3学年ということもあり、周知した内容の理解も早く、リーダーは主体的にクラス内をまとめて協力しながら取り組めており、学生の成長が確認できました。各担当は3~4人の小グループ制にしたことで役割分担しやすくなったこともよかったように思います。学生は外部とのコミュニケーションにも積極的に取り組むことができました。
しかし、課題も見えてきました。たとえば、装具をつけて立っている来場者の方へさりげなく椅子を提供するなどの気配りが不足していたと感じました。また、絵合わせでは学生が決めたルール一辺倒で進めるのではなく、来場者が難しそうにしていればカードの枚数を減らすなどの工夫が必要であると感じました。看護師は心身に病いのある方を対象にするため、目の前にいる方の置かれた状況を汲み取り個別性に合わせた臨機応変な対応(気配り)をしていくことの大切さを学生に伝える良い機会となりました。
さらに、「認知症カフェ」に加えて科目内で「まちの保健室」を開催し、相談ブースを設けて地域包括支援センターの方に協力を依頼しました。今後は「まちの保健室」のさらなる充実を考えており、地域の方の健康相談の場として年に数回、発展させて開催できるよう取り組んでいきたいです。
これからの地域・在宅看護援助論―認知症カフェとフィールドワークを通して
認知症カフェに続いて、2ヵ月後には地域・在宅看護援助論Ⅳとしてフィールドワークを実施しました。ここでは「地域の介護保険サービス事業所」「町会の役員や在宅福祉委員の集まり」「子育てサロン」などをグループで巡回し、それぞれの立場の方へインタビューを行いました。介護保険サービス事業所では、さまざまな特徴のあるデイサービスやヘルパーステーション、グループホーム、居宅介護支援事業所、福祉用具事業所など10ヵ所の事業所を訪れ、そこで働く専門職の方々へインタビューをさせていただき、見学や体験をしました。地域の町会に足を運び、実際の町会活動の様子を聞かせていただくこともありました。子育てサロンでは、子育て世代の親御さんや子どもの様子の見学に加え、サロンで働いている保育士の話もうかがい、幅広い年代の方とふれあう機会となりました。
これまで学ぶ機会といえば病院や施設での実習が中心であった学生にとって、今後看護師として働いたときに連携する職種の方たちとじかに話すことで、見聞を広げることにつながり、貴重な体験の機会となりました。また、学生のうちに専門職のみならず、年代を問わずさまざまな健康レベルの人と触れ合うなどの経験をすることで、地域社会の動向を捉えそこで暮らす人々へ関心を持ち、コミュニケーション能力を高めることにつながったと考えています。
地域包括ケアシステム構築の一端を担う看護師として、互いの職種を結ぶ橋渡し的役割を担う医療専門職の一員として、大きな期待を込めて引き続き看護師を育成していきたいです。地域の方にとっても、学生と交流することが刺激になり楽しいと言っていただけたことを受け、この取り組みが地域貢献の一つになっていくことを期待して、今後も継続していきたいです。