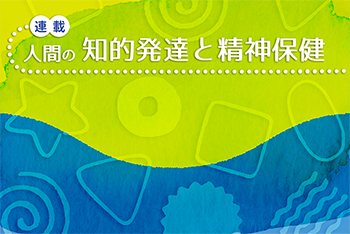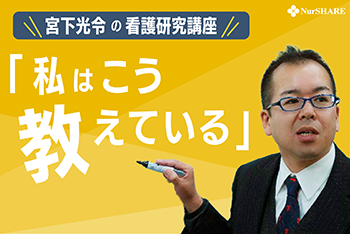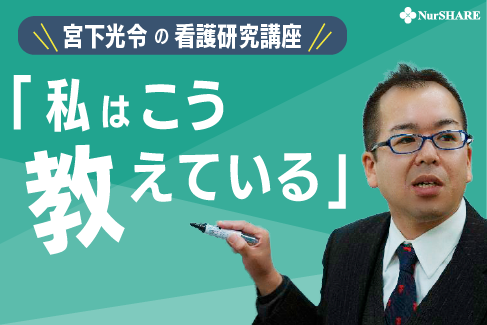本校の紹介と実践内容
当校が位置する丹波市(兵庫県の中部)は人口6万人の田園都市で6町から構成されています。市の面積は広く6町の中には公共交通機関や商業施設などの有無の差が大きく、町により暮らしぶりや健康問題なども多様です。
そこで当校では、丹波市に住む生活者と一緒に行動し、生活者を取り巻く環境や暮らしの実際を知ることを目的に、「地域視診」を行うことにしました。1年生の地域・在宅看護論「暮らしを支える看護Ⅱ」30時間のうち14時間を充てています。6町のうちの商業施設が多く交通機関も発達している地域と過疎化が進み商業施設が少ない地域に協力を得て、2~3名の学生につき1軒のお宅を訪問して半日地域の方と生活を共に過ごし、生活者を取り巻く環境を観察するとともに地域の方にインタビューをする機会を設けました。その後、地域の方と生活を共にした経験や、その中で感じたことを授業時間で発表し学びを共有しています。
授業の企画から実践までのプロセス
地域視診に必要な暮らしや生活の捉え方については1年生の「地域・在宅看護概論」の授業の中で捉えています。また調整能力やマナーについては「コミュニケーション」「礼節と感性」という科目をそれぞれ設けているため、そちらで捉え、実践に活用できるようにカリキュラムの進度を調整しています。
教員らと地域視診を計画した時に、地域住民の生活そのままを学生に見せたいと思い、地域の自治会の協力を得ることを決め、6町の中でも気候や交通、商業施設などの違いを比較できる地域を選択し依頼しました。各自治会長の会議に出向き主旨の説明をし、自治会長を通じて協力してもらえるお宅を紹介してもらいました。その後、各戸へ文書で内容説明を行い、いつも通りの生活を見せてほしいことを伝え、協力を得ました。訪問までに各地域の自治会長に地域の特徴の説明を依頼し、学生に事前に伝えてもらいました。学生は、地域の特徴から生活を想像しインタビュー内容を考えたり、自分の訪問するお宅へのアクセスを調べるなど、準備を進めました。
訪問先により体験内容はさまざまですが、地域視診当日は農作業や作物の収穫を手伝ったり、散歩に行ったり昼食を一緒に作ったりと、普段通りの暮らしの中に入らせてもらう中で、学生は多くのことを経験して帰ってきました(図1、2)。


地域連携授業から得られた学生の成長や教員の学び
全体発表から感じたこと
学生は地域視診の後、インタビューや見学したことをもとに生活者を取り巻く環境や暮らしとその特徴についてグループで発表し、個人ではレポートを提出しました。
発表では、「自宅から日用品を売っているお店までが遠い」「近くに住んでいる人が少なく、不便だしさみしい」「地域に若い人がいない」「車がないと生活できない」など、学生の目線では便利な生活とは言えない地域のようすがわかりました。しかし、その中でも地域の人々がいきいきと生活している姿を見て、住み慣れた場所で生活する意味を考える機会となりました。そして、地域の方が育んだコミュニティを基盤とし、これまでの歴史の中で紡いできたいつも通りの生活こそが、彼らのいきがいであることに気づいていました。腰や足が痛いと言いながらも農作業を楽しそうに教えてくれた方を見て幸せな生き方に思えたと話し、多くのことを感じていたようでした。履修時期が1年生の前期であり、豊かさを求めて行動してきた学生がどこまで感じ取れるかということに危惧もありましたが、看護の基盤を学んでいなくても多様な価値観を受け止め視野を広げることができており、体験以上の学びはないことを実感できました。コミュニケーション技術も未熟で調整能力もままならないことも懸念していましたが、学生なりに考え準備して挑んで飛び込んで入り込むことができており、学生のパワーの大きさを感じました。
学生の個人レポートから感じたこと
個人レポートは、「地域とのつながりは家族とは違う安心感をもたらすとわかった」「地域とのつながりにより、生活の場を信頼できる場所だと感じられるのだと知った」「住み慣れた場所で過ごせるように社会全体が協力してできることを私も取り組もうと思った」「助け合って生きることの考えを見直すことができた」など、学生がさらに考えを広げる機会となりました。
教員として感じたこと
教員として何より学んだことは、地域の方の学生に対する愛情です。当初は実施にあたり自分の生活の場に学生を受け入れてくださる方が何人いるだろうかと不安でしたが、多くの方が快く引き受けてくださり、学生が来る日に備えて体験させたいことを準備し、待っていてくださいました。この心遣いを知り、感謝の気持ちでいっぱいになりました。
地域視診が終わった後に、担当教員は地域の方に学生の発表した資料を届け、お礼の言葉を1軒ずつ伝えました。それぞれの方に「楽しかった」と言われただけでなく、次回したいことや改善したいことを提案してくださり、授業以外でも学生の訪問を希望されたりと、地域の協力を得て学生は成長させていただいていることを実感しています。この授業を通して地域の方に触れたことを機に、この地域で就職したいと希望する学生が増えたことも、地域と連携した教育で得られたことの一つです。
地域連携授業の課題や改善点、実現する上での苦労話
地域視診では日中に訪問するため、協力いただける対象は高齢者が多く、授業の狙いや内容を理解してもらうためには、具体的な説明が想定以上に必要となる場合があります。また、地域の方が日時を間違えてしまい、当日留守にされているなどの事案もありえます。
今は2町の協力を得ていますが、将来的には6町すべてを地域視診に活用し、各町の違いを学べるようにしたいと考えています。また、生活ぶりから健康課題へ、健康課題から地域医療連携の視点へと学生が学びを深化し看護を考えていけるように、カリキュラムを工夫していきたいと思っています。
地域連携授業を考えている学校へのアドバイス
当校は市立校のため、市役所の各組織を通じて、授業協力を得るためにはどの組織へ働きかければよいのか相談し、情報提供を得ています。地域の情報を得るためには、学校としてネットワークを日頃から広げておくことが大切だと考えます。学校として地域の事業やボランティアなどに積極的に参加することで情報を得やすくなり、協力していただけることも増えてくると思います。



_1647410109603.png)