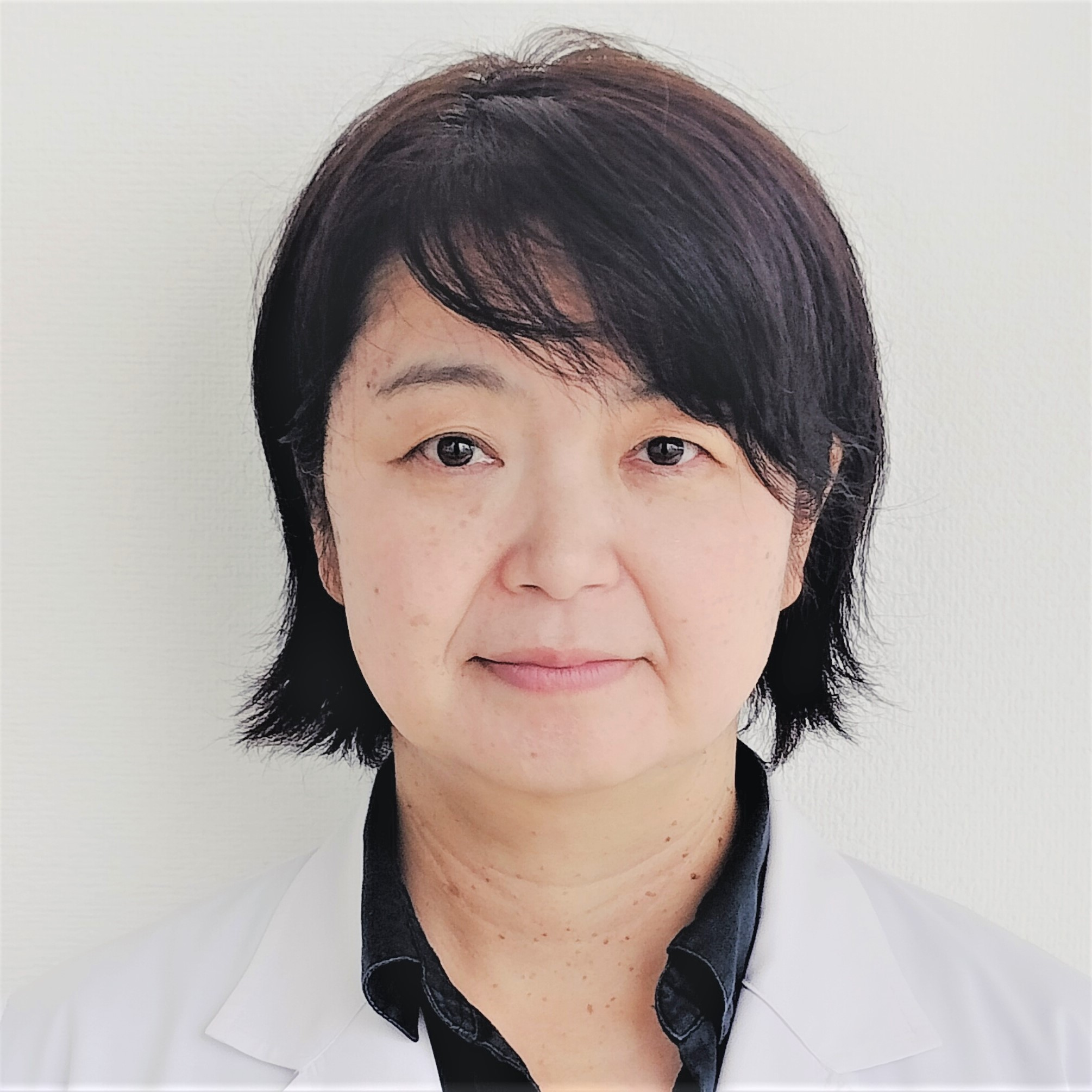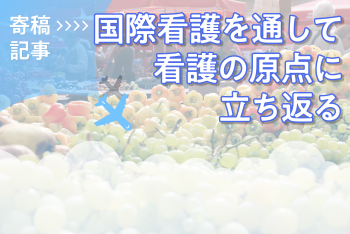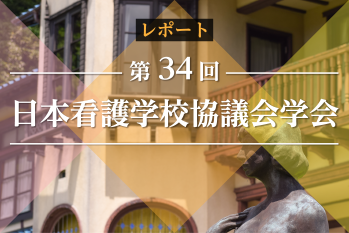はじめに
勤医会東葛看護専門学校(以下本校)は「首都圏に民医連(民主医療機関連合会)の看護学校を」という看護師や地域の方々の強い願いのもと、1995年に開校した看護専門学校です。
開校以来「日本国憲法」と「教育基本法」を理念に据え、「学生が学びの主人公」という文化のもと学生の学ぶ権利を保障し、人権を護り、学生が平和で豊かな社会建設の形成者として成長できる看護教育をめざしてきました。この29年間、学生たちがまさに学びの主人公として生き生きと自由に学ぶ校風を保障できたのは、民主的で経験豊かな多くの教育実践者の方々の惜しみない応援や、地域住民の皆さんと共に歩んだ民医連の事業所の医療活動の歴史と実践が、学生たちに豊かなフィールドとしてもたらされてきたためです。これはまさに本校の財産です。
本校では、医療・看護の科学的な知識や技術の習得にとどまらず、民主的で人間性豊かな看護師の養成をめざしてきました。患者の生活・労働を実体験するフィールドワーク、平和と人権を学ぶ研修旅行など、さまざまな経験から“いのち”の大切さや重さを学びます。この学びを維持し、教育理念を実現するためには、カリキュラムの検討・実施・総括を繰り返し行うことが重要であると考えています。
当校の「地域住民と連携した教育」の概要
本校では、1年次の秋に生命活動の学習、2年次では成人看護学実習を行い、「人間の健康に生きる力に働きかける看護実践」を学びます。そして2年次終盤の2月に、人々の多様な暮らし・労働・健康などに焦点を当て、そこから社会問題にまで視野を広げていく、3日間の「地域フィールド」学習を行っています。これは病院で臨地実習を行ってきた学生が、体験と講義とグループ研究を通して「入院患者」への認識を「地域で暮らす生活者」と捉え直し、国民の命と健康を守る医療の役割までをも明らかにしていくカリキュラムです。
第5次保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部改正に対応するカリキュラムでは、1年次「地域交流演習」、2年次「地域・在宅看護論実習」に続いて2年次後期に「地域フィールド」を配置し、「地域で生活し労働する国民の命と健康を護る看護」を3年次の専門領域で発展させる位置づけにしました。
「地域交流演習」の概要
1年次の入学直後、地域の健康づくりやまちづくりに関する活動を行う「健康友の会」に所属する地域住民(6~7人)に来校いただくか、あるいは自宅に訪問し、その方のありのままの人生をお話しいただきます。学生は、グループごとに聴講し、住民の生の声から生活・健康・命について広く学習します。この取り組みは看護学生としての学びのスタートとして、人間が生きること、まさに“生きざま“を通して自分がどう学び生きるのかまで考える場になっています。
さらに、1~2時間の話を要約せずありのままに記述してもらうことで、いかに自己解釈で他者の話を聞いていたのかということも自覚します。この学びは、事実を正確に捉える看護の基本になり、その後の教育活動をつくり上げていく土台になっています。
「地域フィールド」の概要
「地域フィールド」では、グループごとに研修先(フィールド) へ事前訪問し、具体的な学習課題を明らかにし、事前学習を行います。3日間は各フィールドワークの受け入れ先で、労働時間に合わせて一緒に働きます。実践後は、作成した体験記録を互いに発表・共有して、体験したことから生じた疑問や矛盾から研究テーマを決定し、文献学習や講義を通してその疑問や矛盾が起こる原因 について明らかにし、考察してレポートを発表します。
学習目的は「1.地域で働き、生活する人々の声を体験的に掴み、国民の命・健康・生活・労働を護る医療・看護の役割を学ぶ」「2.国民が安心して幸せに生活し、働くための仕組み、歴史を学ぶ」とし、体験を通してありのままを学習することを基本にしています。
毎年のフィールドワークの要綱作成会議では、社会の動向や問題に結び付けてフィールドを検討し、社会情勢に応じて適宜入れ替えを行っています。2023年は千葉県の酪農農家での体験と、気候変動を学ぶ新たなフィールドを立ち上げました(表1)。
| 地域フィールド | 学習内容 |
|---|---|
| 工務店、職業病外来を有する診療所 | 建設労働者の労働実態と健康問題(じん肺)について学ぶ |
| 地域の医療相談会、そのお知らせのための夜回り | 雇用の実際と健康問題について学ぶ |
| 農園での農業体験など | 食の安全と農業について学ぶ |
| 牧場での酪農農家の体験など | 食の安全と酪農について学ぶ |
| 遊就館(靖国神社)、平和資料館、東京平和委員会、横田基地 | 平和について学ぶ(戦争と医療) |
| 地域の小学校、教育センター | 教育労働と教育について学ぶ |
| 福島でのフィールドワーク(1泊2日) | 東日本大震災被害と健康について学ぶ |
| 葉山海岸(NPO気候危機対策ネットワーク代表の武本匡弘氏にご協力いただく) | 気候変動(今地球で起きている気候変動の原因・実態を学び地球上で暮らすあらゆる生物・地球・命の尊厳を考える)について学ぶ |
「実践を通しての学びと成長」
ここからは、「地域フィールド」における学生の実践についてご紹介します。
建設労働者の労働実態と健康問題を学んだグループの考察では、過酷な労働環境やアスベスト被害、仕事に誇りをもって働いてきた労働者がじん肺に侵され苦しんでいる実態を初めて知り、労働と疾病のつながりについて気づきを得ました。そして「働くこと、それは、ただ生活を維持するためにだけではない。苦しい中でもやりがいがあるから働き続けられるのである。働くことは、生きるうえでその人らしさや健康、生きがいであるが、現在はそれが政策などによって損なわれることがある。働く人の権利が保障されていることが、その人らしく生きていくことにつながる」と考察していました。
次に、雇用の実際と健康問題について学んだ学生が卒業時に振り返ってくれたことをご紹介します。
私はこれまで、この国に貧困や格差があるということについて深く学んだことがなかった。駅や道端でホームレスの人を見かけることはある。でも、それは何か自分の生活や日々とかけ離れたところで起きているような感覚になり、あまり気に留めることはなかった。毎月隅田川沿いの公園で支援団体の方々が開催している医療相談会の案内をしたりカイロや必要な方には毛布を渡したりする夜回りに参加した。21時半、雨が降り雪にも変わりそうな寒い夜だった。公園の一角には、テントのようにブルーシートを張ってランプをつけて生活されている方や、リヤカーを寝床にして休まれている方も大勢いた。この寒い中を段ボールなどで暖を取っていることを思うと、自分がダウンを着ているのは対等ではない気がして、思わず手袋を外し、ポケットに入れた。こんな光景が日本に、身近に、ひろがっているなんて…。(中略)自分がこの貧困や格差のある現実を知って、ただ絶望にさいなまれるばかりにならなかったのは、そういった弱い立場の人に心を寄せ支援する組織があることを知ることができたからである。問題意識を持ち、行動に移す団体の方々を見て希望を感じた。自分も行動しようと勇気をもらった。
この学生はさらに、「臨床の場ではそれぞれの患者さんの社会背景をしっかり受け止め対等平等に向き合い応援したい。その覚悟ができた、忘れられない体験だった」と述べて卒業していきました。
この「地域フィールド」で、学生は労働者の労働実態や生活、生きがいを知り、労働環境や労働政策が健康に与える影響を学び、健康を社会構造や政策から考察することに繋がっていきます。知らなかったことを知ることで学びが深まり、自己変革していく自分に気づいていきます。そして、医療観や看護観、健康観、さらに人間観の発展にまで及んでいきます。
フィールドワークを受け入れ協力してくださった方々は、学生が命・健康・暮らし・労働の事実を社会の問題にまで視点を広げて学ぶ姿に感動されており、「未来をつくる希望である」と励ましてくれました。