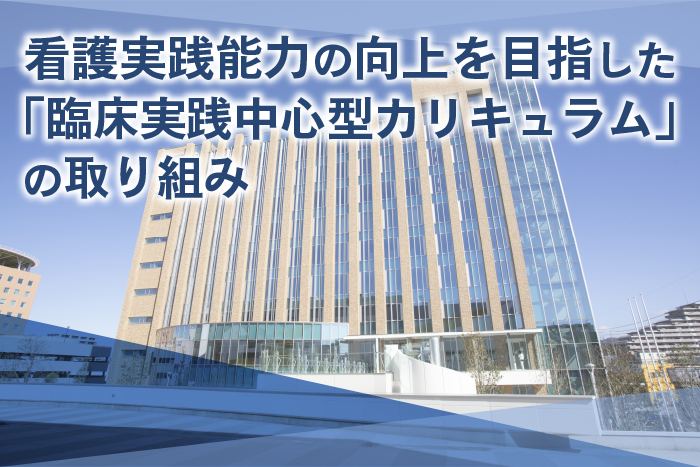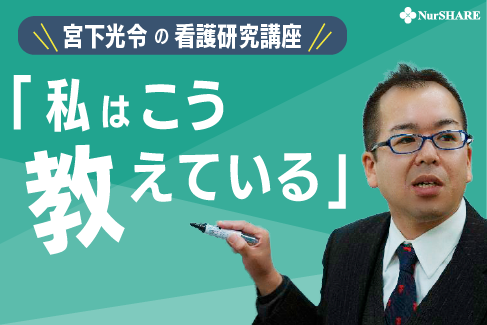はじめに
第3回までに紹介がありましたが、改めて「臨床実践中心型カリキュラム」とは、認知的徒弟性の概念を基盤に、カバーストーリーを提供し、学習者は実際の場面の中で必要な知識を応用しながら問題を解決していく過程を基本として、「MerrillのID第一原理」に基づき授業を展開し、知識、技術、態度を修得していくプログラムです。
活字にすると・・・難しいですよね。私たちも授業設計をするにあたり、一から理論を学習し勉強会や意見交換を重ねました。そして開学とともに授業が始まる基礎看護学領域では他の領域に先駆けて、担当するすべての科目において臨床実践中心型カリキュラムに則った授業を展開しました。主に1~2年生を担当していますので、認知的徒弟制では「モデリング」の工程にあたります。認知的領域の学習においては、教員が問題解決思考を例示して看護の知識を利用する力を養う段階です。
今回は科目「生活援助技術」の単元「コミュニケーション技術」の授業設計について、特にMerrillのID第一原理1)を基に説明します。MerrillのID第一原理は5つのフェーズに分けて構成されていますが、本単元は講義形式の授業となりますので、①現実に起こりそうな問題に挑戦する、②すでに知っている知識を動員する、③例示がある、の3つのフェーズまでの授業設計としました。
目標設定
「コミュニケーション技術」の単元は入学直後の1年生に実施されるため、看護についての知識が全くない学生が対象となります。これまでに「一日看護体験」や入院した経験のない学生の場合、臨床の場はかかりつけ医や医療系テレビドラマのイメージであることも多いです。
今回教授するコミュニケーションは、学生はこれまでの生活の中で当たり前のように行ってきていますが、看護の基盤となる重要な技術であり、適切な看護を提供するためには良好なコミュニケーションにより人間関係が構築されていることが前提となります。
そこで本単元では、コミュニケーションに関する基礎知識、看護におけるコミュニケーションの意義や対象、効果的な方法についての知識を修得させるとともに、コミュニケーション技術の修得に向けた主体的な学びにつなげることをねらいとして、学習目標を以下の4点としました。
【学習目標】
- コミュニケーションの構成要素と成立過程を説明できる
- 看護におけるコミュニケーションの意義、目的、対象を説明できる
- 効果的なコミュニケーションの基礎的技術について説明できる
- コミュニケーション技術の習得に向けて、自己の課題と課題解決のための具体的な取り組みを明確にできる
事前課題と授業の導入
実際の場面の中で、必要な知識を応用しながら問題を解決していくと学習目標が達成できる、という授業設計をする上で、看護の知識がない学生に対しては工夫が必要でした。そのため「これまでの生活の中で誰かと初めて出会い二人でコミュニケーションを行った場面を振り返る(どのような目的で、どのような行動をしたのか? その時、どのような気持ちだったのか? 相手の反応はどうだったのか? 等)」ことを事前課題とし、普段の生活の中から応用する知識の準備をしました。
授業の導入では、先輩看護師と新人看護師が入院直後の患者さんとコミュニケーションを行う場面のアニメーション動画を視聴してもらいました。このアニメーション動画は、先輩看護師がベッドに臥床している患者に対し、立位で見下ろしたままの状態で、視線を合わさず周囲をキョロキョロと見ながら早口で一方的に話をしているという「悪いコミュニケーション場面」です。
アニメーション動画の視聴後に、先輩看護師のコミュニケーションをどう思うか、また自分ならどのように行動するかについて考えてもらい意見交換をしました。そして「初めて患者さんとお会いする場面で、看護師としてどのようにコミュニケーションをとると良いのだろう?」と問題提起をしました。これはMerrillのID第一原理の「①現実に起こりそうな問題に挑戦する」にあたり、この問題を解決できると本単元の学習目標を達成できると考えました。
授業の展開
次に事前課題の内容について発問しながら、普段何気なく行っているコミュニケーションを意識化させ、コミュニケーションの成立過程を分解して考えることで、コミュニケーションを構成する要素があることに気付けるようにしました。これはMerrillのID第一原理に「②すでに知っている知識を動員する」にあたります。
上記の気付きをふまえて、改めてコミュニケーションの構成要素と成立する過程について図を用いて説明し、基本的な知識の修得につなげました。これはMerrillのID第一原理の「③例示がある」にあたります。
その後も発問を繰り返しながら、コミュニケーションの成立過程に影響する要素について考え、看護におけるコミュニケーションの重要性について気付かせたり(「②すでに知っている知識を動員する」)、看護におけるコミュニケーションの意義や目的、対象、効果的な方法等について学生の身近な体験に置き換えたり、教員の体験事例を活用しながら説明しました(「③例示がある」)。
説明後には再度、「悪いコミュニケーション場面」のアニメーション動画を視聴し、ここまでに学んだ知識を活用して、どのようにコミュニケーションをとると良いかをもう一度考えてもらいました。
授業のまとめと事後課題
最後に先輩看護師の「良いコミュニケーション場面」のアニメーション動画を視聴して本単元の学習内容を振り返り、問題提起していた「初めて患者さんとお会いする場面で、看護師としてどのようにコミュニケーションをとると良いのだろう?」の解答例を確認しました。このようにして学生が問題解決する上で、学習した知識を活用することや、うまく活用できなかったことに気付けるようにし、コミュニケーション技術の理解につながるよう展開しました。
また学習目標④の達成を目指し、本単元の内容をふまえて自己のコミュニケーションの特徴および、看護師を目指す上での課題と課題解決に向けた具体的な取り組みを考えることを事後課題としました。これにより今後、コミュニケーション技術の修得に向けて主体的に行動できることを期待しています。
本学では、「コミュニケーション技術」の授業の約10カ月後に生活援助実習があり、実習目標の一つに「患者とコミュニケーションを図ることができる」があります。前述しましたように本単元は講義形式の授業であったため、MerrillのID第一原理の3つのフェーズまでの授業設計としましたが、4つ目のフェーズの「④応用するチャンスがある」として生活援助実習の前にコミュニケーションのシミュレーション演習を行いました。そして5つ目のフェーズの「⑤現場で応用し、振り返るチャンスがある」として実際に実習で患者さんとのコミュニケーションを行い、自己のコミュニケーション技術の振り返りをするようにしています。
授業の評価
授業後の学生の感想では、「動画を使いながら説明を受けたので、看護師や患者のことがとても分かりやすかった」「単にコミュニケーション技術のことだけではなくて、授業中に多くの『問い』に触れたことで自分で考えることの重要性にも気付いた」「動画を見ながら自分はどんな看護師になりたいやこういう場面ではこうしていきたいなど自分の考えをしっかり持つことができた」等、臨床をイメージしながら、かつ自分で考えながら学習することで思考力の養成につながっていることが伺えました。
また、別の単元(食事援助技術)ではありますが、授業にアニメーション動画を用いる効果について検討した結果、「臨床場面の理解の促進」ができ「看護の学習の理解の促進」につながるとともに「内発的動機付けの促進」ができていたことが明らかになっています2)。
今後も学生にとって効果、効率、魅力性の高い授業となるようさらに検討していきたいと考えています。
1)稲垣忠,鈴木克明編著:授業設計マニュアルVer2,p.176,北大路書房,2015
2)児玉裕美ほか:看護学生の授業にアニメーション動画を用いる効果の検討―科目「生活援助技術」の単元「食事援助技術」の学生評価から―.日本医学看護学教育学会誌 32(2):39-47,2023