はじめに
大学設置準備期間より「臨床実践中心型カリキュラム」を構築し、2022年に本学が開設され、本年度で3年目となりました。企画第1回は本カリキュラムの理論的背景、第2回および第3回では本カリキュラムにおける授業設計の方法、そして第4回、第5回では、実際に1年生、2-3年生を対象にした授業(授業設計)について紹介しました(第1-5回の記事はこちら)。
本稿では、3年生の授業内容について紹介をした上で、本カリキュラムの課題と今後の展望について述べます。
2024年の現状(3年生)
本カリキュラムは認知的徒弟制を基本としたカリキュラムであるため、「モデリング」「コーチング」「スキャフォールディング」の工程に基づいて、カリキュラムを構築しています。すなわち、学年が上がるごとにアウトプットする場面を多くし、かつ、学習支援を外していくカリキュラムとなります。
基礎看護学領域において、1年生の座学では、知識を活性化させながら例示する場面が多く、演習では知識を活用する環境を提供し、2年生では、その活用場面が徐々に増えます。演習ではデモンストレーションを行った後に、実際に看護実践を体験させ講義で培った知識を活用させ、コーチングスキルを用いて足場を作りアウトプットさせます。また、専門領域においても2年生後期から3年生前期では、知識の活性化、例示といった形で授業を行い、次のステップで知識の活用となる環境を提供し、コーチングスキルを使いながら学習支援を行います。
●看護学臨床推論(3年生前期)について
3年生前期の「看護学臨床推論(8コマ)」の科目では、1コマ目の対面授業後に学生を3チーム(約30名/1チーム)に分けて、SBL(Simulation-Based Learning)2コマ、eラーニング4コマを組み合わせて授業を行い、最後の1コマは対面授業を行いました。1チームがSBLを受講している時は、他の2チームはeラーニングを受講する設計となります。患者急変対応をフィールドにして臨床推論を学習します。
eラーニングでは、「症例①吐血」「症例②胸痛」「症例③意識障害」「症例④腹痛」の4つの事例について、CBL(Case-Based Learning)を行い、自己学習を基本としてコンテンツを提供します。症例①〜③は100%の学生が修了、症例④は97.7%の学生が修了しています。修了することで出席になるため外発的動機づけも行っていますが、その中でも、学びたいという内発的動機づけの高い学生もいたと考えます。また、自己学習を基本としていましたが、わからないことを友人に聞きながら取り組む学生もいました。修了期限を守り、自分自身の進捗状況を確認しながら計画的に学習を行うことができており、学生の自己調整学習能力の向上につながったと考えます。
SBLでは、チームをさらに3グループ(約10名/1グループ)に分け3つのブースを設けて実施しました。1コマ目は患者急変対応時に必要なフィジカルイグザミネーションとして、「一次評価」「問診」「呼吸音」「心音」「腹部」について演習を行いました。2コマ目は患者急変対応の実際として、「胸痛」「腹痛」「呼吸困難」の患者への看護実践の演習を行いました。患者情報の収集(一次評価、問診、身体所見)について、ボードに観察項目や手順を示したことで、ガイド下での実践は可能となりました。また、「デブリーフィング」で一次評価、二次評価における臨床推論を行いました。コーチングのもと、生理学的徴候の分析や緊急度の判断、「主訴」からの臨床推論を行い、疾患を予測し、看護実践の根拠について学習しました。SBLは知識、批判的思考、臨床推論力を高めると言われており、この能力(コンピテンシー)は、看護を実践する上では必要なコンピテンシーとなります。今回の演習においてもそのコンピテンシーが向上することを期待しています。また、他の領域においても、3年生前期では「成人看護学慢性期」「成人看護学急性期」「在宅看護学」「精神看護学」「母性看護学」などの科目においてもSBLをとり入れており、知識の活用、そして統合する形での振り返る機会を設けましたので、知識、技術、コンピテンシーの向上が図れると考えます。
●専門分野の実習について
本年の10月から各領域の専門分野の実習が始まります。認知的徒弟制においては「スキャフォールディング」の工程となり足場を徐々に外していく学習支援となります。しかし、タスク(実習でのタスク)負荷が高くなると学習効果が低下するため、認知過負荷状態を作らないように、「できる点(知識、技術、コンピテンシー)」については積極的に足場を外し、「できない点(知識、技術、コンピテンシー)」については課題を明確にし、学習支援を行っていく予定です。
学習成果と課題
2年間の授業評価として、「内発的動機づけ」や「認知負荷」のアンケートでは、授業、看護、臨床に「興味」を持って授業に参加した学生は多く、「関連性」や「満足度」が高い授業評価を得ています。また、授業中の「学習タスクの負荷」や授業の「教授法(授業設計の不備)の負荷」は低く、「学習理解の促進」は高い結果を得ています。「学習理解の促進」と「学習タスクの負荷」や「教授法(授業設計の不備)の負荷」、そして、「内発的動機づけ」の項目は関連していることがわかりました。臨床実践中心型カリキュラムは「内発的動機づけ」が高く、「学習タスクの負荷」や「教授法(授業設計の不備)の負荷」は低く、「学習理解の促進」につながったことが示されました。
しかし、「自信」につながる授業については、他の項目と比較すると点数が低い結果でした。これは、いくつかの科目で授業アンケートを実施しましたが、どの授業においても同じ傾向の回答であり、「自信」につながる設計が課題となります。本カリキュラムにおける授業設計は、新しい知識の認知構造を組み立てることを目的に、既有知識の認知構造を活性化させるとして、質問(ヒント)を与える設計としています。そのため、質問に答えることができない学生はどうしても自信につながらないこともあります。また、知識を活用する場面において、「できなかったこと」をできるようにするためのフィードバックやコーチングを行い、自己の課題を明確にしていきますが、そのプロセスにおいても、自信につながることが難しかったと考えます。そのため、成功体験を増やすことや努力していることを認めるなどの学習支援の見直しが必要と考えます。
今後の展望
看護学士教育課程におけるコアコンピテンシーは、単なる知識や技能だけでなく、さまざまな資源を活用して特定の状況の中で複雑な課題に対応できるための核となる能力と定義されています1)。本カリキュラムは複雑な課題に対応できる看護実践力を向上させるために構築していますので、その成果として、コアコンピテンシーの獲得の評価を行っていく必要があります。
おわりに
今回、看護基礎教育におけるカリキュラムとして、「臨床実践中心型カリキュラム」について紹介させていただきました。成果が見えた点もありますが、課題も見えてきましたので、改善しながら引き続き実践力の高い看護師の育成を目指していきます。
1)日本看護系大学協議会:看護学士課程教育における コアコンピテンシーと卒業時到達目標,2018,〔https://www.janpu.or.jp/file/corecompetency.pdf〕(最終確認:2024年9月13日)

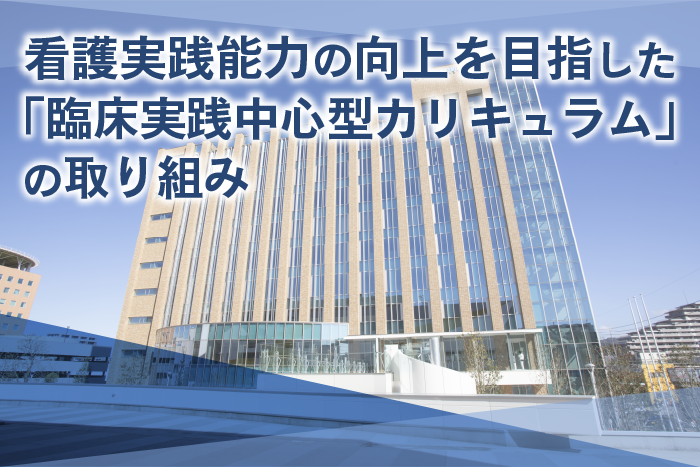


_1646127806362.png)

