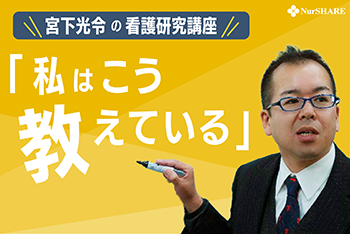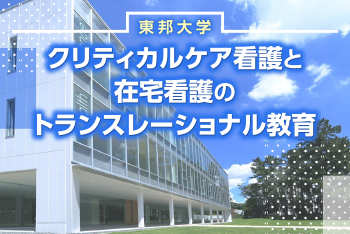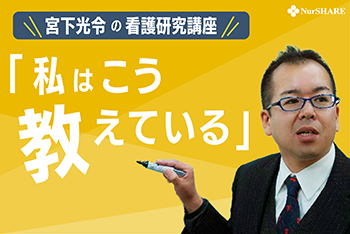はじめに
京都中部総合医療センター看護専門学校(以下本校)は、京都府南丹市八木町にある国民健康保険南丹病院組合を設置主体とする公立の看護学校です。1936年(昭和11年)に南丹病院が設立され、1940年には地域からの要望により本校が設立されました。今年で84年の歴史をもつ学校です。母体病院の南丹病院が2017年に京都中部総合医療センターに名称変更したことを機に、本校も設置主体を明確にするとともに、定員を確保することを目的として2021年に校名を変更することになりました。2022年のカリキュラム改正を見据え、本校の教育理念から教育内容などを見直し、新しい学校作りが始まりました。
地域と連携した学びの企画から実施までのプロセス
カリキュラム改正にあたって、私たちは「地域からの要望で設立された学校」であるなら地域から愛される、本校があってよかったと思っていただける学校にしたい、本校のことを地域の方に知ってほしい、と思いました。そのためにまず学生に地域へと出てもらい、地域の方と触れ合ってもらうことから始めたいと強く思ったのですが、当時は新型コロナウィルス感染症がまん延し、容易に人との接触ができない状況でした。
地域との交流を諦めかけていたときに南丹市の方と話す機会があり、私たちの想いを伝えていく中で、南地区大堰塾(地域の老人クラブ)の方とお会いする場をいただきました。そこで「地域貢献ができる学生を育てたい、地域の方と共に学生を育てたい」と伝えると、「地域の先人たちが望んで設立された学校です。もちろん協力しますよ」と温かいお言葉をいただきました。この出会いをきっかけに、コロナ禍ではありながらも地域交流が少しずつ始まりました。その他にも南丹市社会福祉協議会、南丹市農林商工部、八木町観光協会、京都信用金庫を含め多くの地域の方との交流がスタートしました。
地域交流に関する取り組みの内容と学生の様子
現在では、地域のさまざまな団体にご協力いただき、多様な活動(表1)を行っています。詳細は表1をご参照ください。科目設定はその年度ごとに決めています。たとえば小・中学生との交流会 は、コロナ禍では小児看護学実習として実施していましたが、現在は教科外活動としています。老人クラブとの折り紙交流会(図2)であれば、基礎看護学方法論や基礎看護学実習オリエンテーションなど、交流する学年の学習状況やレディネスに応じて実施しています。
.png)


4月に入学した新入生は、地域の方(70~80歳)と一緒に地元の八木城跡登山をします(図3)。学生は汗をかき息も切れ切れですが、地域の方はサッサと軽やかな足取りで登られており、学生はその姿を見て元気に活動される高齢者の姿に驚いています。また、折り紙交流会では折り方を教えてもらったり、教えたりすることで、高齢者のペースに合わせることや敬う心を育てています。

「地域交流プロジェクト(図4)」の取り組みでは、地域の方を学校にお招きして、血圧測定や健康チェックをしたり、健康教育、ロコモ体操など健康維持のための情報を提供します。また、小・中学生をお招きし手浴、赤ちゃん抱っこ、車椅子移動など看護体験をしてもらうこともあります。「地域交流プロジェクト」の案内にあたっては、年に2回「学校だより」を発刊し、南丹市を通じて800戸に配布しています。また、来校者には学生が作成した暑中見舞いやクリスマスカードを郵送しています。
開始当初は20数名の来校者でしたが、今では約50名が来校されるようになり、足浴、血圧測定、手浴、ゲームなどを行い楽しい時間を過ごしていただいています。学生は来校者とコミュニケーションを取りながら、暮らしの中で困っていることや、健康を維持するために食事や運動方法はどうしているかを聞き、住民の地域での暮らしを学び地域在宅看護論につなげていきます。加齢にともなう変化や交流会の意義なども実感しながら、学生は看護の意味を学んでいます。

小・中学生との交流では、成長発達課題に合わせたかかわり方を学ぶだけでなく、進路相談を行うことで、看護師を目指した初心を思い出し勉強を頑張るようになる学生もいます。農業体験(図5)では農業の大変さや自助・共助・公助の実際を学びます。学生はいつも元気いっぱいで大きな声で笑い合いながら交流しています。

多くの地域交流を行う中で、学生と地域の方が顔見知りになり、声をかけてもらったり「さつまいも食べて」「庭に花が咲いたから飾って」と気にかけていただいています。また、教員も地域貢献をしたいと小学生への職業体験(出張)や保育園での子供救急蘇生研修を行っています。教員も地域を知ることで、視野を広め、地域の中の本校のあり方を考えながら積極的に取り組んでいます。
学生の成長と学び
学生達は地域の方からの温かいお言葉をいただき、看護師になるという思いを再確認するとともに、地域貢献できることを誇りに思っていると感じています。
学生の感想を一部ご紹介します。
・足浴を終えて「いつも足がしびれているけど治った」と足浴の効果を感じてもらうことができました。高齢者の方の笑顔や感謝の言葉を聞いて、改めて頼りにされる看護師になりたいと思いました。
・今までさまざまな形で地域交流をさせてもらいましたが、皆さんはとても温かくいつも優しいです。「この交流会が一つの楽しみ」と言われとても嬉しくなりました。今後も地域の方々とかかわっていきたいです。
・私たちは先生や京都中部総合医療センターの方達だけでなく、地域の方に支えられていることを改めて実感することができました。地域の方に愛される看護師になりたい。
・交流会があっても参加できない人がたくさんおられることを知った。今後、私たちが地域交流をとおして貢献できることはたくさんある。一人でも多くの方と交流し地域貢献したい。
変化した入学目的
地域交流を通して本校でしか学べないことをアピールポイントにしたことで、受験生の本校に入学したい志望動機に明らかな変化が見られるようになりました。「私が京都中部総合医療センター看護専門学校への入学を希望したのは、城山登山など地域散策があり地域を深く知ることができるからです。さらに地域の方と交流があり地域における看護を学ぶことができるからです。地域と自分のかかわりを考え、地域の方に寄り添うことのできる看護師を目指して頑張って行きたいと考えています」と言ってもらえることがあるなど、地域交流から看護を学びたいというビジョンを明確にして受験する学生が増えています。
課題と今後の取り組み
現在の課題は、お互いに楽しく交流し学ぶために参加者の要望を組み入れ、実施内容を変化させていくことでマンネリ化を防ぎ継続していくための工夫です。
今後の取り組みとしては、本校でのサロン開催、地域の方からの講義、一緒にウォーキングをするなどの健康活動、挨拶や声かけなどを通して高齢者の孤立を防ぎ、異変に気付くための 「地域見守り隊」活動を実施したいと考えています。
おわりに
・交流会に参加させていただき、とても楽しく勉強になりました。看護師さんが育って行かれること、頼もしく嬉しいことです。安心して暮らしていけることを実感し感謝しています。
・色々な学生さん達の頑張りを見て、とても良いことをされて今後の道に進まれることを願っています。今日は良い一日になりました。このまま続けていただけたら嬉しいです。
これらは地域の方からのお言葉です。こういったお言葉を見ると、3年前、京都中部総合医療センターに隣接しているにもかかわらず「学校ってどこにあるの?」と質問を受け本校が地域に根ざしていないことにショックを受けたことを思い出し、本校の地域交流活動を住民の方々に知っていただけるようになってきたことに喜びを感じ ます。今後さらに「本校があってよかった」と思っていただけること、地域の方と共に学生を育てていくための取り組みをしていきたいです。