ジャパンハートは「医療の届かないところに医療を届ける」をミッションに掲げ活動する、2004年に設立された日本発祥の国際医療NGO(非政府組織)です。アジアの開発途上国(ミャンマー・カンボジア・ラオス)で子どもの無償治療などを行っており、その数は年間約4万件、累計35万件を超えます。日本国内では離島・へき地への医療者派遣、災害被災地への現地支援や小児がんの子どもと家族の外出を医療者がサポートする活動に取り組んでいます。
この連載では、ジャパンハートを通じて国内の離島・へき地医療で活動する看護師のようすや、そこでの医療の現状などをお伝えしていきます。
離島・へき地における医療者数の実態
離島やへき地における看護師の配置状況は、地域の医療提供体制に大きく影響しています。厚生労働省の調査によれば、離島の診療所では、1施設あたり常勤医師が平均1人、常勤看護師が平均2人1)配置されています。 一方、へき地医療拠点病院*では、常勤医師が平均20人、常勤看護師が平均102人1)と、より充実した人員配置が見られます。
しかし、これらの数値はあくまで中央値であり、実際の配置状況は地域の特性や医療需要によって変動します。特に小規模な離島やへき地では、医療資源が限られており、看護師の確保が困難な場合も少なくありません。そのため、自治体や医療機関は、医療従事者の派遣や遠隔医療の導入など、さまざまな対策を講じています。離島・へき地では看護師の確保が難しく、とくに専門的なスキルを持つ人材の不足が顕著です。長崎県の報告では、同県の看護職員は2025年に661人不足するとの需給推計2)がなされており、とくに離島では確保が困難な状況にあります。さらに、へき地医療拠点病院の中には、へき地への看護職派遣を実施している施設もありますが、その割合は約17.2%3)にとどまっています。このような状況から、離島やへき地での看護師の確保と育成は、地域医療の質を維持・向上させる上で重要な課題となっています。
離島・へき地における看護師確保が困難な背景
離島やへき地において看護師の確保が困難である理由は多岐にわたりますが、主な原因と考えられる7つの背景についてご説明します。
人口減少と少子高齢化
離島・へき地では人口減少と高齢化が全国平均よりも進行しており4)、若年層の人口が少ない上、地域で育った若手の看護師が豊富な経験や専門性を求め、都市部へ流出する傾向が強く、地方の医療機関では新規採用が困難な状況にあります。ある研究では離島・へき地において50歳以上の看護職が約半数を占めており、若年層の看護師の確保が課題である3)と提示しています。
生活環境とライフスタイルの違い
離島・へき地では、都市部と比べてショッピング施設や娯楽施設が少ないなど生活の利便性が低いことや、医療機関が少なく他職種との交流が限られることなどが、若手の定着を難しくする要因のひとつになっていると思われます。
業務負担とワークライフバランスの課題
離島・へき地では、医療者不足に伴い看護師1人あたりの業務負担が大きく、夜勤やオンコール対応を多く求められることがあります。また、医師の数が少ないことや専門医が常駐していないために、看護師が幅広い役割を担うことになり、都市部の病院と比べて業務内容が多岐に渡る傾向にあります。
教育・研修の機会の不足
閉塞的なイメージから、離島・へき地ではキャリアアップのための研修機会などが限られ、専門的な知識やスキルを習得しにくい印象があるようです。実際、長期的なキャリア形成を望む看護師は、病院内での専門教育プログラムや学会参加の機会が豊富である都市部での就職を選択する傾向にあります。
医療機関の経営と財政の問題
離島・へき地の病院や診療所は経営が厳しく、十分な給与や福利厚生を提供することが難しい背景があります。大規模病院に比べて給与水準が低くなりがちで、都市部の病院と比べると待遇面での差が生まれています。
医療搬送と救急医療の困難
離島では高度医療が提供できる病院が少なく、緊急時の搬送が必要となるケースが多くあります。救急患者をドクターヘリや巡視船で都市部の病院へ搬送することが日常的に行われていますが、その対応を担えるスタッフが限られているため、緊急対応における個々のスキルや能力が求められます。
地域医療の特殊性と役割の広さ
離島やへき地の看護師は、病院内での看護業務だけでなく、訪問看護、保健指導、地域住民の健康管理など幅広い役割を担っています。また、細分化された病棟編成ではないことから総合的なスキルが求められるため、都市部の特定分野に特化した看護業務に慣れた看護師にはハードルが高く感じることもあります。
これまでお伝えしてきたように、離島・へき地における看護師の確保が難しい背景にはさまざまな理由があります。これらの課題を解決するためには、遠隔医療や派遣制度を活用したり、地域医療連携の強化を進めることで、看護師の負担軽減と定着率向上が期待されています。
しかし派遣制度の活用に関しても、課題は多くあります。派遣会社への仲介手数料が重なり経営が圧迫されることや、内部の正規看護師と派遣看護師との給料格差による不満が生じるなど、現場の苦悩の声も聞かれます。
そこでジャパンハートでは、2018年から独自の離島・へき地医療看護師支援事業「RIKAjob」を始めました。
離島・へき地医療看護師支援事業(RIKAjob)
RIKAjobとは国際医療NGOジャパンハートが運営する離島・へき地医療看護師支援事業です。 「R(離島・へき地)」「I(医療)」「KA(看護師)」の頭文字をとって名付けました。
私たちは、2010年に国際看護研修(アジア開発途上国や離島・へき地での臨床医療の実践)の一環として離島への看護師派遣を開始しました。その後、ある離島とのかかわりの中で離島・へき地の看護師不足が顕著であることを知りました。それを受けて、「医療の届かないところに医療を届ける」という理念に基づき、国内の離島・へき地の医療者不足に対応すべく、2018年にRIKAjob事業を開始しました。現在は18病院と提携し、看護師の派遣人数は550人を超えました。
日本国内には現在、看護師の人材派遣を行っている会社がおおよそ400社あります。一方、RIKAjobは社会貢献事業であり、人材派遣会社のような仲介手数料は取らずに運営しています。これは病院への経営負担をかけず、その分の予算等を院内整備や広報、スタッフ、患者へ還元していただきたいと考えているからです。
また、RIKAjobは「看護師のための離島・へき地医療支援」をコンセプトとしており、看護師がやりがいをもって働くことができること、看護師としてのスキルアップ・キャリアップにつながること、オンオフともに充実させることができる環境であることを中心に考えて、一人ひとりの看護師の想いに寄り添い病院をマッチングしています。
離島やへき地では専門分野に細分化されていない病院も多く、0歳から100歳まで全ての年齢層やあらゆる疾患に対応する力が必要です。また地域性が高く、患者と看護師の心理的な距離が近いことも特徴です。そのため、離島やへき地で働くことにより、看護師としてのアセスメント能力や対応力が高まるほか、新しい看護観の形成につながり、さらにその後のキャリア選択の幅を広げることができると考えています。RIKAjobで看護師を派遣することにより、離島・へき地の病院の人的不足の改善、業務効率の上昇や時間外労働の減少、リスク管理などの業務改善などが期待されることはもちろんですが、離島・へき地で働くことは看護師にとっても非常に価値あることと考えています。

看護師の人生と地域医療をつなぐ新しい働き方 ―RIKAjobの特徴
ここからは、RIKAjobの特徴についてお話しします。
伴走型のフォローアップシステム
離島・へき地で働くことへ不安を抱く方も多くいます。そのため、離島医療の経験のある看護師による病院のマッチングおよび定期的な面談など、フォロー体制を構築しています。派遣希望の方は病院選定にあたりオンライン面談でマッチングを行います。また派遣者が興味のある病院の看護部長とのオンライン面談を設定し、派遣にあたっての不安を解消する機会もあります。派遣後は、1~2ヵ月後にフォローアップ面談を実施し、その後も希望があれば面談に対応しています。
多様なキャリア形成・スキルアップが可能
離島・へき地によって地域性や文化はさまざまであり、取り組んでいる医療の特性も異なります。RIKAjob では18病院と提携しており、それぞれ看護師が興味のある地域や専門(訪問看護や無医村診療、救急看護、手術室看護など)、病院とマッチングができます。看護師にとって自分に見合った場所を見つけることも楽しみの一つとなっています。
離島ホッピング
RIKAjobでは奄美大島群島内の複数の病院と提携しており、いずれも同系列であるため、奄美大島群島内においては、最低3ヵ月のスパンで複数の離島やへき地の病院を連続して活動することができます。 病院が変わっても、転勤扱いとなるため新たな入職手続きは不要の上、移動費のサポートや賞与や有休休暇などの福利厚生も継続されます。
災害活動に参加する仕組み
離島・へき地医療を通して培った高いアセスメント能力や対応力を活かせる場のひとつとして、災害医療の現場があります。RIKAjobには「災害支援スキーム」という枠組みがあり、 平時は離島・へき地医療へ従事し、有事(発災時)にはジャパンハートの災害支援・対策事業(iER)の医療チームメンバーとして、災害医療現場で活動する仕組みを構築しています。その仕組みを構築した背景には、発災時看護師として医療支援活動をしたい思いを持つ人が多くいる一方で、急な勤務変更や長期休暇の取得が困難などの理由により、災害支援に興味があるものの、平時の仕事との両立が困難なため諦めざるを得ないという現状があります。RIKAjobでは災害支援スキームにより、看護師が離島・へき地で働きながら、災害支援にも参加できる形を実現するとともに、災害支援活動における人材確保にもつなげています。災害支援スキームに関しては、また別の回で詳しくお伝えします。
* * *
看護師の人生と、離島・へき地医療の現場のいずれも豊かにする「RIKAjob」に関する情報を発信していきますので、ぜひご覧ください。次回は、離島で実際に活動する看護師の様子をお伝えします。
1)小谷和彦,前田隆浩,春山早苗ほか:離島におけるへき地診療所とへき地医療拠点病院の医療体制と診療に関する全国調査.令和4年度 分担研究報告書,p1-2,2023,〔https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202206013A-buntan1_0.pdf〕(最終確認:2025年2月27日)
2)長崎県:離島・へき地における医師・看護師確保の充実について.令和5年度政府施策に関する提案・要望書,p.104,2022,〔https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2022/06/1654686501.pdf〕(最終確認:2025年2月27日)
3)楠元裕佳,八代利香:へき地医療拠点病院におけるへき地の看護職への支援の実態と課題.日農医誌 70(5):460-473,2022,〔https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrm/70/5/70_460/_pdf〕(最終確認:2025年2月27日)
4)総務省総務省地域力創造グループ過疎対策室:過疎対策の現状と課題,p.1,2017,〔https://www.soumu.go.jp/main_content/000513096.pdf〕(最終確認:2025年2月27日)
.jpg)
2004年、創設者・吉岡秀人(小児外科医)が自身の長年の海外医療の経験をもとに、医療支援活動のさらなる質の向上を目指して設立した「日本発祥の国際医療NGO」。東南アジアを中心とする国内外で、小児がん手術などの無償の高度医療含む治療を年間約4万件実施しており、累計数は35万件を超える実績があります。これらの活動は全て「未来の閉ざされた人たちに、明るい未来を取り戻す」ことを目的としています。
2025年10月、カンボジアに「ジャパンハートアジア小児医療センター」を開設予定。この新病院は、カンボジアや周辺国の貧困層の子どもたちに高度な小児医療を提供し、命を救うことを目的としています。



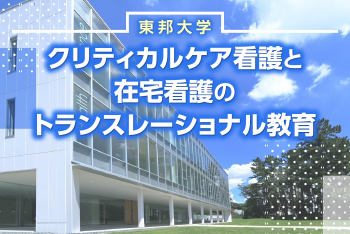
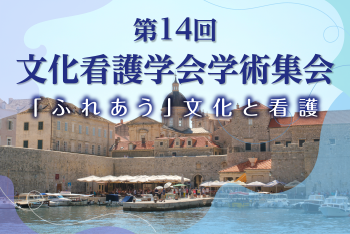

_1678352053026.png)