へき地医療の実態とは?
日本各地には、医療資源が限られたへき地が点在し、地域の医療を支えるために日々工夫が重ねられていますが、ジャパンハートが提供する離島・へき地への看護師派遣支援プロジェクト「RIKAjob」もその一端を担っています。
本記事では、青森県大間病院での活動を通してへき地*医療での看護師の役割、現場での工夫、そして地域医療の魅力に迫ります。
へき地とは、「無医地区※1」、「準無医地区※2(無医地区に準じる地区)」などのへき地保健医療対策を実施することが必要とされている地域
※1 無医地区とは、原則として医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点としておおむね半径4kmの区域内に50人以上が居住している地区であって、かつ容易に医療機関を利用することができない地区
※2 準無医地区とは、無医地区ではないが、これに準じて医療の確保が必要と都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた地区
※3 「無医地区」及び「準無医地区」を有する都道府県は千葉県、東京都、神奈川県、大阪府を除く43道府県
[厚生労働省医政局地域医療計画課:疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について,〔https://www.mhlw.go.jp/content/001103126.pdf〕を参考に作成]
へき地医療の特徴
へき地医療には、離島医療と共通する課題も多い一方で、異なる特徴もあります。
離島では海や空を使った移動手段が主であるため天候の影響を受けることが多く、専門医不在・物資備蓄の制約が顕著です。一方、山間部などのへき地では本土とつながっているため緊急搬送は可能ですが、唯一の道路が雪や災害で寸断されれば「陸の孤島」と化すリスクがあります。
どちらも医師・看護師の人手不足に悩まされ、住民の高齢化が進んでいたり、慢性疾患を抱える患者が多い地域であるため、その対応が大きな課題です。それでも、へき地の現場では、少数精鋭の医療チームが地域住民の生活を支えるために創意工夫を凝らして日々活動しており、離島医療とはまた違ったへき地ならではのやりがいと魅力、そして仲間との協力体制が存在します。ここからは、へき地医療を支えるある病院における看護師の働き方を例としてご紹介します。
離島・へき地医療の医療者確保に関する課題に関してはこちら(第1回記事)、離島医療の課題に関してはこちら(第2回記事)をご覧ください。
大間病院(青森県)―「陸の孤島」を支える本州最北端の病院
本州最北端、青森県下北半島の突端に位置する国民健康保険大間病院(下北郡大間町、以下大間病院)は、周囲を海と山に囲まれ道路網が限られるこの地域において、地域医療の砦です。大間町と隣接する佐井村・風間浦村を合わせた約7,000人(2025年4月)の住民の健康を預かり、外来診療から病棟看護、救急対応、訪問看護、在宅診療(看取りを含む)、そして無医村診療まで幅広い医療サービスを提供しています。内科系疾患を中心に診療し、対応困難な場合は隣町むつ市の病院(車で約1時間)や青森市の基幹病院(車で約3時間)へ患者を搬送します。しかし、冬季には豪雪で道路が閉ざされることもあり、ひとたび道が遮断されれば大間は「陸の孤島」と化してしまいます。陸続きではあるものの、地理的条件は離島に匹敵する厳しさです。このような環境下で、大間病院の医療チームは地域に必要なことは何でも担う覚悟で臨んでいます。
へき地医療を支えるマルチプレイヤーの看護師
へき地にある病院は、職員の数が決して多くはありません。大間病院も職員数が限られるため、看護師が外来・病棟・透析・訪問看護・搬送業務などをローテーションしながら担っています。まさにマルチプレイヤーです。
チーム全員でマルチロールをこなす
病棟は一つですが、地域唯一の病院であるため、脳卒中や消化器・呼吸器疾患、婦人科系などさまざまな疾患を持つ、急性期から終末期までの患者が入院しています。また配属場所以外でも人手が必要な場合、フレキシブルに応援に入ります。なお、通常訪問看護ステーションは独立した施設ですが、大間病院では病棟に訪問看護チームがあり、平時は病棟に勤務する看護師たちが、訪問日には訪問看護に出向きます。慢性的な人員不足がゆえに、“当たり前のように”マルチプレイヤーとして業務もこなす柔軟性が培われています。
さらに、大間病院には医療ソーシャルワーカーが不在のため、退院支援の調整も看護師が担っています。尿カテーテル抜去後の排尿確認なども、ポータブルエコー(超音波検査機)を使って自ら確認するなど、医師へ報告・相談する前にできることは行う工夫も見られます。大間病院ではほかにも、臨床検査技師が不在の時間帯には医師自ら採血検査の機械操作を行い、X線撮影や場合によってはCT撮影までも担当するといったように、看護師が他の職種の役割も包括的にこなしながら、看護師のみならず医師も含めたチーム全員が必要に応じてマルチロールを担っているのです。
巡回診療に赴くことも
大間病院は、地域に医師がいない「無医村」への巡回診療も重要な使命として担っています。週1回、医師1名と看護師1~2名が車で片道1時間以上かけて、無医村である佐井村の診療所に赴き、診療を行っています。道中は、上り下りの多い山道ですが、辿り着くと顔なじみの患者が談笑しながら待っているアットホームな雰囲気です。往復の移動時間を考慮すると、診療時間は1時間程度と限られますが、たとえ無医村であっても、住み慣れた地域で生活を続けたい高齢者にとっては貴重な機会となっています。
大間病院では医療者が少ない一方で、地域住民との距離が近く、個別性を踏まえた寄り添った看護をできることが魅力です。たとえば、終末期であればご本人が過ごしたい場所ややりたいことなどを汲みながら、家族と多職種がチームとなって、ご本人やご家族の希望を実現できるように尽くします。
足りないからこそ、助け合う~へき地医療で育まれる看護師の本質
このように住民に寄り添う医療を提供する大間病院ですが、慢性的な看護師不足は深刻で、これまで12名の看護師をRIKAjobから派遣しています。大間病院で働く看護師はマルチプレイヤーであることが求められますが、「できることは何でもやる」という前向きな精神がチームに根づいており、お互いを助け合いながら、こなせる業務を増やしていくことで看護師としての能力も自ずと底上げされます。さらに自分たちで地域医療を支える誇りと連帯感があります。
へき地の医療は、人手や設備面が十分ではない環境ですが、チームの使命感や連帯感で、足りない部分を個々が埋めようとすることで、看護師としての能力や責任感も育っていくのです。それが、へき地医療の魅力のひとつです。
へき地で活動する看護師の声
ここからは、実際にへき地医療に従事する看護師の体験レポートをお届けします。 へき地で働く看護師の不安や悩み、そしてそれを乗り越えて見つけたあたたかい気づきややりがい――この体験談を通して、少しでも何かを感じていただけたら嬉しいです。
Bさん(愛知県出身 看護師8年目)
はじまりは、ひとつの“問い”からでした。
「私の看護って、なんだったっけ?」。ICUで慌ただしい日々を過ごしていた私は、ふと立ち止まったとき、自分の看護観を見つめ直したくなりました。患者さんの思いをゆっくり聴く時間もないまま、治療を優先せざるを得ない。でも、“この人の人生”に、私はどこまで寄り添えているのだろう。そんな思いを抱えて出会ったのが、「へき地で看護師として働く」という選択肢でした。そして私は、青森県の大間病院へ向かうことを決意しました。
雪の町、大間での暮らしが始まります。到着したのは、海にも氷が張る真冬の大間。津軽海峡から吹きつける風は冷たくて、しかしフェリーターミナルで出迎えてくれた大間病院の看護師長の笑顔は温かかったことを覚えています。「こんなところに、本当に病院があるの?」。最初はそう思うほど、町は小さく静か。でも、スーパーも薬局もあって、暮らしには不便がない。そして何より、ここには地域の医療を支える人たちの熱い思いがありました。
「できることは、なんでもやる」。それが大間病院。配属初日から驚かされたのは、看護業務の幅広さです。病棟勤務に加え、訪問看護、1時間以上かけての転院搬送、退院前訪問……。ひとつの業務に専念するというよりも、「必要とされるところに入る」という感覚でした。たとえば胃瘻の造設に立ち会ったときも、前処置・搬送・処置後のケア・家族対応……、すべてを看護師が担っていました。「ここでは、分業という概念がないのかも」。それが正直な感想でした。でも、患者さんや家族の人生にまるごとかかわれるという実感が、そこにはありました。
そして外から来た私を、誰も“外の人”にしませんでした。「私はよそから来た人間だから、地域に馴染むのは難しいかも」。そう思ったのは最初だけでした。大間の看護師さんたちは、私の経験や価値観をありのまま受け入れ、対等な仲間として迎えてくれました。スノーブーツを履いて訪問に行くなんて初めて、雪かきしてから夜勤に入るなんて想像していなかった。そんな私の不慣れも、笑いながら見守ってくれる温かさ。地域の方も、「どこから来たの?」と気さくに話しかけてくれて、“外の人”から“一員”へ変わっていくのを感じました。
私たちが支えるのは、「人と人」の関係。大間町、佐井村、風間浦村――、この地域の住まいは雪国ならではの古い造りで、冬は足元も滑りやすく、ADLが低下すると暮らしにくい環境です。病棟は1つ、高齢者施設も3つだけ。入院や介護が必要になると、住み慣れた場所を離れざるを得ない人もいます。だからこそ、大間病院の看護師は、地域の暮らしを熟知して、患者さんの「その後」まで見据えて動いています。ソーシャルワーカーが不在のなか、地域資源を把握し、消防や介護施設と日頃から情報共有を行いながら、患者と家族の不安をひとつずつ取り除いていく。「足りないものは、自分たちで補う」。そんな姿勢が、大間病院には当たり前のように根づいているのです。
「この地域の一員として、私は何ができる?」。赴任から1ヵ月経ってもまだまだ戸惑うことも多く、毎日が学びの連続です。でも、そんな私にとって何よりの支えになっているのが、大間病院のスタッフの一体感です。それは医療者と患者という枠を超えて、「人と人」でつながる関係。「地域の人のことを、一緒に本気で考える」その姿勢に触れるたび、自分も地域の一員になりたいという思いが強くなっていきます。
休日には病院から貸してもらった車で、青森のあちこちへ出かけるようになりました。温泉、海鮮、絶景、そしてどこへ行っても出会う、人の温かさ。名前も知らない人との何気ない会話が、心をじんわり満たしてくれる。それも、この土地ならではの魅力だと思いました。
最後に、不便はないものの大間は決して「便利な町」ではありません。医療資源も交通網も限られていて、雪が降れば「陸の孤島」になります。でもこの場所には、「ここで生きていく人たちを、最後まで支えたい」と願う医療者たちがいて、「ここに病院があってよかった」と語る住民の声があります。看護師として、一人の人として、この町で過ごした時間は、私にとっての看護の原点になりました。
「患者さんの人生に、もっと深くかかわりたい」「生活に根ざした看護をしてみたい」「人と人として、地域とつながる医療を体験したい」そんな思いを抱いたことがある方は、まずは3ヵ月、RIKAjobを通して人間味あふれる環境での勤務を経験してみることが、結果的に看護師としてのキャリアの大きな転換点になるかもしれません。
.jpg)
2004年、創設者・吉岡秀人(小児外科医)が自身の長年の海外医療の経験をもとに、医療支援活動のさらなる質の向上を目指して設立した「日本発祥の国際医療NGO」。東南アジアを中心とする国内外で、小児がん手術などの無償の高度医療含む治療を年間約4万件実施しており、累計数は35万件を超える実績があります。これらの活動は全て「未来の閉ざされた人たちに、明るい未来を取り戻す」ことを目的としています。
2025年10月、カンボジアに「ジャパンハートアジア小児医療センター」を開設予定。この新病院は、カンボジアや周辺国の貧困層の子どもたちに高度な小児医療を提供し、命を救うことを目的としています。



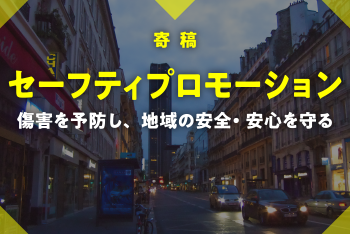
_1678352053026.png)
_1678352053026.png)
