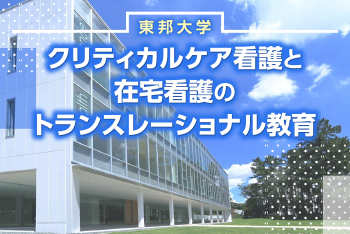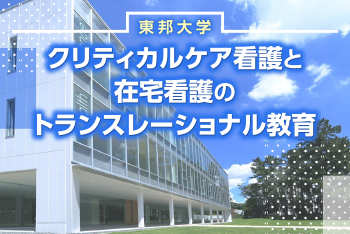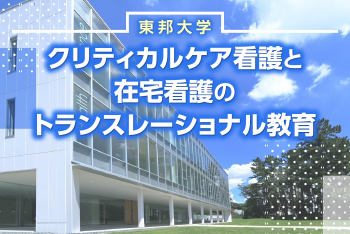文化看護学会(岡田忍理事長、千葉大学大学院看護学研究院教授)は2022年3月12日(土)、第14回となる学術集会(永井優子集会長、自治医科大学看護学部教授)をオンラインで開催した。テーマを「『ふれあう』文化と看護」と定め、同会では初となる一般へ向けた市民公開講座を実施した。市民公開講座は研究活動を通して得られた知見をわかりやすく提供するプログラムとされていることが多いが、同会においては学術集会参加者と全く同じプログラムを提供し、できるだけ専門用語を使わないようにすることで、看護以外のバックグラウンドを持つ参加者とも共に考えられる機会になるよう取り組んだ。
主な演題は以下の通り(座長・演者ともに敬称略)。
|
◆ 会長講演 |
コロナ禍だからこその“ふれあい”
永井優子集会長は学術集会のテーマでもある「『ふれあう』文化と看護」を題材に講演を行った。学生時代、講義の中で「清潔や適切な栄養摂取が保たれていても、ふれてもらえない赤ちゃんは心身が発達しない」というホスピタリズムに関する研究の話を聞き、ふれることやふれあうことの重要性を知ったことが同会の原点である、と永井集会長は語る。その後児童精神科領域で自閉症児らとかかわる機会を通し、ふれあうことはつらく苦しいものであると考えることも時にはあったが、ある写真と出会い、ふれたりふれられたりすることのあたたかさやぬくもりを感じたという。

講演の中盤では、存在としての適応戦略をとるために集団となって進化してきたヒトの生理的・文化的な歩みを通してふれあう暮らしがどのようにヒトや社会を変容させてきたのかについて論じ、後半では文化看護学の視点からより深く「ふれあい」を見つめた。
永井集会長が今こそ“ふれあい”を取り上げたいとしたのは、COVID-19のパンデミック(以降、コロナ禍)によって、社会全体が「ふれる」「さわる」ことに対してより敏感になっていると感じたためだ。同会は、看護職が人々の暮らしや考えの背景たる文化への感受性を高め尊重することで、受け手と看護職双方が心地よさや安らぎ、満足感を得られる看護実践を見つけられるよう目指しているが、そのために必要な「受け手との間の節度のある相互交流」が、コロナ禍によって大きく制限されてしまっているのが現状である。永井集会長は、「この状況に対して複雑な気持ちを抱くことはあるが、誰が抱くどんな感情も間違いと否定されるものではない」とした上で、文化的な看護のための相互交流には絶対的な客観が存在せず、看護の受け手から見た主観的な認知から逃れられないからこそ、看護職には誰とでも波長を合わせて受け手の理解を可能とするような実践力が必要であると考えテーマを定めたと話した。
“さわる”“ふれる”を通した深いコミュニケーション
看護系の学術団体からの講演依頼は初めてだという伊藤亜紗准教授。簡単には言葉にできない曖昧なものについて美術・芸術などを通して深く考える学問「美学」を専攻しているが、18世紀ヨーロッパで学問として確立された美学に対して自身の生活や経験とのギャップを感じたといい、美学では珍しいとされるフィールドワークを通して障害者や病気を持つ人らの話を聞くことで、彼らだからこそ得られる世界の見え方や体の使い方などについて研究を行ってきたという。
当日は「『さわる』と『ふれる』から考える接触面の人間関係」というテーマで基調講演を行い、一方的でモノに対する接し方のような印象を与える“さわる”と感情を加味した双方向的なやり取りのイメージがある“ふれる”について、直接的な接触、何か別のモノを通して起こった接触、コミュニケーションの形態としての“さわる”“ふれる”接触など、様々な事例から捉えた。伊藤准教授は「物理的な接触がかなり制限されるコロナ禍の時代だからこそ、物理的な接触を超えた“さわる”“ふれる”の可能性を開拓していく想像力や感覚を鍛える時代なのではないか」と締めくくったのち、質疑応答の時間を設け、参加者たちからの疑問や意見に応えた。
ある聴講者からは「学生を含め、人々がふれることに消極的になっている傾向があり、コロナ禍でますます強くなっている」という声が寄せられた。伊藤准教授は大学の教育現場で感じることとして、「多様性が増す世界の中で学生のコンプライアンス意識が高くなり、自身の言動や行動に対して配慮・検閲する意識が高まっていることから、お互い立ち入らないようにしようとする表面的なコミュニケーションが増えているように思う」と話す。永井集会長も伊藤准教授の見解に同意し、「人と接することに対して若い人たちが臆病になってきている」として自身が学生らに感じている印象を語った。その後も数多く質問や感想が寄せられ、看護学の外側から“ふれる”“ふれあう”ことについて考える貴重な機会となった。
医療職も看取りの文化・死の文化の担い手
大湾明美教授が座長を務める教育講演は、市民講座の一部として一般にも公開された。人類学を専門とする田中大介教授が演者となって「看取りと葬送の変容 -「死の文化」について考える-」という題目を定め、根源的な問いかけである「死」について文化人類学視点から捉えることで文化実践としての看取りと葬送について、聴講者らと共に考える機会とした。田中教授は様々な文化的遺物や芸術作品などから国内外のかつての人々がどのように「死」「弔うこと」を捉えてきたかを解説するとともに、先人の知恵や葬送に関する文化を通して、人の死は周囲の社会構造という個人を超えたつながりやふれあいのシステムにも影響することを論じた。
また、COVID-19の影響や独身世帯の急増、自宅ではなく病院で亡くなる人の増加など社会構造の変化によって“死”の切迫感や捉えられ方が昔とは形を変えている中、自身のフィールドワークを通した経験から、「現代の死の文化の担い手は、時間的・空間的に現代の死に近い看護職のような医療現場の人たちなのではないか」という考えを展開し、「それぞれの時代、それぞれの場所で死者の亡骸や近しい環境にある人を受け止めてケアする固有の実践様式があって、それが文化としてとらえられるものではないか」として講演を締めくくった。
大湾座長は講演に関し、田中教授が報告した葬儀業者が遺族の「弔いたい」という希望を叶える柔軟な実践を行った事例についてふれ、「医療や介護が行っている看取りや死に関するケアにも共通するものがあるのではないか」と述べた。
様々な立場からいまの医療を見つめる
同じく一般にも公開されたシンポジウムでは、上野まり教授が前半、永井集会長が後半の座長を担当した。テーマを「新型コロナウィルス感染症パンデミックによる看取りと家族ケアの変容」と設定し、入院治療を担う立場、在宅ケアの立場、地域住民の相談を受ける立場からそれぞれ福田氏、鶴岡氏、渡邊氏がシンポジストとして登壇した。冒頭、上野教授は「超高齢・多死社会においてCOVID-19とともに暮らす新たな時代の看取りや家族ケアについて市民を含む聴講者らと考え、希望をもって前を向き暮らしていける方策を考えていきたい」と挨拶。その後は福田氏、鶴岡氏、渡邊氏の順番でそれぞれの立場から看取りや家族ケアの実践について話した。
COVID-19で入院患者と家族のふれあいも難しく
入院治療の現場について話した福田氏によると、患者と家族が最期までの限りある時間を十分に過ごせるよう確保したいという意向の一方、家族の来院や面会は院内感染リスクを増やし、他の患者にとっては不利益を被る可能性もある点から、看護師たちも葛藤や心苦しさを抱えていたという。対応については都度院内の専門的な部署などを含め、多職種で状況を多角的に判断して行った。また、COVID-19に感染した患者の家族は様々な反応を見せ、「患者のそばにいたい」という気持ちと入室による自身の感染や他者への伝播の恐怖の間で葛藤する家族、患者を隔離してひとりにしてしまうことに罪悪感を抱く家族、身内が院内クラスターの発生源となるのを恐れ隔離することに安心感を抱く家族など、多様な考え方を窺い知れたという。どの場合においても看護師は家族の意向と価値を大切にすることに徹し、どのような選択肢をとっても罪悪感や後悔につながらないよう支援することに努めたと報告した。
その支援策として、患者と家族の“ふれあい”の架け橋となる看護ができるよう、限られた環境の中で家族の希望を叶え看取りやその後について一緒に考える時間を確保するために様々な取り組みを行ったという。福田氏は、家族を看取る人のケアという点で本質的な視点は変わらないが、制限下の中でふれあいを断念するケースもあれば、心のふれあいや絆を大切にするケースもあり、自分たちはどうかかわるのか、面会の多様性をどのように取り入れていくのかなどのブラッシュアップが求められるとの考えを示した。加えてCOVID-19の場合は周囲に病気を公開しづらく状況を共有しにくいことから、家族のグリーフワークの非充実や複雑性悲嘆といった精神健康的問題の増加が心配され、こういったケースについて病院から地域に広げて対応していくことができるのかも模索していきたい課題であると述べた。
地域・在宅医療の立場、健康支援サロンの立場
地域・在宅医療に約20年にわたってかかわってきた医師であり、栃木県で「つるかめ診療所」の所長を務める鶴岡氏は、コロナ禍における在宅ケア現場で起こっている看取りの変化として「患者周辺のご家族の数が確実に減っている」「看取り後のグリーフケアの方法が変わっている」ことを指摘した。前者については患者との距離感がある人もおり、話を聞いてみると「病院での感染対策と同様にしなければならない」と考える人、自分が感染への恐怖を感じているために距離を取る人など、様々な考え方があるのだという。また、同診療所では看取りの1ヵ月後を目安に家族の元を訪れ、その後の近況など聞き取るようにしていたが、感染の状況によっては対面でのグリーフケア対応ができず電話などを活用することがあると話した。
NPO法人「サロン みんなの保健室」を運営する渡邊氏は、サロンの立ち上げの経緯や、サロンでの取り組みについて語った。40年以上にわたる看護師経験の中で、患者の社会背景や家庭環境、生きてきた時代の背景等によって生じた格差により健康への意識やサービスに関する知識に格差があること、セルフケア不足を解消し自己評価能力を向上させるために働きかけたくても業務に追われて忙しい看護師は指導や退院後フォローアップの時間を取れないということに問題を感じていた。かねてより“看護師の社会的役割”について考えていた自身の背景も相まって、人々の健康保持のため病気の予防段階(未病段階)から介入できないかと考え、気軽に立ち寄れる健康支援の拠点として同サロンを立ち上げた。サロンでは血圧や握力、体組成などの測定のほか、地域の老人会との交流や健康相談、セミナー、看護職・福祉職希望者への進路相談も行っている。
医療の現場はウィズコロナ時代をどう捉えるか
コロナ禍による影響を感じるポイントは様々
座長を永井集会長に交代してのディスカッションでは、「業務や活動の中でCOVID-19への感染を周囲に明かせずメンタルへの不調を来すような例はあったか」という永井集会長の問いかけに対し、渡邊氏は「むしろステイホームで人とかかわれず落ち込みがあったり、筋肉が落ちた人が躓きやすくなったり体重が増えたりといった例のほうが見られた」と話す。直接的にCOVID-19に関連する可能性がある例でいうと、嗅覚や味覚がなくなったと訴える人からの電話相談や、感染が不安だからパルスオキシメーターを借りたいという相談者への対応を行ったことがあるそうだ。「感染は心配だから専門職に相談したいが、何事もなかったのに病院に行くことで感染するのは怖い」と思っている人や、病院で何を相談してよいのかがわからない人の拠り所として渡邊氏のサロンが機能していたことがわかる。
鶴岡氏は、コロナ禍が在宅医療という選択の後押しをしているとの見解を示す。コロナ禍前であれば「家族に迷惑をかけたくないから」と病院での看取りを希望していた人たちが感染を気にするようになったり、自分たちが介護やケアを行うことに自信がなく在宅医療に抵抗を持っていた家族が「面会できないまま別れるのは辛い」と考え在宅での看取りに踏み切ったりといったケースが見られるようだ。家族の中に、難しそうで最後まで患者をサポートできるかわからない、と不安があっても、実際に在宅医療をスタートすると医療者や周囲の人からの励ましなどもあり成功体験を積み重ねていくことで、気持ちの変化が生まれるのだという。“在宅医療”という選択へ一歩踏み出すことの困難さを、コロナ禍という大きな制限が逆に払拭させた格好だ。
入院治療の場で看護を担う福田氏は、患者と家族が面会できる機会が減ったこと、対面で話を聞くことができる場が失われたことで意思決定支援が難しくなっている現状を話した。患者の中でどのような治療を受けるか、または受けないかについて結論が出ていても、その背景などを家族や周囲の人から聞き取れず、患者の意図を汲み取る時間が十分に取れないケースが増えているのだという。
よりよい死や看取りのために
先の教育講演を行った田中教授は、福田氏の意思決定に関する発言に関連して「医療従事者の方々が、エンド・オブ・ライフ期を迎える患者や家族の不安や切迫感、複雑な感情をどこまで受け止め、引き受けるのか、それを判断する難しさがある」と考えを述べた。これを受けた永井集会長は、病院での看取りやコロナ禍の制限下で行われる葬儀などによって現代の人々にとっての“死”が昔よりも一般的なものでなくなっていることを指摘。アドバンス・ケア・プランニング(ACP、通称「人生会議」)などに注目が集まるとは言え、死を受け入れ残り時間をどのように生きるか、その後はどうするのかを考えるのに十分な時間が取れないのが現状であり、一般の人々が医療職に死や看取りに関する相談をすることに抵抗があるなかで、よりよい死や看取りのために医療職はどうかかわっていくべきかを問題提起した。
鶴岡氏は永井集会長の問いに対し、「医学に基づいて立てた見込みや予測といった事実を患者や家族と共有し、現状見込まれるゴールに対して必要な(不必要な)措置は何かを一緒に考えていくことは専門職にしかできない重要なこと。ただし強要はせず、現状の見込みを本当に受け手が知りたいと思っているかの確認はしなければならない」と述べた。
おわりに
これらの講演のほかにも、同学会では終日をかけて文化的観点から“ふれあい”や“看取り”、“死”などについて考えられるようなプログラムが組まれた。コロナ禍でふれあいの機会が失われ、医療職がこれまでのように五感を使った丁寧な看護を必ずしもできる環境ではないいまだからこそ、これまで人々が辿ってきた文化を丁寧に精査して見つめ直し、新たな時代の文化に寄り添うような看護実践の展開が広く求められるのではないか、とのメッセージが共有された会となった。
なお同会は、2023年3月19日(日)に第15回文化看護学会学術集会を実施すると発表した。千葉県立保健医療大学健康科学部看護学科の佐藤紀子教授が集会長となり、同学を会場として「人と人をつなぐケアの本質」をテーマに行われる予定である。
※第15回文化看護学会学術集会の詳細はこちらからご覧いただけます。