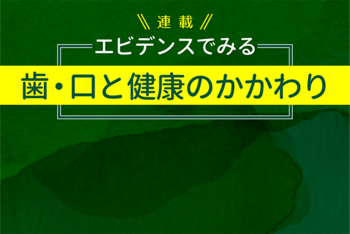「先生、何年?」
私が医者になってすぐの頃ですが、初対面の医者同士が必ず行う会話を不思議に感じていました。それは、どちらともなく「先生、何年?」と尋ねることです。言葉を足しますと「先生(は)、何年(卒ですか)?」という意味なんです。その答えですが、たとえば昭和58年卒ですと、「ゴーハチ」です、と答えます。私が医学部6年のときの年末年始、国家試験の勉強をしていたところ、勉強会仲間がA4のレポート用紙をどどーんと掲げながら急に部屋に入ってきて、「次の元号は「平成」でーす!」って叫んでました。小渕官房長官のマネですね。
というわけで、私は正確には平成元年(1989年)卒なんですが、このように聞かれたときには2通りの答えを用意していました。相手がおそらく先輩(つまり昭和年代卒)だと感じたら、「ろくよんです」と答えます。昭和64年は1月7日までしかなかったわけですが、相手が私のことを何年「下」の学年か計算しやすいように考えたわけです。逆に相手のことを後輩だと思ったら、「へーいちです」と答えます。こちらも相手が私のことを何年「上」か計算しやすいだろうと思うからです。
てな感じで厳密には昭和の時代には自ら医療行為をしてはいなかったわけですが、学生時代の病院実習は昭和の時代でしたし、使っていた教科書にも微妙に昭和の時代を感じさせる手技なんかが載っていました。これらの事実、語り継いでいかないとみんな忘れてしまうような気がしてきましたので、今回は「昭和・平成にはこんなことをやってたんですよ」という回でございます。
カエルやウサギでにぎわう産婦人科病院⁉
私が学生時代に使っていた産婦人科の教科書にはこんなことが載ってました。妊娠反応のところです。
今では薬局でも買える妊娠検査薬ですが、大昔は妊娠したかもしれない女性の尿をウサギやカエルに注射して、その反応を見ていたというんです。ウサギを使うのがフリードマン反応、カエルの方はマイニニ反応というそうなのですが、その反応の名前と動物種の組み合わせが「婦人科の試験のヤマ」だったんです・・・。ということは、産婦人科病院の検査室ではカエルがゲロゲロ鳴いてたり、ウサギがピョンピョン跳ねてたりしたのかぁと、そのときは想像していました。いえいえ、私が医学生の頃はもう、尿中hCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)の検査はできるようになってたのですが、少なくとも私が生まれた頃の産婦人科病院は本当にそうだったんだろうなと思います。東邦大学大森病院産婦人科の中田雅彦先生のブログ1)にも記述があります。ちなみに、中田先生は1990年卒だから、「へーに」(平成2年)ですね。
「カットダウン」からPICCが広まるまで
私の母の肘の内側には、ケロイドになった傷がありました。いつかどこかで怪我でもしたのかなとずっと思っていましたが、医者になってから、あの傷はカットダウンのあとじゃないかと気づきました。カットダウンという手技、私が医者になってからはもう、ほとんど見なくなっていましたが、昔は末梢血管に点滴路を確保する、いわゆる「ルートを取る」ときに、皮膚を切開して静脈が見えるようにして、その静脈を切断して中枢側に直接チューブを入れて結紮していたみたいです。教科書に載っていたのはたしか足関節あたり(内果)の図でした。美容的なことを考えると、うちの母みたいに肘の内側でカットダウンというのはどうなんでしょう。
ただ私が医者になった頃は、ちょうど中心静脈カテーテルが始まったころで、この手技を先輩から教えてもらってました。いまでは「CVカテーテル」といいますが、当時は「IVH」と言ってました。高カロリー中心静脈栄養(Intravenous Hyperalimentation)の略ですね。ただ、当時は普通の病室でCVカテを入れてましたし、エコーガイド下ではなくブラインドでやってたんです。今ではCVカテ挿入時にはマキシマルバリアプリコーションが当たり前で、ちゃんと感染対策をした上でエコーのある処置室で挿入しますよね。さらに今では、鎖骨下静脈のような中心静脈を直接刺すのではなく、末梢の静脈から長いカテーテルを中心静脈まで伸ばす、その名の通り「末梢静脈型中心静脈カテーテル」、略してPICC(ピック,Peripherally Inserted Central venous Catheter)が汎用されるようになりました。母も晩年、入院したときにはPICCを入れてもらっていました。カットダウンから考えると隔世の感があります。
感染対策・滅菌いまむかし
感染対策といえば、私が医者になった頃は、MRSAが陽性の方(保菌者も感染者も問わない)には「カーテン隔離」をしていました。さらにカーテンの下の床に目印となる黄色いビニールテープを貼って、それより中に入るときにはスリッパを履き替えていました。今では手指衛生の徹底、そしてゴム手袋の適切な使用と高頻度接触面の消毒で対応すると思いますが、当時はそういうことがわからなかったんだと思います。また当時は、B型肝炎ウイルスのキャリアーの方に観血的な処置をする場合、術者は手袋を二重にしていました。かといって救急外来に血だらけで運び込まれてくる交通外傷の患者さんには手袋をせずに対応していたわけで、その患者さんが入院してからB型肝炎ウイルスのキャリアーであったことが検査でわかることもしばしばあったので、この「二重手袋」の感染対策をなんだか変だなと感じていました。患者由来の湿性生体物質はあまねく感染性があるものとして取り扱うという「標準予防策」の考え方を知ったとき、モヤモヤ感が晴れたことを思い出します。

さて、いつも国試問題ですみません、図1は第104回(2010年施行)の医師国家試験の問題です。いわく動脈採血の図ですが、正しいのは1つだけ、さて? というものです。①は駆血帯を使っていますが、この問題は静脈ではなく動脈採血なので不要、というわけでバツ、④も同じように動脈採血なら止血のときに肘を曲げないのでバツ、⑤は有名な原理原則で「リキャップ禁止」ということでバツなんです。そうなると正解は②と③の2つになるぞ、と思っていたのですが、厚労省の正解をみると、③は間違いなんだそうです。
なぜ、と思ったら、なんと「手袋をしていない」から、とのこと。
うむむう・・・。実は今から15年前にこの国試問題が出題された当時、採血するときに私、手袋をしていなかったんですよ。血管の位置がわかりにくいからとかなんとか言い訳をしながらですが・・・。採血時の手袋着用は今では当たり前ですよね、でも当時はまだまだ一般的ではなかったように思います。そう考えると、私より先輩の外科の先生が若いときは、外科手術でも滅菌手袋をしていなかったんだそうです。もちろん手術時手洗いはしてたんでしょうが・・・。そういえば手術時手洗いも変わりましたね。昭和の時代はブラシを使って10分以上ゴシゴシ洗え、とくに爪の間は積極的に洗えと言われてました。洗った後はだいたい、皮膚がヒリヒリしていました。そして最後に泡を落とすときは滅菌水を使っていたんです。今ではラビング法が主流ですよね。そして最後のすすぎ水も水道水が一般的だと思います。いやあ、本当に変わりました・・・。
.png)
今回は「昭和・平成の医療遺物」を思いつくままに書いてみました。「あるある!」と思った方は私と同年代の方でしょうし、「なんですか、それ?」と思った方は令和世代の医療者ということになりますでしょうか。そういえば、そんなクイズ番組もやっていますね。その医療編があってもおもしろそうですね。
参考文献
1)中田雅彦:#5 妊娠検査薬―今昔物語.雅の徒然日記~教授室(中田雅彦)から綴るよもやま話です,2022年6月25日,〔https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/gyne/blog/2022/copy_of_hcg.html〕(最終確認:2025年3月13日)