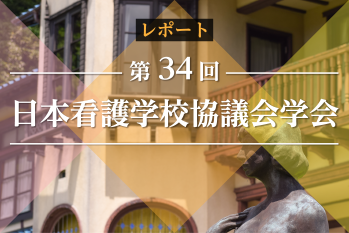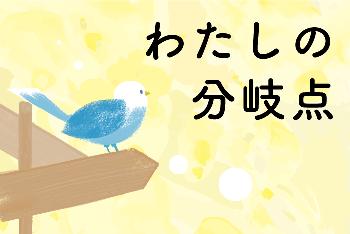はじめに
大学に入学し、未知の世界であった病院の電算化システムと出会い、医療情報システムに興味をもったのが1976年です。この頃の私は、病院や研究室にある様々な機器に興味津々で、触わっていると不具合に遭遇することが多々ありました。壊したかも…どうしよう…と思いながら恐る恐る申告すると、教授は「機械は使わなくても壊れる、使って壊れるなら本望」と言ってくださいました。また、講義では、「病気の治療は(これが最善だと)信じてするが、病理学は真実だ」と聴きました。うまく説明できませんが、治療はこうしている間にも状態・状況が変化しうる“今まさに生きている人”を対象に行うもので、一方、病理学は組織やご遺体からの最終診断を担うがゆえに、揺るぎない真実と言えるのだと理解しました。
大学院に進学した頃には、看護職は、研究活動を通して得たエビデンスのある真実を伝え、それが真実だと信じてもらえる人でなければならないと思うようになりました。教育に従事するようになってからは、「真実を信じてもらえる人として、未来を創造しながら誠実に向き合うこと」を大切に、学生たちに教えてきました。やはり専門職は、真実を信じてもらえる人でなければならないと考えています。
未来を創造する
20代や30代の頃、今の社会や働く環境をイメージしていたわけではありませんが、指示されたことや、しないといけないと思った目の前のことに真摯に向き合ってきました。そうすると、“しないといけないこと”が“したいこと”になり、周囲の指導や協力を得ながら“できること”が増えていきました。たぶん、人とのかかわりの中から気づきを得ることで、(なるかならぬかはさておき)未来が創造できるのだと思います。
医療情報システムの進化
医療情報システムは、1980年代に医事会計システムから、各部門への依頼業務のコンピュータ化が進み、外来のみならず、病棟においてもオーダリングシステムが稼働しはじめました。私は縁あって、1999年に誕生した電子カルテの開発に参画し、看護システムの稼働に立ち会うことができました。医療情報システムへの興味から看護システムを意識していた大学時代から、およそ20年後のことでした。それからさらに20年余りが経った現在は、2020年からのCOVID-19対策を契機に、オンライン診療が本格的に根づきはじめ、医療はオンラインでも叶うという考えが基本になりつつあります。機器の開発と共に、医療情報が共有・利用される範囲は部門単位から施設単位、そして地域単位へと徐々に広がり、都道府県単位または国単位で包括されて管理・利用する時代が来ました。
今では、ネットワークを活用して病院・診療所・訪問看護ステーション・薬局・介護施設等が診療情報を共有することで、質の高い医療・介護サービスを提供し、「ときどき入院、ほぼ在宅」の社会が実現しつつあります。また、医療関連情報の電子化や標準化が進んだことから、医療費や健康診断の内容を分析できるようになり、健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針により、全ての健康保険組合にデータヘルス計画の策定が義務づけられ、2024年度には第3期の計画がスタートします。
思い返せば1985年頃、私は名古屋市医師会で検討されていたホームケアサポートシステムにおいて、患者情報収集サブシステムについて考え、患者宅に設置する特殊端末の開発に没頭したものです。特殊端末は手づくりの試作品で、患者入力用キーパッドとコントロールボックスからなり、はんだごて片手に電子基板を組み立て、アセンブラでプロブラミングしながら、そして使う人を思い描きながらの悪戦苦闘でした。1997年からは情報ネットワークを活用し在宅支援システムやテレケアを検討しました。これらすべてが、現在の医療の姿につながっていたと信じています。
時代の移り変わりを捉える
2020年からのCOVID-19の大流行により、社会全般のデジタル化の遅れが露呈しましたが、大学ではオンライン教育が一気に進みました。
私が所属する島根県立大学では、2008年当時、文科省の「質の高い大学教育推進プログラム」として採択された「eポートフォリオによる自己教育力の育成~モバイル端末を活用した参画型看護教育で培うキャリア育成~」に取り組みました。この取り組みでは、学生全員にノートパソコンを貸与し、学内に整備した無線LANの環境下で、授業中も双方向で活用できる事業を展開したことを思い出します。
国の政策であったe-Japan*はu-Japan*に代わり、その後情報化社会(Society4.0)に続く新たな社会(Society5.0)が提唱されました。私たち看護職が、望む・望まないに関係なく、我が国そして世界を取り巻く環境は変化しています。与えられた環境に甘んじるのではなく、未来を創造しつつ、より納得できる環境を提案することが重要です。
*e-Japanとu-Japan:e-Japanとは、すべての国民がICTを活用できる環境を整えることを骨子として政府が2000年に策定した、日本型IT社会の実現に向けた構想を指す。その後進として打ち出されたu-Japanは、ユビキタスネットワーク社会(コンピュータやネットワークが偏在し、必要なときにどこでも利用できる社会)の実現を目指して2006~2010年に実施された、ICTを推進するための政策である。
真と信
信じてもらえる人になる
真実を伝えるには、公表することです。研究的に取り組んだ調査や開発の成果は、論文にまとめて投稿することによって、真実であると伝えることができます。視察した内容や事業として取り組んだ内容も真実ですが、投稿論文として採択されるのは簡単ではなく、著者である私を信じてもらうしかありません。論文誌の編集者もまた、未来を創造しながら、著者を信じて採否を精査されるのだと思います。
学生に物事を教えるときも同じです。授業では、論文から最新知見を紹介し、変遷を伝え、学生たち自らがその先を描けるよう努めました。授業で話す内容は真実でしかありませんが、授業をしている私を信じてもらわないと真実が届きません。また、信じてもらえるかどうかは、普段のなにげない言動が重要であるように思います。
私が卒業研究を担当する学生には、毎年3月の学会での発表を促します。学会発表のイメージをもたない学生たちですが、私を信じて楽しそうだと思ってくれるようで、全員が発表に臨みます。卒業後は、私の授業内容より、学会の話題ばかりです。
学生の未来を共に創造する
学生に「いつ笑う?」「いつ笑いたい?」と投げかけることがよくあります。目の前の快楽を優先するのではなく、将来を見据えて今どうすれば良いかを考えてほしいからです。この言葉は、学生自身が納得して軌道修正するきっかけになっているようです。そして、学生に厳しいことを言う際に、自問自答することでもあります。今は受け止められずに嫌な思いをしても、きっと将来受け止め理解してもらえると信じられれば、嫌われても反感をもたれても、厳しいことを言ってきました。卒業は通過点で、その学生の将来を創造しながら、看護教育に携わってきました。
学生とかかわる際に、これは仕事(給料の範囲)か、お節介か、と自問自答することもよくあります。定年退職目前の今年の3月上旬、15年前に卒業した学生から以下のメールが届きました。
~前略~ 〇〇年に卒業した、旧姓〇〇です。 ~中略~ 卒業式では、真っ黒のスーツの私に、先生が自分のコサージュを外して胸に付けてくださったこと、今でも思い出します。〇〇年夏頃、大学院の受験を思い立ち、出願に必要な研究計画書の相談をメールでさせていただきました。その後、〇〇で勤務しながら、〇〇大学に入学、修士課程、博士課程と進学し、論文〇〇が〇〇学会で受理され、今年3月の修了式に出席できることとなりました。修了式では、前回と同じスーツを着る予定ですが、自分でコサージュを準備して出席します。 ~中略~ 研究とは何ぞやと少しでも学べたこと、仲間に出会えたこと、進学してよかったと思います。大学院に進学できたのは、先生のご指導(在学中も含め)があったからだと思います。先生との出会いがなければ、大学院に行こうとは思ってなかったと思います。 ~後略~
コサージュは全く記憶になく、私のお節介で、きっと迷惑だったと思います。もちろん研究計画書のことはしっかり覚えており、仕事の延長として全力で返信したと記憶しています。看護学博士の学位取得のお知らせは、とてもうれしいものでした。
また、卒業して10年以上経験があるとある専門職の方が、私に叱られたエピソードとして上司に話された内容を聞き、お詫びしたことがありました。今だから言えると話してくださいましたが、実習中に私がその方の首根っこをつかんで制止したらしく…、あのとき叱られなかったら自分は歪んでいたかもしれないと思い感謝しているとのことでした。これも全く記憶にありませんでしたが…、仕事として意識して行う言動より、無意識の言動が人の心には届き、感謝されるように思います。
教育の評価として国家試験合格は重要ですが、その先の、その学生の職業人生を応援したいと思って看護教育に携わってきました。卒業後に学生たちから良いこともそうでないことも連絡が来ること、学会で再開できること、教員冥利に尽きます。
おわりに
今回、紹介した内容は、私を育ててくれた貴重な経験や受けてきた教育です。自由に学べる環境と気づきをいただいた恩師には、感謝しかありません。私の教育観の軸は、マインドセットにあったと思います。人とかかわるには、信じてもらえる人でなければなりません。また、信じてもらう内容は真実でなければなりません。
博士号を取得した頃、「受けた恩は、受けた人には返せない」と恩師に言われました。恩はそんなに簡単に返せるものではないですが、師に返さなくても良い、それより次に続く後輩に伝えるものだと教えられました。経験という歳を重ね、私が受けた恩が縁あってかかわった学生に少しでも伝わっていれば幸いです。
今、65歳の定年を迎え、改めて安堵と感謝です。
1)厚生労働省ホームページ:データヘルス,https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21054.html,アクセス日:2023年2月20日
2)総務省ホームページ:u-Japan政策,https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ict/u-japan/index.html,アクセス日:2023年2月20日
3)内閣府ホームページ:Society 5.0とは,https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html,アクセス日:2023年2月20日


トリミング_1678759157085.jpg)