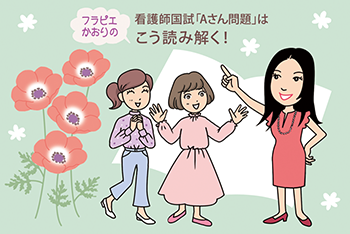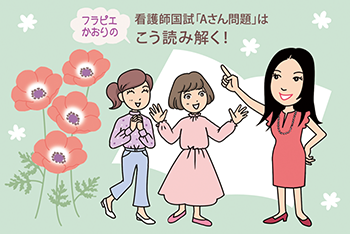このレポートでは、2021年11月15日に静岡県立大学大学院で開催された石松伸一先生(聖路加国際病院 院長)による特別講義「多数傷病者発生時の医療機関の対応」の様子をお届けします。本講義では、種々の災害や事件による多数傷病者に、救急医として対応してこられた石松先生ご自身の経験や心残りなどを踏まえ、今こそ医療・看護に携わるすべての方々に伝えたい大切なことが、ていねいに語られました。
(石松先生のプロフィールはこちら)
石松先生は、1995年3月20日に起こった地下鉄サリン事件において、傷病者640名を受け入れた聖路加国際病院の救急外来で陣頭指揮をとったことで知られている。本講義は、静岡県立大学大学院看護学研究科で学ぶ梶山千珠子氏(修士課程2年)が人為災害に関する研究の一環として石松先生へのインタビューを行った縁から企画されたが、梶山氏を指導する操 華子先生(同大学院 教授)は、事件当日、次々に運ばれてくる傷病者であふれかえった病院の廊下で、看護師として初期対応にあたっていたという。
多数傷病者を発生させる原因、状況
石松先生はまず、多数傷病者を発生させる主な原因である「CBRNE(シーバーン)」について説明した(表1)。
|
・「C」化学物質 (chemical):窒息剤、血液剤、びらん剤、神経剤、ヒ素 |
世界のいたるところで、戦争や紛争、テロリズムにおいて実際にこれらが兵器として用いられ、多くの死傷者を出してきた。日本でいえば、CBRNEでの多数傷病者の発生はまれであるが、多数傷病者を発生させる事故・災害は幾度となく起こってきた。
表2は、自然災害を含めて聖路加国際病院がこれまでに経験した多数傷病者発生事案である。多数傷病者が発生する場所として「交通機関(列車、航空機、バス、船など)」や「人の集まる場所(駅、劇場、ビル、学校など)」が挙げられる。石松先生によると、とくに人が多く集まる=多数傷病者が発生しやすい、と認識すべきだという。
| 発生日時 | 災害・事件等 |
傷病者総数 |
同院受診者数 (死者数) |
|---|---|---|---|
| 1995.3.20 | 地下鉄サリン事件 | 5,500以上 (13) | 640 (2) |
| 1996.10.31 | 深川第四中学異臭事件 | 43 | 4 |
| 1998.5.7 | X-JAPANメンバーの葬儀 (築地本願寺) |
不明 | 57 |
| 2000.9.11 | 日本橋郵便局薬物漏出事件 | 54 | 7 |
| 2001.6.14 | 入谷中学修学旅行集団食中毒 | 48 | 8 |
| 2001.9.1 | 新宿歌舞伎町雑居ビル火災 | 47 (44) | 2 (2) |
| 2003.2.27 | 集団ヒスタミン中毒事件 | 31 | 13 |
| 2004.1.31 | 東京駅硫酸漏出事件 | 8 | 3 + 2 |
| 2004.7.14 | 江戸川区北葛西光化学スモッグ | 17 | 3 |
| 2006.6.15 | 芝浦工大水酸化チタン発生 | 14 | 14 |
| 2008.6.8 | 秋葉原無差別殺傷事件 | 17 (7) | 2 |
| 2011.3.11 | 東日本大震災 | ― (19,747*) | 30 |
テロリズムによって目の前の命が脅かされるかもしれないという恐怖
ところで、2001年9月11日に起こったアメリカ同時多発テロ事件のむごたらしい映像は、今も鮮明に記憶している読者が多いことだろう。このテロリズムの1週間後、炭疽菌が生物兵器として用いられた事件がアメリカで起こった。いわゆる「アメリカ炭疽菌アタック」である。人獣共通感染症の原因菌として知られる炭疽菌は、特段めずらしい菌というわけではないが、酸素と接触して芽胞化すると死滅しにくくなるという特徴がある。治療薬はあるが診断に時間を要するため、感染後に重症炭疽病を発症して適切な治療にたどり着けずにいると、数日で命を落としてしまう。
「アメリカ炭疽菌アタック」は、芽胞化して乾燥し白い粉状になった炭疽菌が混入した郵便物が、アメリカ国内の報道関連会社や議員に送り付けられた事件だが、炭疽菌の吸入による死者も発生した。この事件に、石松先生はおそろしさを感じたと話す。テロリズムは、政治の中心地や人が多く集まるところで起こるものと思い込んでいたが、こうして郵便物とともに兵器が運搬されるということが現実に起こり、郵便物が届く場所ならばどこでもテロリズムが発生しうるということに恐怖を覚えたのだという。
この事件のあとしばらくは、同院でも炭疽菌の可能性を疑い対応せざるをえない事案がいくつか起こった。そのたびに石松先生は、もしかしたら重症炭疽病を発症して命を落とす患者やスタッフが出てしまうかもしれないと、最悪の状況を想定して措置を講じたという。幸い、炭疽菌は一度も検出されることはなかった。
こうした対応をとることができたのは、やはり同院において最大数の傷病者を受け入れた事案の経験があったからかもしれない。その事案こそ、地下鉄サリン事件である。

あの日、聖路加国際病院で何が起こっていたのか
地下鉄サリン事件において同院では、受け入れた640名の傷病者のうち2名が死亡という転帰をとり、また対応にあたった医療スタッフの23%に何らかの二次被害を思わせる症状が生じたという。石松先生は、多くの二次被害を招いた要因がどこにあったのか、当日の様子を次のように詳細に説明しながら分析した。
事件の第一報から、“爆発火災”と思い込んだ
午前8時16分、消防庁から第一報が入った。「地下鉄茅場町駅で爆発火災が発生したもよう」というものだった。爆発火災だから、熱傷や多発外傷の患者が搬送されてくるというイメージがこの時点で出来上がっていた。ところが、待てど暮らせどそれらしい患者は到着しない。
一方で8時25分に、「目が痛い」と訴える患者が3名ウォークインでやって来た。しかしこれから爆発火災の被害者が複数やって来るから、目の痛みだけの、しかも自力で来院できた患者なら少し待っていてもらおうと判断をした。これが最初のミスだったと石松先生は自戒する。なぜ、目の痛みを訴える患者が同時に3人もやって来た、ということから化学兵器による攻撃の可能性に思い至らなかったのか。頭の中が爆発火災という情報に支配されていたからにほかならないが、もしこの時点でこの3名の患者から状況を聞き取っていれば、もっと早くに事件の概況を知ることができたかもしれない。
誤った分析をしてしまった
8時40分、ようやく救急車のサイレンが聞こえてきた。搬送されてきたのは、息苦しさと目の痛みを訴える中年期の男性だった。爆発火災と聞いていたのに焦げ臭さはまったくない。それに患者自身は意識がはっきりしている。石松先生はこの男性の様子から、当時、軽犯罪でよく用いられていた催涙スプレーを想起した。だれかが駅や電車で催涙スプレーを噴射したのかもしれないと考えた。そして、想定されたような大ごとは起こっていないのではないかと、個人防護具をはずした数分後の8時43分、たまたま現場を通りかかったという人が自家用車に若い女性患者を乗せて来院した。女性は心肺停止状態であった。するとすぐに2人目の心肺停止状態の患者が運ばれてきた。石松先生はここで、「催涙スプレーでまさか心肺停止になるだろうか……」と頭の中が真っ白になったという。
病院全体が“緊急事態”を認識した
その後、救急搬送患者のみならず、ウォークインの患者も次々と来院してくるなかで、8時50分にはついに救急外来へのスタットコール(非常招集)が発動された。病室はあっという間に患者で埋まり、院内の礼拝堂も患者収容のために開放された。廊下には、患者を乗せたストレッチャーや付き添いの人があふれかえっていた。
そして9時30分、日野原重明 院長(当時)は、予定手術を含めた当日の通常診療をすべて取りやめ、傷病者の対応に専念するという勇断をした。当時はなんともあっさり決断してのけたなと思ったが、今、同じ院長としての立場から考えると、この決断は実に苦しく、よほどの覚悟を伴うものだったのではないかと石松先生は振り返る。この決断のおかげで、通常診療のために来院するはずだった患者への二次被害を起こさずに済んだのだ。
ようやく原因が明らかに
9時40分、消防庁から原因はアセトニトリル(有機溶媒の一種)らしいという情報が入る。しかし自身の幼少時代の経験から有機リン系の農薬に臭気があることを知っていた石松先生は、特有の強烈な臭いを感じなかったため、アセトニトリル以外の原因の可能性を探っていた。一方で症状からすると有機リン中毒も否定できないため、鼻汁や流涎の強い患者に対して硫酸アトロピンの投与を開始した。
10時30分には自衛隊中央病院より応援の医師・看護師が到着した。そして11時を過ぎる頃、「サリン中毒」が強く疑われるという有力な情報が入った。前年の松本サリン事件で被害者の治療にあたった、信州大学医学部附属病院の柳澤信夫院長(当時)からの電話での知らせだった。11時30分頃には、ようやく警視庁が「原因はサリンである」旨の記者発表を行った。
患者の身元把握にかなりの時間を要した
原因が明らかになったことを受け、午後0時から院内でカンファレンスを行い、治療方針や患者の帰宅の可否の判断方法を整理した。午後2時には軽傷の患者の診察を再開し、帰宅可能と判断された患者らは帰路についた。
しかし夜になっても院内には帰宅できない患者が多く残っており、そうした患者には入院をしてもらった。ここで、入院患者の名前すら把握できていないことが問題となった。来院時に受付をしているような状況ではなかったためである。そこでスタッフは、入院患者一人ひとりから名前と住所を聞き取り、家族に連絡をとった。そして聞き取った名前は、テレビ局を経由して公表した。これらによって、多くの患者が家族との再会を果たすことができた。患者を探しに病院を訪れる家族に向けては、患者の名前を模造紙に書き出して院内に掲示した。名前の公表に際してはスタッフ内で賛否があったが、携帯電話もSNSも普及していなかった当時、せっかく病院にやってきた家族が患者に会えないという状況を回避しようと、公表するという判断を石松先生はしたという。入院患者の名前の公表を終えたのは、夜の10時を回っていたという。
対応における問題点から得た教訓を実践に活かす
石松先生は、この一連の対応における問題点として、「情報」「分析」「二次被害」の3点を挙げる。
問題点①:情報
事件当日、同院の最寄り駅である築地駅前では道路は通行止めとなり、そこに応急救護所が設営されて各所からたくさんの救急車が集められ、各病院へ傷病者が搬送されるという大騒動となっていた。しかし石松先生は、スタッフとともにずっと病院で待機していたために、まさかすぐ近くの駅周辺がそのような状況になっていたとは夢にも思わなかったという。大地震で揺れを感じるわけでもなく、あるいは爆発音が聞こえてくるわけでもなく、正しい情報を得られないまま、ただ第一報を頼りに、それに備えることしかできなかった。現代のように情報通信技術が発達していなかったとはいえ、このように、発生現場の情報がまったく病院にもたらされなかったこと、また院内の内線電話もパンク状態となり、院内における情報伝達も不十分であったことが問題であった。加えて、犯人がどさくさにまぎれて院内に侵入した可能性があるなどのデマにも、少なからず翻弄されたという。正しい情報を得ること、それを関係各所に迅速に行き渡らせること、そして正しい情報を対外的に伝えること、これらが非常に重要であると認識した。
問題点②:分析
状況分析をしようにも情報収集がままならず、原因を特定するまでに時間を要した。柳澤先生によって有力な情報がもたらされたように、経験者や有識者からの情報提供は非常に有用であるし、同じく現場での迅速な分析や原因物質の同定ができること、そして中毒情報センターなどの情報源の活用も重要となる。
問題点③:二次被害
医療スタッフに二次被害を思わせる何らかの症状が生じたのは、防護が十分にできていなかったことが要因と思われた。神経ガス中毒の場合、通常の個人防護具の着用で完全に被害を防げていた保障はないが、自分が「催涙スプレーかもしれない」などと言ってしまったがために、個人防護具を装着しない状態でスタッフに対応させてしまった面もあると石松先生は言う。またとくに礼拝堂での対応を担当した医療スタッフにおける症状の発生率が最も高かったことについて、換気が悪い環境だったことが影響したと思われた。それ以降、化学兵器による災害の発生時には礼拝堂は使用しないという方針となった。
地下鉄サリン事件の教訓を踏まえた院内の体制整備
石松先生はこの事件の教訓として、「1.先入観を持たない」「2.自分の身は自分で守る」「3.患者の身元把握は重要」を挙げる。
これらを実践に落とし込むために、多数傷病者の受け入れ訓練を導入した。また明らかとなった問題点を解消するべく、その後院内の連絡系統を整備し、“災害”の基準と対応を整理・周知し、病院全体での連携・協力システムを構築した。
医療従事者として、念頭においておきたいこと
石松先生は、あの日の対応で、今もなお悔やんでいることがあるという。
同院で亡くなった患者の一人は、心肺停止状態でやって来た女性患者だった。まだ20歳代という若さだったという。亡くなった1年後、ご両親が手記を発表した。手記のなかに、自分の娘は聖路加国際病院に運ばれたが、当初は病院に電話するも該当者がいないと言われ、数日間ずっと、そこにいるはずの娘に会うことが叶わなかった、という主旨の記述があった。
入院患者に名前を聞いて回りはしたが、当然ながらそれは自分自身で名乗ることができる状態の患者のみであったため、身元がわからないままの患者が何名かいたという。彼女はその一人だった。このことが自分にとってはとてもショックだったと、石松先生は後悔の念を吐露した。本人が名乗れない、身元がわかる所持品もない、だからしかたないよね、で片づけてはいけない。こういう患者にこそしっかり対応しなければならないと強調した。
「ご家族からしたら、何日間も会えないまま、どこにいるかもわからず、不安な時間が続く。大切な人の命が危ないのではないかと心配を募らせ来院したのに、身元確認ができていないから面会は難しいというのではいたたまれない。せめて服装や所持品など、把握しうる情報をご家族に積極的に伝え、ご本人である可能性が高ければ対面できるように計らうなど、患者さんの状況が厳しくてもなんとか調整するのが病院の務めではないかと思うのです。」
もしもまた、あの日が訪れたら
本講義は「もし明日、あの日の惨事が再び起こったら……」という問いかけで締めくくられた。助けることができなかった2人の命を守れるだろうか、家族にもっと早く会わせてあげることができるだろうか、そしてスタッフの二次被害を防ぐことができるだろうか。こうした思いを、医療従事者として常に頭に、心においておかないといけないと、石松先生は強く聴講者に訴えた。
経験をつないでいくこと
講義終了後、石松先生、企画者の梶山氏、操先生とで想いを伝え合った。
梶山氏は、「地下鉄サリン事件当日の聖路加国際病院の様子を知り、あのような状況の救急外来の最前線で、患者さんの対応をする自分を想像したときに、どういうことをわかっていないといけないのか、どういうことができなければいけないのか、知識をもつことが重要だと改めて認識させられました。多くの医療従事者が教育を受ける機会を得ることも大切なのかもしれません」と、まっすぐに語った。
また操先生は「四半世紀以上の年月が流れましたが、あの日の病院の光景がありありと蘇ってきました。良くも悪くも、時間とともに記憶のなかで輪郭が不明瞭になっていたものが再び形を取り戻したような感覚です。梶山さんがこうして研究テーマに選んでくれたからこそ得られたものですから、感慨深いですね。彼女の研究のなかでは、石松先生と同じようにインタビューをさせていただいた方がほかにもいらっしゃいますが、みなさん快くご協力くださいました。26年が経ってもなお、現実としてあの事件は存在しているのだと、強く思いました」と話した。
これに対し石松先生は、「まさしく、人はそうして少しずつ忘れていくんですよね。医療従事者も新しい世代の方がどんどん入ってきますから、本当はたくさん学んでほしいけれど、経験を継いでいくことがなかなか難しい。だからこうして講義の機会をいただけたことは、私にとってもありがたかった」とほほ笑んだ。
凄惨な事件の記憶を呼び起こすのはつらいことだが、それでも、貴重な経験や大切な教えをつないでいくことの価値は計り知れない。
決して“有事”への備えではない
そして最後に石松先生はこのように穏やかに語った。「今回は、多数傷病者が発生したときの対応ということで、さも有事の特別なことのように受け止められた方もいらっしゃるかもしれません。しかし私としては、こうした対応は決して特殊なことではないと思っています。有事の対応は、あくまで日常の延長線上にあるものなんです。常日頃から、患者さんの安全を一番に考えることです。日々、目の前の業務に真摯に向き合うことで、さまざまに思考し、新しい発想や気づきが生まれる。それがきっと、予期せぬ事態が発生したときに活きてくるはずです。本当に大事なことは何か、情報があふれすぎている現代だからこそ、立ち止まって考えられるといいですね。」


_1643625006637.png)