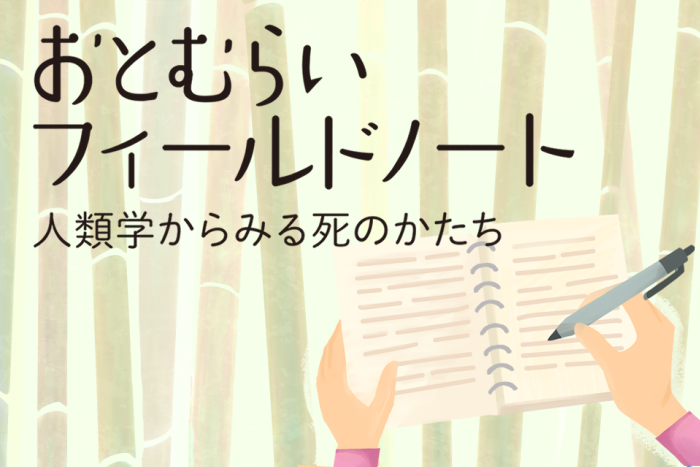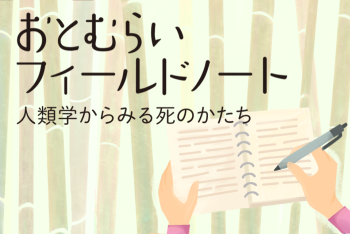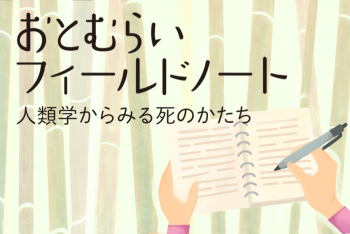まだ連載が始まったばかりというのに猛暑によって早くも命脈が尽きたかと思われたわたくしは、ようやく季節が秋へと遷りかわったおかげで辛くも一命をとりとめ、なんとか第4回へと漕ぎつけることができました。……などと「いのち」という言葉をさりげなく散りばめてみましたが、第3回の最後でお伝えしたとおり今回は「たましい」から「いのち」へと話を進めて、人間の生命というものがどのように考えられてきたのかということをあれこれとフィールドワークしてみたいと思います。
息をする、ということ
神様でも仏様でもない一介の小市民である私が「生命とは何か」などという壮大な問いに真正面から挑むのはそれこそ手に余るどころかバチが当たりそうなので、まずは前回にならって国語辞典を紐解きながら、一般的にはどのように受けとめられているのかということを探ってみましょう。
いのち【命】
生物の生きてゆく原動力。生命力。
[新村 出(編):広辞苑,第7版,p.201,岩波書店,2021より引用]
おお、何という簡潔にして平明な言葉。それだけでなく、このように生命というのものをなんらかの力やエネルギーとして理解するというのは古今東西に共通するものかもしれません。たとえば医学の祖として名高いヒポクラテスをはじめ、古代ギリシアの人びとは空気中に漂っているプネウマという存在を体内に摂り込むことによって人間は生きているのだと考えました。このプネウマというのはもともと「息」とか「呼吸」をあらわす言葉で、つまりはフワフワとした生命のエネルギー源を吸い込んでいるというイメージですね。
また厳密には区別されるものの、似通った意味をもつ言葉としてプシュケーやアニマという言葉を聞いたことがある方もいるのでは。いずれも紀元前の西洋文化に端を発する言葉ですが、とりわけアニマというのは現在の私たちにも馴染み深いものといえるでしょう。えっ、記憶にない? いやいや、今や老若男女問わず皆が大好きなアレですよ。絵に息を吹き込んで、生命を与えてイキイキと動かしている……そう、アニメ(ーション)。実はこれ、はるか昔から続く生命観にも連なる言葉なのです。
イキツキタケの謎
そう言えば、まさに「〇〇の呼吸!」なんて主人公たちが叫びながらパワーアップして鬼を倒すアニメも最近大ヒットしたような気が……。それはさておき、日本では臨終を迎えるときに「息を引き取る」という表現を用いますが、英語でも“breathe one’s last breath”、すなわち「最後の息をする」という同様の言い回しがあります。そもそも日本語の「いきる」という言葉は「いき(息)する」から転じたという説もあるほどで、生きる=呼吸をするというのは洋の東西を問わない生命観のイメージとは言えるでしょう。この「息をする」ということに関連した弔いの風習も数多く存在します。
その最たるものがイキツキタケ(息つき竹)。最近ではあまり見かけなくなりましたが、この風習が残されている地域も少なからずあると言われています。ここで、日本民俗学の泰斗として知られる柳田國男の『葬送習俗語彙』をちょっと参照してみましょう。
イキツキタケ
(前略)青竹の長さ六尺以上のもの二本の節をぬき、多く手伝い人の一人が持って葬列に加はり、そして埋葬したる土饅頭の中央に立てる風がある。それは息つき竹と呼ばれて居る。多分霊の通路とする為に必要だつたのではあるまいか。
[柳田國男:葬送習俗語彙(復刻版),p.140,国書刊行会,1975より引用]
このように、イキツキタケというのは亡骸を埋葬した墓の上に、節を抜いた竹を立てる風習を指します。しかし死者はもう息をしないはずですから、矛盾と言えば矛盾ですよね。ここで、「死んだと思って埋葬してしまったけれど、もしも生きていたらどうしよう……」と思って、とりあえず息はできるようにしておくという理由もおおいに考えられます。とくに脳波計も心電計もない時代であれば、死の事実というものは体表から感じ取ることのできる徴候で視認するしかありませんからなおさらのこと。
少し話は逸れますが、日本に限らず世界各地にある「通夜」の風習も、実は同じような意味合いをもつものでした。それは単にお葬式の一部分を構成する行事というだけでなく、「もしも蘇生したら」という強い思いと願いを抱いて、一晩かけて死者を見守りつつ過ごす重要な時間でもあったのです。
一方、先ほどの引用に記されている「霊の通路とする為に必要だつたのではあるまいか」という解釈も見過ごせません。前回の最後で「死んだ後も魂という存在がどこかにいるという思考や感情」について述べましたが、肉体が活動を停止した後も魂や霊といった存在は残っているとするならば、暗い土のなかで魂が閉じ込められたままになってしまいますから。
そのほかにも「生者と死者の世界を分け隔てる境界線として立てたのでは」とか、「土葬が主流だった時代は、何かお墓の目印を立てておかないと亡骸がどこに埋まっているかわからなくなってしまうから」といったものまで、このイキツキタケをめぐっては多種多様な議論がこれまで交わされてきました。

原書では「座棺を埋葬した土の上に竹を立てておいて、翌朝行って、その竹で棺をつついて、
成仏を確かめる。息を吹き返せば、この竹の節穴からでも息してくれやという発想が、
いまは行事の一つとして残っているのだ」という説明が付されている。
[芳賀 登:葬儀の歴史,巻頭図版p.4,雄山閣,1980より引用]
えっ、それでは結局正解はどうなのか、ですって? いやあ、それはもう「わかりません」というしかないのが正直なところ。しいて言えば、すべて正しいという気もするのです。とくに苦楽をともにした身近な者の生死については、人間はそんなに合理的で秩序だった思考や行動を組み立てられるわけでもありませんから。むしろ、そんな複雑さや不思議さこそが、人間らしさであるとは言えないでしょうか。
それでも今回は「息をする」という側面から「いのち」について語ってみましたが、もちろん人間の歴史で生命がどのように語られ、どのようにイメージされてきたのかということは、これだけで語り尽くせるものではありません。生命というものが複雑怪奇で摩訶不思議だからこそ、人間は豊かな想像力をはたらかせて「生命とは何か」を考え続けてきたのかもしれませんね。