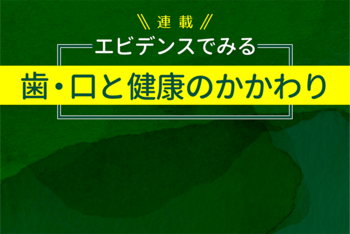前回まではメタレベルの正義論を扱ったが、今回以降は正義論の中身の議論に入る。そこで、功利主義・自由主義・平等主義など、個別具体的な正義の構想を順に見ていきたいのだが、これらの主義・構想を、対立する陣営にグループ分けする方法がある。今回は、そのような陣営区分の中でも最も有力な方法の1つである、義務論と帰結論の対比について考えよう。
頑固なのはどっちか
まずは、義務論と帰結論、それぞれの定義を明確にしたい。義務論は、ある行為やルールの道徳的な良し悪しを、その行為・ルールそのものの性質によって判断するのに対し、帰結論は、ある行為やルールの道徳的良し悪しを、それ自体に内在する性質ではなく、それがもたらす副次的な波及効果の良し悪しによって判断する。
仮に嘘つき行為は、道徳的に悪いとしよう。そして、減量に苦労しながらも成果の見えない友人に「痩せたね」と言うことは、誰も傷つけず、世界に優しさと平和を追加する効果があるとする。帰結論者は、「嘘も方便」と言うのに対し、義務論者は、そのような結果の改善は嘘つき行為の悪さを免除・緩和するものではないと言う。この点で、帰結論者は、要領がよく世渡り上手に、義務論者は頑固に見えるかもしれない。
最も極端な義務論者は、「世界が滅びようとも(つまり帰結が破滅的でも)、義務を果たすべき」というスローガンを掲げる。不器用でまっすぐな義務論者である、山口貴由『シグルイ』1の主人公、藤木源之助は、農家の子でありながら武士としての義を貫くことで、友も仲間も師も、実家同然の道場も、剣士の命である右腕も、最後は恋人も失う。彼の周囲の人は誰もが不幸になり、帰結は破滅的に最悪なのだが、それでも「ならぬものはなりませぬ」2 と言って、聞く耳を持たない。不器用でまっすぐな義務論者は、原理主義者になりやすいのに対し、帰結論者は結果のためならフレキシブルに原理を曲げる傾向がある。
しかし、これはあくまでも実践上の傾向にすぎず、理論的には、義務論と帰結論のどちらが、より頑固であるかは決まっているわけではない。私が午後のコーヒーのお供を、ザッハトルテにするかタルトタタンにするかは、少なくとも自由な社会においては、専ら私個人の専権事項であり、他人にとやかく言われるべき筋合いの問題ではない。しかし、仮に何らかのバタフライ効果3的 因果関係で、ザッハトルテにした場合の世界の人々の幸福の総量が、タルトタタンのそれよりも、わずかに多くなるとしよう。その多くなる量を、1人当たりにすると、無視すべきほど小さなものであるにもかかわらず、最も極端な全体主義的4帰結論者は、私にザッハトルテを選択することを命じる。タルトタタンを選ぶことは、些細な利己のために全体への波及効果を無視し、帰結の改善を犠牲にする、非国民的所業である、と。
ここまで頑固な帰結論を実際に採用するのは、最大多数の最大幸福を愚直に求める、極めて急進的な功利主義者くらいなので、実際にはあまり見かけない主張ではあるが、ともかく理屈だけで言えば、義務論と帰結論で、どちらが頑固でどちらが融通が利くということはない。
全体と個の間でバランスを取る
次に、生命倫理や公共政策という実践的な文脈で、義務論と帰結論の対立がどのように現れるのかを見てみよう。生命倫理において最も顕著な例の1つは、終末期における治療のあり方だろう。死期が迫って意識も戻らない者をどうするか。帰結論者は、本人のQOLの見込み、家族から社会全体まで、周囲に与える様々な負担を考慮して対応を決めようとするだろうし、義務論者は、そのような波及効果は度外視して、生命の維持5を絶対の義務と考えるだろう。
さらに公共政策の例として、新空港の建設を考えよう。上で極端な帰結論に、全体主義的という形容詞をつけたが、この文脈では、帰結論が全体主義と、義務論が個人主義と結びつきやすい。「全体」は、世界全体でも日本全体でも千葉大学全体でも良い。また、「個」は、一個人でも一大学でも一国でも良い。ともかく、「全体」対「個」の対比が、ここで重要になる。
ある新空港を建設すると、地域経済・国の繁栄・補償を受ける地権者の生活水準など、すべての者の状況が結果として改善するとしよう。帰結論者は、もちろん建設を支持する。しかし、個人の権利を絶対視する義務論者6は、そのような良き帰結を度外視して、建設予定地の所有者が、何の理由も示さずに土地を売らない自由を尊重する。このように、権利とは、個(一個人や一国)が、全体(国全体や世界全体)の政策に対抗し、それを覆すような拒否権としての性質を有している。
ここで重要なのは、このような実践的意義の高いケースでは、義務論寄りの立場と帰結論寄りの立場、どちらを取るにせよ、どちらかに極端に偏った考え方は好ましくないということである。次回以降取り上げる正義の構想・主義は、極端さの程度に多少の差はあれ、上で述べた例ほどの極論に与するものはない。極論は、哲学的には尖っていて興味深いのだが、バランスを取った玉虫色の解決が、実践的には優等生的で現実的である。
義務論と帰結論の間で、具体的にどのあたりに落としどころがあるのか、たとえば空港建設予定地の所有者の権利をどこまで尊重するべきかは、個別のケースによりけりであり、理論的に答えの出る問題ではない。ただ、義務にせよ帰結にせよ極端に走る者は、藤木源之助のように、ある意味で大変に美しいのだが、そこに無傷でついていける個人も社会もないということだけは、はっきりと言えるだろう。
***
さて、次回は具体的な正義の構想の一番打者として、先にも挙げた功利主義に登場を願おう。
2会津藩士の什の教えより。
3「風が吹けば桶屋が儲かる」の喩えのように、力学的な因果関係において、小さな原因が、遠くの幅広い事柄に大きな影響を与えること。
4ここでの全体主義者とは、世界「全体」の人々の幸福の総量という観点から帰結を理解している者という意味である。
5これも、実際にはほとんどありえないが、理屈上は、生命の停止を絶対の義務とする義務論もありうる。
6この意味で、義務論者は権利論者であることが多い。義務と権利は、表裏一体の関係にあるから、当然のこととも言えよう。