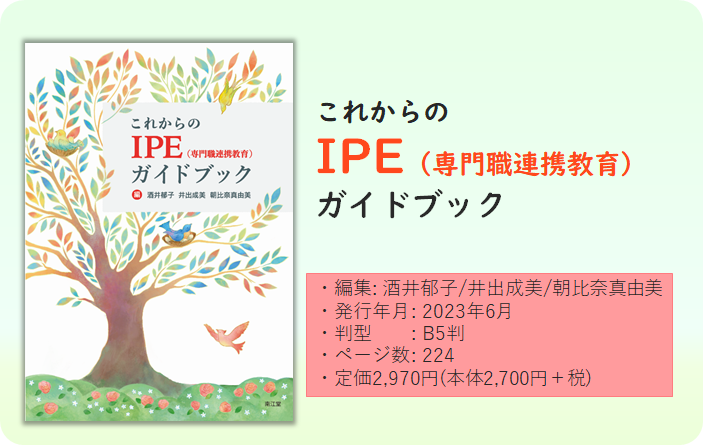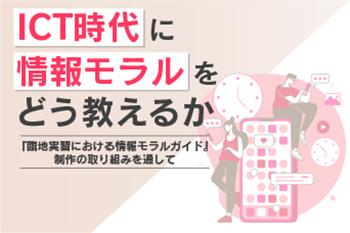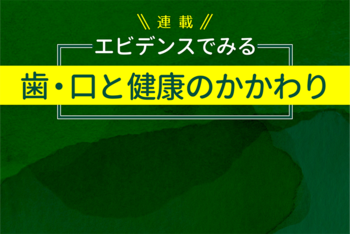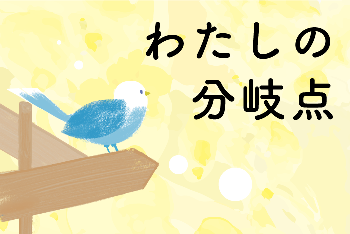クリスマスですね。日照時間が短い今日この頃ですが、今の季節が一番太陽のありがたみを感じます。みなさまに太陽があたりますように。韓流ドラマ『今日もあなたに太陽を~精神科ナースのdiary~』を完走しまして、なんとリアルにリスペクトとともに看護師を描いてくれたことよ、と感動しているカピバラです。というわけで今回はみなさまにとってリアルな話題、せん妄と看護師の傷、そしてそこからの回復の話をお伝えしたいと思います。
せん妄になった患者さんをめぐる昔話
カピバラが今の大学に着任したのは2000年でした。そして相次ぐ医療事故に対して厚生労働省から患者の安全を守るための医療関係者の共同行動が発表されたのが2001年です1)。ここを起点として患者安全を守るための施策が次々と出されていきました。その当時、どこの急性期病院もそうだったと思いますけど、みなさん、せん妄ケアに困難を感じていました。とくに夜の病棟は、人員も少なくなりますから一瞬も気が抜けない落ち着かない状況。今のように7対1の看護体制でもありませんでしたし、専門職連携実践は夜明け前でチームとして多職種が連動してケアに当たるということも難しい時代でした。せん妄予防に関する知見もまだ乏しく、せん妄を発症した患者さんへのケアに決め手を欠いていました。こんな状況のなか、医療安全への意識の高まりから、患者さんの転倒やチューブ抜去が生じてしまった時、組織から「事情聴取」される風潮が強まっていました。
「(トイレの便座を指さして)あそこに白いサルがいる!!」「(娘さんのいる)○○に電話してください。(看護師の腕をあたかも受話器のようにとって耳に当てて)もしもし、今ね、ワンちゃんが襲われているの、助けて!」「(病棟から出ようとしつつ)葬式に行くんだ、なぜ止めるんだ?」など、せん妄を発症した患者さんとのやり取りに疲れ果て、転倒などのインシデントが生じたあとのあれやこれやも思い浮かび、「安全」を守れないからと、「ごめんね」と言いながら患者の体を縛る看護師たち。病院に出入りしていると、そんなことを見聞きしました。
いろんな急性期病院や回復期リハビリテーション病棟でフィールドワークをしていると、「転倒転落は看護の責任」「せん妄になるのはケアが悪いから」という他の医療専門職からの意見も耳に入ってきました。今思えば、かなり知識不足で偏った同僚の認識により、現場の看護師が追い詰められていたのは事実です。なんとかならないかと思い、病院の看護師有志たちでせん妄ケア研究会を立ち上げたのが2004年のことでした。
せん妄をめぐる医師との思い出話
先日、何かの会合で再開した際に、その当時のことを思い出話として語った医師がいました。その医師は「病院の執行部にいたころ、カピバラさんが僕のところにやってきて、外科系の病棟で何が起きているのか把握しているのかと、えらい剣幕で詰め寄ったことがあったよね(笑)」とおっしゃいました。不肖カピバラ、どなたに対してもえらい剣幕で詰め寄ったりすることは基本しませんし、わざわざ言いに行ったりもしません。たぶん廊下の立ち話とかそんな感じで話したんだと思うのですが、彼の中ではそのような心象風景だったのね。
彼はこんなふうに話しました。「せん妄は、患者の命も安全も脅かす、スタッフも傷つく、発生率や要因を病院としてどう考えているのかとカピバラさんに言われた。」(カピバラの心の声:それは確かにそう言った。どう考えているんですか? と質問したことを詰め寄られたと解釈したのね。確認しただけなんだけどな。)「そう言われてその日のうちに病棟に行ってみたら、確かに自分が思っていた以上に大変なことになっていた。これはまずいと思っていろいろと手を打ったんだよ。あの時、伝えてもらって本当に良かった。」
思えばここが、組織としてせん妄を予防する体制が必要だと病院執行部が気づいた小さなきっかけであったように思います。
今年の6月の第33回日本老年学会総会(第28回日本老年看護学会学術集会との同時開催)の合同シンポジウム「せん妄ケアのシステム化と専門職連携」で、彼をはじめとする病院執行部と千葉大医学部附属病院の包括的せん妄ケアチームの20年にわたる活動をまとめ、今後の展望をケアチームのコアリーダー(看護管理者)が紹介してくれました。その時、「せん妄ケアのかなめは看護師である」と、20年前によく聞いた看護師にせん妄ケアは任せた、みたいな議論が始まり、そのコアリーダーは「せん妄ケアはそれぞれに専門職がその専門性を発揮して、役割を重複させつつみんなでかかわることが必須です」と述べ、それにはカピバラ心の中で拍手でござったよ。よく言った! とあとで本人に賞賛を伝えたら、「あそこで引き下がってはわたしたちのJourneyの意味がなくなるんで」、とあっさりと答えてくれたのもうれしかった。ここまで来るのに20年の試行錯誤があったわけです。
「何かあったらどうすんだ症候群」
このエッセイで何度か触れている、医療者のオーバースペックな対応をカピバラは「何かあったらどうすんだ症候群」と名付けております。実際に何かよろしくないことがとある患者に起きてしまい、その場に居合わせたもしくはその情報を耳にした医療専門職が、ほかの患者に対してこのよろしくない状況が起きないように、あれをして、これをして、でも不安だから念のためにこれもやっておこう、と念には念を入れていく症状です。とくに医師と看護師で罹患率が高い。安全に医療を提供するために、予防策を講じることは良いことなんですけど、予防策はあくまでも患者安全の手段であり、予防策を固守することが目的ではないはず、、なのですが、目的と手段が入れ替わってしまうために、何を何のために予防すんだっけ? という判断が止まってしまうことが起きることも多いです。
とくに、急性期病院の病棟の看護はチームで展開するので、同調圧力がかかってしまう。「この患者は今は落ち着いているので、行動制限をしなくてもよいと思うが、チームに相談してからじゃないと、個人の判断で身体拘束を解いてはいけない」という思考回路にはまり、身体拘束がいつまでも外せない状況になることも多々あります。そしてシフトがあるので、次の勤務帯の看護チームへの忖度、もとい配慮も働いてしまう。「夜勤の看護師に迷惑をかけないように」「せん妄になりそうだから、身体拘束をして行動制限をばっちりして」申し送ったりするなどのことも生じたりします。患者さんへのケアのはずが、自分たち看護職の安心のための行動制限となっていく。これはそうなってしまう理由があるんだと思います。
傷ついた看護師が身体拘束をしてさらに傷つく
「何かあったらどうすんだ症候群」の症状の一つとして、起きてしまった「何か良くない状況」について、看護師が自分のせいだと自身を責めてしまうというのがあります。このことが背景にあるため、別の患者に対しても、自分のケアのせいで「良くない状況」が生じないように、せめて自分が担当する今夜一晩、転倒やチューブ抜去が起きないようにと考えるようになり、せん妄になりそうな怪しい気配がする患者に「ごめんね」と言いながら身体拘束実施の選択に至ることも多かったのかなと思います。
この時、看護師は、自分のせいで患者を危険な目に合わせた記憶がよみがえり(もしくは危険な目に合わせる自分を想像して)、それで傷つき、今看護しようとしているこの患者を、実は縛りたくないのに縛らなければならないと判断する自分にも傷つくという、二重の傷つきがあるのかもしれません。
もちろん患者にとって身体拘束は苦痛であり、身体的精神的な弊害が多く、時には致命的な状況になるリスクが高いことは研究知見として蓄積されています。しかし「何かあったらどうすんだ症候群」のチームに、これらの研究知見が届くことは稀です。何かあったらまずいので、第一選択が身体拘束であるからです。これでいいのかな? と疑うことをしないので、調べるという行動がキックオフされないわけですね。
ためらいなくケアするには
経験の浅い看護師ほど、看護チームの文脈を読み、前後左右を見て、いろいろと観察しつつ、話を聞いてくれそうな先輩看護師に遠慮がちに確認しながら(時には確認もできず、チームから求められる看護はこうなんだろうと忖度、じゃなくて配慮して)看護しようとします。この時この看護師は患者のことより、チームリーダーとかコワイ先輩のほうを気にしつつ、ためらいつつ看護しています。
一方、まったくためらいなく、すっと患者に必要な看護をする人がたくさんいるチームもあります。余計なことは考えないで患者さんに全集中していて、患者の状況とタイミングだけがケア提供の決定要因であるチーム。そのようなチームの看護師はケアリング状態にすっと入ることができる。せん妄を予防しよう、発症しつつあるから身体の状況を整えるためにこうしよう、この薬は変更してもらおう、身体拘束は余計に患者を混乱させるからなるべくしない方向でみんなで工夫しよう、理学療法士や作業療法士にも病棟に来てもらって患者さんをなるべく一人にしないように時間の構造化をしよう、などど、ケアの方向性がどんどんクリアになっていきます。このようなためらいなくケアを推進するチームにとって、身体拘束は第一選択ではなく、最後の手段となります。
このようなチームとなるには、患者さんに向き合うことを推奨、賞賛され、失敗したとしても、そのチャレンジを肯定され、その失敗から学んだことをチーム全体で共有できたことに感謝するような信頼の醸成が必要です。それにはたぶん、とある専門職だけが「責任をとる」という考え方と真逆の発想が必要ですね。それぞれ責任を共有し、目的・目標を共有し、結果をチームで引き受けるという見えないグランドルールがあることが条件です。看護師はこのようなチームで活動すると、心理的に安全を確保されるため、患者さんのケアにためらいなく注力することができます。ためらいなく患者さんへのケアを行うことにより、患者さんはより良い状態となっていき、せん妄や転倒やチューブ抜去のリスクも身体の回復につれて減少しますよね。そして、患者が良くなっていくことで看護師の傷も癒えていきます。患者と看護師の回復には相互作用があるんですよね。
今日も、いつも、あなたに太陽を
患者さんを照らす看護師のみなさんこそ、太陽の光で光合成しなくては。組織の中で自分なりに患者さんに向き合って仕事をするためには、まず自分を大切にする看護師でいたほうが良いかもです。看護師こそ自分の心の黄色信号を受け取れるようにしておきましょう。患者の黄色信号には敏感なのに、自分の黄色信号は無視していては、いつか無理が来てしまいますよね。今日もあなたに太陽を。太陽とは、自分を大切にするってことなのかなと思います。
1) 厚生労働省:患者の安全を守るための医療関係者の共同行動〔https://www.mhlw.go.jp/topics/2001/0110/tp1030-1b.html〕,(最終確認:2023年12月21日)
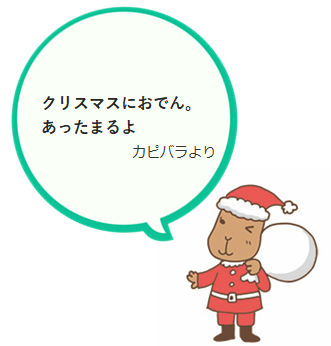
\引き続きカピバラからのPRです/
●千葉大学大学院看護学研究科では、博士前期課程・看護実践学コース・特定看護学プログラムの入学試験を令和6年2月7日に実施します。出願受付期間は令和6年1月5~10日です。
➡詳しくはこちら(https://www.n.chiba-u.jp/admission/graduate/outline.html)から
●特定行為研修を含むカリキュラムを有している特定看護学プログラムは地域包括ケアシステムの推進に向けたクリニカルリーダーを育成しています。ご興味のある方は、下のURLからぜひ動画をご覧ください。
・YouTubeのサイト➡ https://youtu.be/2MJbAxUsJB0?si=v7EuyHmKRBZxFclG
・千葉大学看護学研究科ホームページからもご覧いただけます➡ https://www.n.chiba-u.jp/outline/movie.html