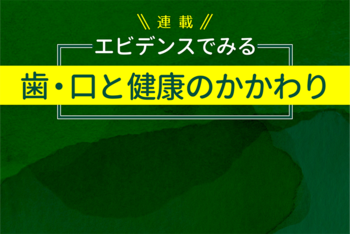発災時の鮮明な記憶
2011年3月11日、山形県内の大学で教員をしていた私は、卒業研究の調査協力への御礼のため、学生と県内の病院を訪れていました。挨拶を終え、一息ついていたその時、ギシギシという音とともに大きな揺れに襲われました。患者さんやスタッフの叫び声が響き渡る中、私はとっさに「閉じ込められてはいけない」と思い、外来患者さんが集まっていた部屋の扉を必死に開けていました。
揺れが収まった後、非常灯に照らされた院内に一瞬の静けさが訪れ、すぐに混乱が押し寄せました。パニックで過換気になる人、廊下の隅にうずくまる人、呆然と立ち尽くす人――今でも鮮明に思い出されます。
私の居住地域は甚大な被害を受けることはありませんでしたが、度重なる余震、断たれたライフライン、空になったコンビニエンスストアの棚、長蛇のガソリンスタンドの列など、不安は募るばかりでした。灰色の3月の空からは雪が降り、暗闇が迫る中、懐中電灯やラジオを探し周り、家族と寒さをしのぎ、おびえる愛犬を抱きながら、日常が一瞬で失われたことを実感しました。
被災地で目の当たりにした「生」と「死」
震災から数日後、単独で被災地支援に入るという保健師に同行しました。雪が降りしきる中、タクシーで宮城県仙台市へと向かう道中、倒壊した建物を目にして背筋が凍るのを感じていました。
仙台市の南東部に位置する人口約13万人の若林区は被害が大きく、多くの住民が亡くなり(死者339名:2025年3月公表1))、2万人を超える住民が、58ヵ所の避難所に避難している状況でした2)。
私は、同行した保健師とともに、避難所の一つとなっている若林区の小学校での支援活動に従事することとなりました。フリーでの支援活動だったため支援車には乗ることができず、片道30分ほどの道を歩いて通いました。途中、津波に流され床下がむき出しになった住宅や、店内が泥でぐしゃぐしゃになったレストラン、いつ開店するかもわからないスーパーに並ぶ人々の列を目にするたびに、奪われた暮らしとかろうじて残された暮らしを分ける「境界線」があることを強く感じていました。
数日後、若林区の中でも甚大な津波被害を受けた荒浜地区で支援活動をする機会がありました。沿岸部に近づくにつれ、そこに広がっていたのは現実とは思えない光景でした。津波に飲み込まれて消えた街並み、折り重なる車の山、フロントガラスに赤く記された「×」印*――胸の奥に重い憤りを覚えると同時に、「今、津波が来たらどうしよう」「自分は生きて帰れるのか」という恐怖に襲われました。私は初めて自分が生きているということの尊さを感じるとともに、恐怖という感情に戸惑っているのだと実感しました。
*当時、車内に遺体があることを記すサインとして使用された
約1週間の避難所での支援活動を終え、最後に訪れた遺体安置所――静寂と異臭の漂う中、整然と並ぶ棺には、特徴や服装が記された紙が無造作に貼られていました。そこには亡くなるまで確かに誰かを思い続けていた「人」が存在していました。
そしてそこで目にした、一つ一つ棺を確認していく、大切な人を探しにきた人々の背中。死とは何か、生とは何か、そして死に直面している人々に対して看護師である自分が向き合うべき本質とは何か、その問いを突き付けられているように感じました。
学生に何を伝えたいか――支援活動を経験した「私」の使命
私は看護基礎教育を終えた後、大学病院で内科・外科・救急などに従事し、その後は訪問看護師として在宅で療養する患者さんやご家族に関わってきました。この間、医療資源が整った環境下での医療や看護の提供にとどまり、自ら災害支援に携わることはありませんでした。
しかし、東日本大震災の発生によって多くの人々が犠牲となり、その犠牲者の大半が津波による溺死で、医療で救命できた命はわずかだったという事実が、「災害によって日常は突然失われること」、そして「人は死に向かう存在であること」を私の心に深く刻みました。この経験後、平時から人々が安心して暮らせる社会を守るために、また災害という有事の際に、「私」には、そして「看護師である私」には、「教員である私」には何ができるかどうかを問い続けるようになったと感じています。
現在、私は基礎看護学の科目のほか、災害看護とエンドオブライフケアの科目を教授しています。これらを教授する際、学生たちには災害などによって社会そのものが揺らぐ状況になっても、地域で暮らす人々の生活と命を支える視点を持ち、看護師として何ができるか、ということを思い続けて欲しいという願いを込めています。授業や演習では、「患者さんの生活背景を想像すること」「常に何を優先すべきかを考えること」を重視してもらい、演習などで用いる症例をじっくりと考え、その考えを共有し、行動につなげる機会を設けるようにしています。
.png)
ひとたび災害が発生すれば、突然命を奪われる人がいるだけでなく、日常を失い、病と共に生きることが困難になり、避難生活の中で命を落とす人もいます。どのような状況にあっても、人々が「幸せ」を実感できる看護を届けられる看護師を育てること――それが東日本大震災で支援活動を経験した今の私が果たすべき使命と考えています。
1)仙台市ホームページ:東日本大震災における本市の被害状況等,〔https://www.city.sendai.jp/okyutaisaku/shise/daishinsai/higai.html〕(最終確認:2025年9月25日)
2)佐藤健,恋水康俊,昆野辰樹:東日本大震災における仙台市内の避難者発生の地域特性.日本地震工学会論文集 12(4);278-287,2012