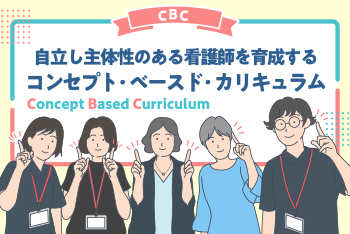教員としての心構えをもつ
「あなた、教員は向いていないんじゃない?」
これは看護師を辞めて教員になると上司に伝えたときに返ってきた言葉だ。少々ムッとしたが、「そうかもしれません」と返答してしまうくらい自分が教員になるイメージは沸いていなかった。なぜ教員に転職したのか? 大学時代にお世話になった教授に教員にならないかと誘われたとき、入職時に抱いていた看護師としての目標を達成し、次の目標もなく漫然と過ごしていた私は、その日々を打破するきっかけになるかもしれないと期待を抱いたのだ。流れに身をまかせただけで、そこには教員としての目標がないばかりか、仕事内容の理解すらなかった。それゆえに、教員として働き始めた当初は、学生とどう接したらよいのか、何を伝えればいいのかわからず、自分の存在意義がないように感じた。
教員としてのあり方のヒントを得たのは、同僚であるA先生の振る舞いを見たときだった。A先生は学生と何やら真剣に話をしていた。そのとき、上司がA先生に話しかけたが、A先生は学生との話を続け、数回話しかけられた結果、「今大事な話をしているんです」と上司との会話を断っていた。学生との話を優先したことに驚いた私は、A先生に理由を聞いた。すると、「学生から将来進む道について相談されて、あのときは学生の話より大事なものはなかった」と答えた。それを聞いて、教員となった自分は学生に真剣に向き合い、成長を一番に考えて行動しなければならない立場なのだと自覚したのを記憶している。
主導するのではなく、学生と一緒に考えることを大切に
1年のうち半分近くは実習指導に携わった。学生が成長できるように導かないといけないと思っていた私は、自分が考えるのと同じように学生も考えられることが指導だと思っていた。しかし、学生の感性や看護実践に心を揺さぶられる体験を幾度とする過程で、指導方法は変化していった。
学生にはっとさせられた実習
3年次の実習で、ある学生が終末期にあるがん患者を受け持った。患者はベッド上で過ごす時間が長かったが、化学療法で頭髪が抜けたためウィッグを装着するなど、常に身なりを整えていた。呼吸困難感を緩和するためモルヒネが持続投与され意識レベルが低下したとき、学生はウィッグを外された患者をみて、「いつも身なりに気を使っていたのにウィッグをしていなくてかわいそう。ウィッグをつけてあげたい」と言った。その気づきに私はハッとされられた。呼吸状態などの身体面に気をとられていた私とは違い、学生は患者が大事にしていた思いに寄り添っていた。尊厳を守るとはこういうことだと学生に教えられた感覚だった。
手術室実習において患児を受け持った学生の看護も印象深く覚えている。学生は、翌日に手術を控えた幼児期の患児に、自作の絵本を用いてプレパレーションを行った。不安な表情を浮かべ今にも泣きそうな顔で手術室に来た患児に対し、多くの医療者がいる中で学生が中心となって絵本の内容をなぞるように一生懸命声をかけ続けた結果、患児は一度も泣かずにスムーズに麻酔導入に至った。手術室での実習は学生が直接的に看護を提供することは難しく、見学が主になりがちな中で、学生が中心となって効果的な看護が行えたことは驚きであった。
学生の感性を尊重して伸ばす
患者と真摯に向き合っている学生は、たとえ看護過程の記録が書けなくても、どのような看護が必要かわからないと言っても、患者はどうなりたいと思っているのか、何がつらいと思っているのか問うと、答えることができる。教員だからといって自分の考える優先順位や看護に誘導するのではなく、学生の考えをしっかり聞き、その考えを尊重したかかわりをするほうが、学生の自分で考える力をより伸ばせると感じた。
学生のとらえた患者像や気になる点を掘り下げるようにして、そう考えた根拠となる情報を振り返り、原因を推測し、目標に向かってどう援助するかを一緒に考えることを大事にするようになっていった。このように看護学実習での学生とのかかわりの中で私の教員としての軸が形作られていった。また、学生と意見交換をしたり、実践を見守ったりすることで、新しい視点を獲得し、自分自身の看護観を醸成することや、看護師としてのやりがいを再認識する機会にもなった。
学びのスイッチは学生時代に入るとは限らない
一方で、自分で考えられない学生や、知識も意欲も少なく医療職者として働いていけるか心配になる学生もいた。しかし、心配なまま卒業した学生の中には、何年も臨床で頑張っていたり、病棟をリードする看護師になっている卒業生もいた。卒業後何年かたってから、「実習のとき、夜遅くまで一緒に間質性肺炎の勉強してくれましたよね。あの頃は全然勉強していませんでしたが、看護師になってめちゃくちゃ勉強しました」「卒業するときに、一人前になるのに人より時間がかかるかもしれないけど、絶対いい看護師になれるから頑張るんだよ、と言われたことを信じてやっています」と話してくれた。大学時代は人生の一部でしかなく、いつスイッチが入るか、いつ彼らが花開くかはわからない。長い目で学生を見ることも大切で、教員が先にあきらめたり、決めつけたりしてはいけないと痛感した。そしてそれは、自分自身に対しても同じなのだろう、と。
.png)
もう一度、看護師として
教員として10年あまりを経て、今看護師としてホスピスで働いている。職業人生も折り返しに差しかかり、何をしたいか、どう終わりたいか考えたとき、看護師を志したときからいつかは…と思っていた終末期看護に挑戦し、自分の考える看護実践をしたいと思ったのだ。教員として働く中で、看護の奥深さや自分の可能性の広がりに気づいた経験がこの選択につながっているのは確かだ。
教員に向いていないと言った上司に今ならこう伝えたい。
「教員に向いているかわかりませんが、教員になってあの頃より看護が好きになりました。」




」サムネイル2(画像小)_1642033387967.png)