ギリシア神話に出てくるセイレーンという怪物をご存知でしょうか。上半身は女性でありながら下半身は鳥という、なんとも奇怪な姿で、航海中の船に近づいては美しい声で歌い、その歌声を船乗りたちが聞いてしまったら一巻の終わり。セイレーンの声に惑わされて大海原を迷子のようにさまよい、ついにはタイタニック号よろしく難破して海の藻屑となってしまうのだそうな。それでは、セイレーンの声に惑わされないためには一体どうしたらよいかというと、答えはひとつしかありません。そう、聞かないように耳をふさぐしかないのです1)。そして実はこの話、遠く離れた日本のおとむらいとも意外なつながりが……。
ミミフサギ
前回のコラムでとりあげたタマヨビ(魂呼び)は、死者の魂を呼び戻そうとする習俗の話でした。ここで、逆のパターンを考えてみましょう。つまり、もしも死者の魂が生者の声を聞くことができるならば、セイレーンのようにあの世へ道連れにしようと自らの声を生者に聞かせることもできそうな気がしませんか。もちろん生者の側にとっては、いくら親しい間柄であったとしても、あの世へ連れ去られてはたまったものではありません。というわけで、「死者の魂が自分を呼んでも聞こえないように耳をふさぐ」という習俗もあるのです。
それが、読んで字のごとくミミフサギ(耳ふさぎ)もしくはミミフタギと呼ばれるもので、とりわけ同い年の知人や親戚が亡くなったときに行うことが通例でした2)。しかし、そのやりかたは地域によってさまざま。ここで民俗学の泰斗(たいと)として知られる柳田國男の『葬送習俗語彙』という文献を紐解いて、どのようにミミフサギを行っていたのかという事例をいくつか参照してみたいと思います3)。
- 白い餅を買ってきて耳に当てた後、その餅を屋根の上に投げる【三重・伊勢】
- 米の粉を練って耳の形にしたものをつくり、耳に当てて「ねぢかちねぢかち」と唱える【愛知・北設楽】
- 自分の家から屋根が見える家で死者が出たときだけ餅を耳に当てる【愛知・南設楽】
- 小型の丸餅をつくり、耳に当てた後は川に流す【茨城・多賀】
- 握り飯をつくり、耳に当てた後は三叉路(つまりY字路)に行って、そこで握り飯を捨ててくる【東京・青梅】
- 饅頭を2つ持って橋に行き、その饅頭を耳に当てた後は橋の上において、そのまま後ろを振り返らずに帰る【栃木・足利】
- 春ならば浅葱(アサツキ)を、それ以外の季節は草履の切れ端を耳に当てて、「いいことをきけ、わるいことをきくな」と唱える【新潟・東蒲原】
上に挙げた事例はごく一部なのですが、それでもミミフサギという習俗が多様であることがお分かりいただけるのでは。ただし共通性もあって、全国的にみるとミミフサギは餅をはじめとする「米でつくった食べもの」で耳をふさぐというやりかたが最も多かったと考えられています。でも、なぜ米や餅なのでしょうか。
耳は魂の通路
この理由として、各地のおとむらい文化を長年にわたり研究してきた国立歴史民俗博物館の関沢まゆみ氏は「米の霊力で凶報が身体に入り込まないようにするという意味、つまり米によって生命力を強化して死者に引き込まれないようにするという意味」4)があったのだろうと述べています。考えてみれば、日本人にとって米は単に主食というだけでなく、ある種の神聖さを宿した象徴的な食物として位置づけられてきました。茶碗にご飯粒を残して「一粒の米にも八百万(やおよろず)のカミサマがいるのだから、モッタイナイことをしてはいけません」などと叱られた経験がある方々もいらっしゃるのではないでしょうか。このようなカミサマ的な強い力が米に秘められているのならば、たしかに死者の魂が呼ぶ声も跳ね返すことができそうな気がしますよね。
そして関沢氏はもうひとつ、「年取りを疑似的に行い死者と同齢でなくなったことを表そうとしている」5)という理由も挙げています。ここで、少しばかり補足を。餅の出番が一番多い季節はいつかというと、今も昔もお正月。そして、かつての年齢の計算法は現在のように誕生日で起算する「満年齢」ではなく、元日で年をひとつ重ねるという「数え年」が主流でした。ここでもうピンときた読者もいらっしゃるでしょう。先ほど、ミミフサギは同い年の人間が亡くなったときに行うことが通例と述べました。つまり、死者の魂が同い年の人間をあの世に連れて行こうとするのならば、本当にお正月であろうがなかろうが、餅をつくって「今はお正月なので年齢をひとつ重ねました!なので、あなたと同い年じゃないですよ」ということにしてしまい、お引き取り願おうというわけです。
そのため、ミミフサギの習俗はトシタガエ(年違え)やトシマシ(年増し)などの異名で呼ばれることも多く、なんと室町時代の文書にはすでにこのトシタガエに関する記述が登場しています6)。しかし、このように古くから行われてきたミミフサギ=トシタガエの光景も、前回のタマヨビと同様に現在では見かけることがめっきり少なくなりました。古来、日本では「耳を霊魂の通路として意識する感覚があったのではないか」7)という指摘もありますが、もしもそうだとすると現代の私たちは魂と触れ合い、その声を聞くという感覚8)や想像力を失いつつあるのかもしれませんね。
2)なぜ同い年の人間が亡くなった場合に行われるのかという理由は諸説あります。いわゆる「おまじない」は概して「似通った属性を持つものどうしは、お互いに影響し合う」という人間の思考に基づく場合が多く、このタイプの習俗を人類学ではしばしば類感呪術と呼ぶのですが、ミミフサギもそれに位置づけられるかもしれません。
3)柳田國男:葬送習俗語彙,民間伝承の会,pp.36-41,1937
4)関沢まゆみ:耳塞ぎ(みみふさぎ).民俗小辞典 死と葬送,新谷尚紀,関沢まゆみ(編),pp.57-58,吉川弘文館,2005
5)前掲4)
6)室町時代の皇族である伏見宮貞成親王(1372-1456)が当時の文化や世相について記した『看聞日記』(かんもんにっき)という日記が初出と考えられています。
7)小池純一:見る・聞く・嗅ぐ.民俗学事典,民俗学事典編集委員会(編),p.33,丸善出版,2014
8)余談どころか、どちらかというと前回のタマヨビに関する話にはなってしまうものの、臨終の現場に立ち会うことの多い看護師の方々からは「意識が混濁して人事不省(じんじふせい)の状況にある患者さんでも、実は周囲で話している声や、呼び掛けている声は聞こえていることが多いんです。だから意識レベルが低下していても、患者さんのまわりで不謹慎な話は本当にしちゃいけないんですよね」という話をよく聞きます。一説には聴覚は死の間際まで残る「最後の感覚」とも言われていますが、これに関しては大阪大学大学院教授の髙島庄太夫氏による「最後まで残る感覚、聴覚について」というコラムが参考になるかもしれません(https://www.med.osaka-u.ac.jp/introduction/relay/vol44)(最終確認:2024年11月11日)。

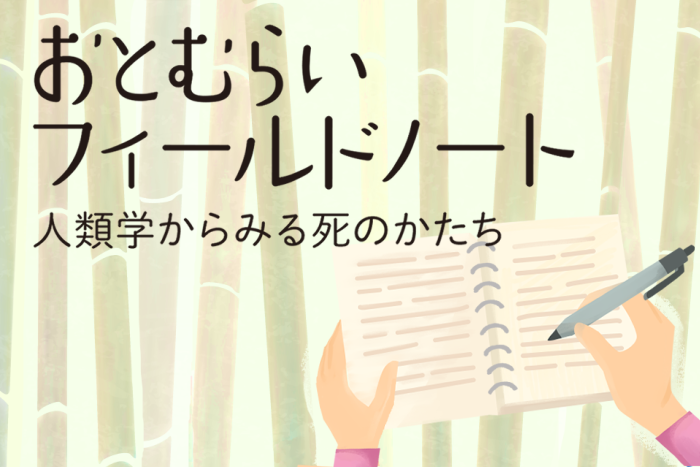




_1695266438714.png)