今まさに病室のベッドで息を引き取ったばかりのおばあちゃんを家族が取り囲み、しくしくと泣きながら皆で「おばあちゃ~ん」「戻ってきて~」と声をかけると、おばあちゃんが「まったくウルサイねェ、いったい何事だい」なんて言いながら起き上がって一同がビックリ仰天! そんなベタベタなコントをご存知のあなたは、きっとワタクシと同じく昭和生まれですよね?
まあ昭和生まれか平成生まれか、流石にいらっしゃらないと思いますが令和生まれかはさておき、実際の看取りの場面でそんなことが起きたらビックリ仰天どころでは済まない気もする一方、最期を迎えつつある人に向けて「お願いだから逝かないで」という思いで名前を呼ぶというのも自然なこと。NurSHAREをご覧の看護教育者や医療従事者の皆さんのなかには、そんな光景を数多く経験された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
屋根の上で、井戸の底へ
死にゆく人の名前を呼ぶ。上に述べたようにそれは遺された側の人びとにとっては自然な感情のあらわれでもありますが、皆が皆そのようにするというわけでもありませんし、そうしなかったからといっても別に薄情なわけでもありません。悲しさと切なさを堪えて最期を看取るという方も多いはずですから。ただし、臨終に際して名前を呼ぶという行為そのものは、以下に民俗学者の井之口章次氏が語っているように、かつては全国的に行われていた習俗でもありました。
人が死にそうになったとき、大声でその人の名を呼び、よみがえらせようとする「まじない」がある。呼べば戻ってくるかも知れない、と考えていたのである。そんな馬鹿なことが、と考えるだろう。呼んだくらいで生きかえるなら、この世の中に、死ぬ人などあろうはずがない。ところが、明治時代の中ごろまで、全国で知らない村がないほどに、魂呼びは行われていた。分布図を作っても意味がないくらいに、広く行きわたっていたのである。1)
このタマヨビ(魂呼び)は、それぞれの地域ごとにタマヨバイ・ヨビモドシ・ヨボリカエシ・ヨビイケルなどの別称が数多くあり、やりかたも地域によって「危篤に陥ったときに行う」「呼吸が止んだ直後に行う」「身内が行う」「身内でない人間に頼む」など千差万別なのですが、ある程度共通している要素も見受けられます。それは何かと言うと、タマヨビを行う「場所」。冒頭のコントのように、死にゆく人の枕元で囁くように語りかけるというケースもそれなりにはあったでしょうが、最も多いのは屋根の上で、または井戸の底に向けて、名前を大声で叫ぶというやりかたでした。そう言えば第3回でも魂の存在を人びとがどのように捉えてきたかについてあれこれ論じましたが、肉体から抜け出してフワフワと天空に舞い上がる魂を呼び戻すためにできるだけ高い所へ、さもなければ黄泉の国へと舞い降りていく魂を呼び戻すために地下の奥底に向けて……というイメージが、このタマヨビの習俗からは伝わってきますね。
瞬間なのか、プロセスなのか
平安時代に書かれた『小右記』2)という文書には、あの藤原道長が最愛の娘の死に際して陰陽師を招き、屋根の上で名前を呼ばせて何とか生き返らせようとしたという出来事が記されているほどですから、タマヨビがかなり古くから行われていたのは間違いないといって差し支えないでしょう。ただし、ここでちょっとばかり注意が必要です。というのは、今日では「ご臨終です」と告げるのは皆さんもご存知の通り医師による死亡判定を経た上で行われます。つまり変死や異状死でない限りは「最後の瞬間」を何時何分何秒に至るまで厳密に定めてから告げられるということになりますが、昔はそういうわけにはいきません。
また以前のコラムを紐解くと、第4回で書いたように「脳波計も心電計もない時代であれば、死の事実というものは体表から感じ取ることのできる徴候で視認するしかなかった」わけで、日本に限らず世界各地にある通夜の習俗も、単におとむらいの一部分を構成する行事というだけでなく「もしも生き返ってくれたらという強い思いと願いを抱いて、一晩かけて死者を見守りつつ過ごす重要な時間」でもありました。ですから、タマヨビという習俗も現代の私たちにとっては何だか非科学的だなあという思いも脳裏を過る一方、死んだとばかり思っていた人間がむっくりと起き上がって息を吹き返すという事態も昔は往々にして起きたであろうことを考えると、タマヨビは「そうすることになっている」という文化的な習俗としての側面を持つだけでなく、蘇生のための措置、もしくは息を吹き返すかどうかを確認するための措置でもあったという見方もできます。
そう言えば、10年ほど前にワタクシが四国地方で調査をしていたときに、仮に日中に亡くなったとしても遺体を納棺するのは絶対に夜の0時を過ぎた時点で、つまり日付が変わってから真夜中に行うというならわしを厳格に守っている地域がありました。もちろん医師による死亡判定は行われているのですが、日付が変わらない限りは「まだこの人は病人の体(たい)じゃけぇ、死んでないんじゃ」ということで、死者として扱ってはいけないというのです。いささか不謹慎なたとえにはなりますが、あたかもトコロテンがむにゅぅ……と押し出されるように肉体から徐々に魂が抜けだしていく(ので、何かの拍子で戻ってくることもある)という、タマヨビの習俗にも相通ずるイメージが未だ色濃く残っているのかもしれません。
タマヨビの習俗は、高度成長期の頃にはほとんど失われてしまったと言われていて、実をいうとワタクシ自身もこれまでの調査で出会ったことはありません。ただ、このように死ぬという出来事を「瞬間」ではなく「プロセス」として捉えるという感覚は、現代でもいくらかは残っているような気もしますし、特におとむらいをめぐる文化ではしばしば見かけることがあります。さて、看護の現場ではいかがでしょうか。
2)藤原実資(957-1046)という平安時代の貴族が書いた日記と伝えられています。

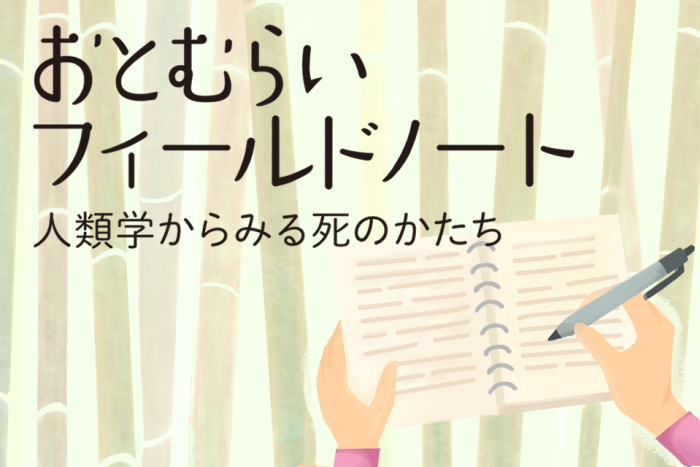

_1729484624408.png)
_1685342416837.png)

」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)