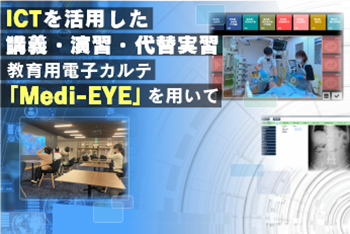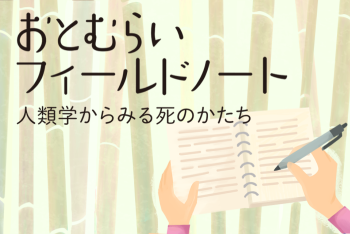看護学生として、看護師として経験を積む日々
とくに看護師になりたいと思って看護学校に入ったわけではない。3つ上の姉が医学部附属の医療技術短期大学生で、野球部のマネージャーをやりながら学生生活を送っている姿が楽しそう、ということの影響が大きかった。また、親元を離れたい一心でもあった。なので、看護学校に入った後に看護師の仕事というものを知り、毎日がつらかった記憶がある。半面、福岡の田舎から上京し、刺激的な生活の中でアルバイトに明け暮れたことも思い出す。だから当然、1年次は追試の女王でもあった。
そんな私は、3年次の実習で胃がんの壮年期の男性を受け持ち、「患者のことを考える」ということの大変さを知るとともに、しかしそれがとても意味のあるものだということを感じ始めた。この経験を糧に、私はその1年後、看護師として臨床の世界に飛び出した。
看護の楽しさを知った臨床時代
臨床での最初の1年半は、消化器外科の病棟で勤務した。オペ出しや術後管理はスピード感があり、観察、アセスメントや技術がどんどん身についた気がして楽しかった。その後、内科病棟に異動して糖尿病やアルコール依存症の患者さんと出会い、じっくり患者とかかわった。今となって考えるとその人を支える、その人の生活を支える援助を実践し日々学んでいたように思う。学生のころとはまた違って、患者と家族のためを思ってさまざまな関係者を巻き込んで計画を立て、即実践することができるようになっていった。それを認めてくれた病院の風土も私の看護への尊敬の念を強めたのかもしれない。勤めていた病院の理念でもあった「患者の立場になって考える」は、私の看護の礎になっているものでもある。
同じ看護観を持つ仲間を育てたいと考え、看護教員へ
臨床の現場に出て5、6年が経ったころ、主任になった私は、後輩や新人の指導、そして看護学生の実習指導を担当するようになった。
指導をする中で、学び手である後輩や学生と自分との間で、援助技術の方法や考え方が違っていることがあった。そんなときは、相違点について、意見交換をしながらよりよい方法を一緒に考えることになる。しかし、お互いに相入れない問題が起こることもあり、そのときは、私も相手もかなりエネルギーを使って議論した。
そんなやりとりをするようになったころから、「今の看護基礎教育がどのように実践されているのか、知ることが必要ではないか」と考えるようになった。また、リーダー業務の整理や業務改善などをする中で、一緒に仕事をする際に、同じような看護観をもった同僚と組むと、とても仕事がやりやすいとを感じることがあった。「ということは、基礎教育を担い自分と同じような看護観をもつ学生を育て、その学生たちが現場にはばたけば、もっと仕事がやりやすくなるのではないか」と思った私は、自己中心的な「仲間を増やしたい」という考えのもと、看護基礎教育への道に足を踏み入れることになった。
1年間の教員養成研修を終え、母校である都立の看護学校に教員として就職した。5年後には臨床に戻り、最初の希望であった現任教育に力を注ぐはずだったが、それがすでに今年(2024年)で25年目の勤続となった。
教員になって一番困ったのは、「人を評価する」ということである。恥ずかしながら私は、「評価」というものは、天が決めた基準に基づくと真剣に思っていた。そのため、自分が自分の考えで試験問題を作成したり、評価項目に沿って自分が採点をするということにかなりとまどった。「評価」というものを人間が作り人間がやっているということを改めて理解し、評価の難しさ、恐ろしさを知ることになった。教員であれば、指導する学生を評価することになる。それはすなわち、自分の指導が評価されるのだということを、改めて理解することになり、身の引き締まる思いがした。
学ぶことと教えること
ヒューマン・ケアリング理論を提唱したジーン・ワトソン博士の講演を聴きに行ったとき、心に残った印象的な言葉がある。「気遣いは、気遣っているということが重要なのではなく、“気遣われている”と感じてもらうことが重要だ」と。その際、「教えたよね」という言葉を、私はときどき使っていないだろうか、とふと思った。当時私は、1年生の学生に基礎看護学領域で基礎看護技術を教えていた。彼らが2、3年生になって実習指導をする中で、自分が講義した内容については、この言葉を使っていないか・・・。教えることも気遣いと同じで、「教えたよね」が重要なのではなく、教えられたことを学生が「ああ、学んだ。教わった」と思い出せる知識になるように、教員が指導をしなければならないのだと考えた。とはいえなかなか難しく、今でもつい「教えたよね」と言ってしまうが・・・。
自らがそのことに興味をもち、学びたいと思い、自ら「学び取った」知識や技術は強い。しかし、学生がそう思えるようになるには時間がかかるし、「ああ、そうか」と思えるまでにも時間がかかる。でも、そう思える瞬間はいつかやってくる。それが「学ぶ」ということであり、その瞬間に立ち会うことは「教える」喜びでもある。
.png)
各々の思いや価値観を大切にし、共有し、調整することが責務
教務総括となった今、学生との距離を感じることがある。担任をしていたころは、気になると学生に声をかけることができたし、なにより学生のことを知っていたと思う。理解までしていたかはわからないが知っていた。別の言い方をすれば、見ていたと思う。自慢すると、担任した学生の顔を見れば全員の氏名を空で言えた。今は、コロナ禍のマスクの影響か自身の加齢現象か、顔を覚えられないのは残念な事実である。
もちろん看護教員として、学生指導はメインの責務である。ただ、この立場になったことで、教員たちの思いや指導に対する考えを大事にし、価値観を共有し、よりよい指導ができるよう調整することも今の自分の責務となったと考えている。そのために、教員たちと議論するのはとても楽しい。先に、「自分と同じような看護観を持つ学生を育て、その学生たちが現場で活躍していけば、もっと仕事がやりやすくなるのではないか」と自己中心的なきっかけを述べた。でも実は、さまざまな人がいろいろな考えや価値観を持っていて、これらを徐々に合体させていき組み合わせていき、良いものの集合体にしていくことは魅力的なことなのだと気づいたのである。
そうは言っても、これだけ経験を積んでも私はまだひよっ子で、上司に感情あらわにたてつくことも少なくない。知識も技量もまだまだである。でも、これから先、看護教育界を背負ってくれる若い先生方が、看護教育に喜びを見出して楽しいと思ってくれるよう、力を尽くしたいと思う。



_1685342416837.png)