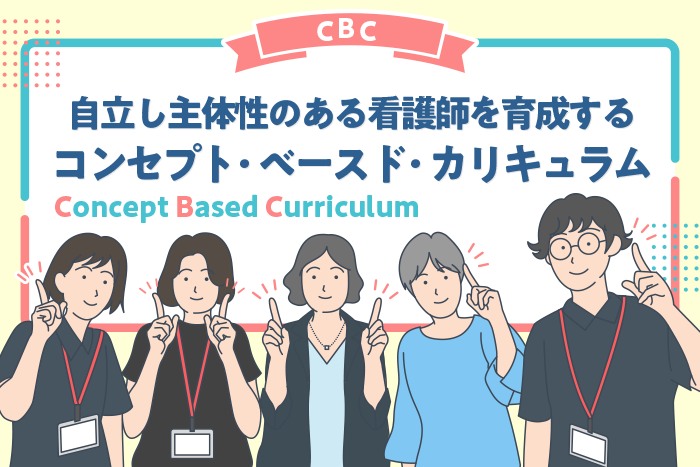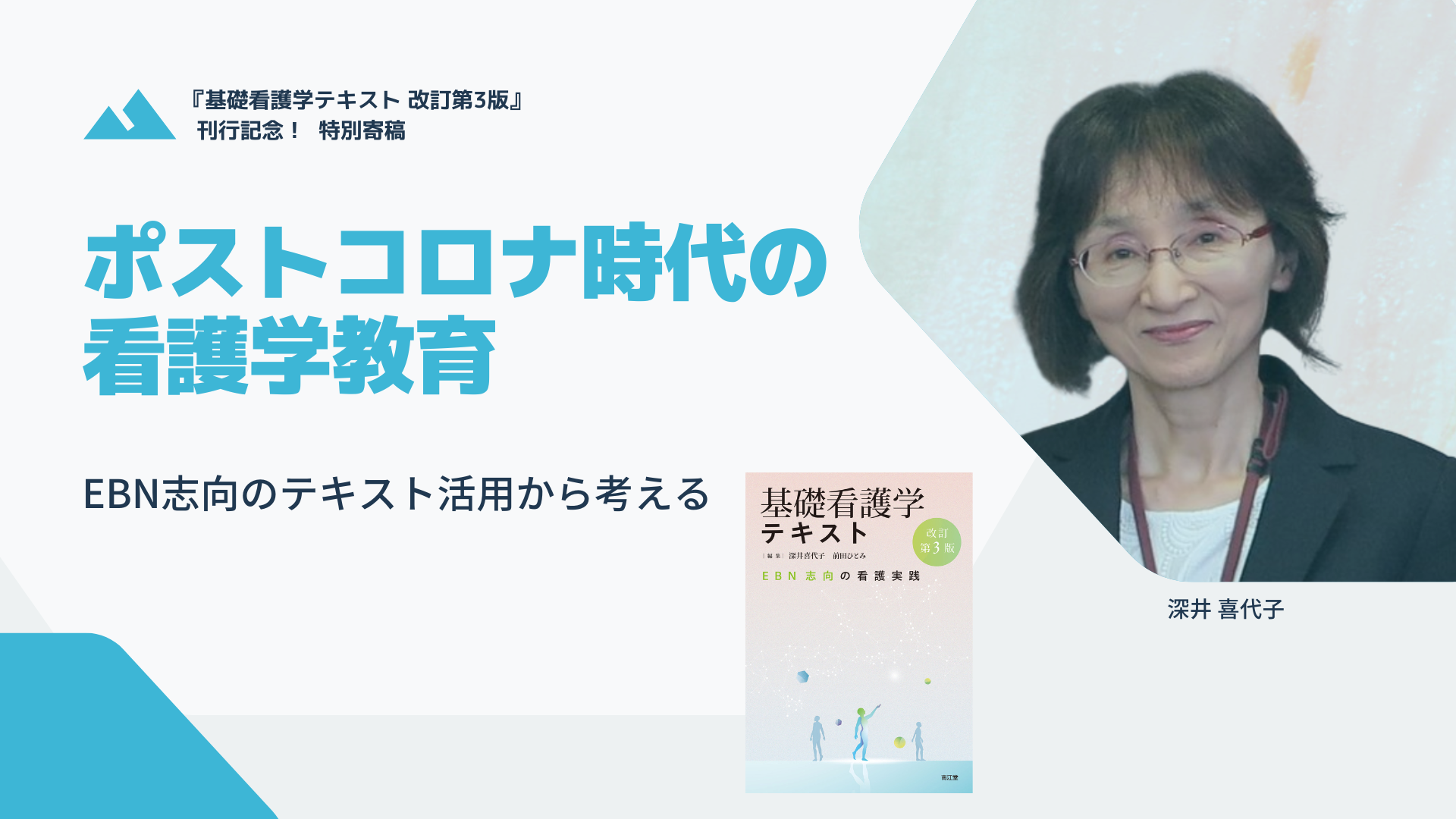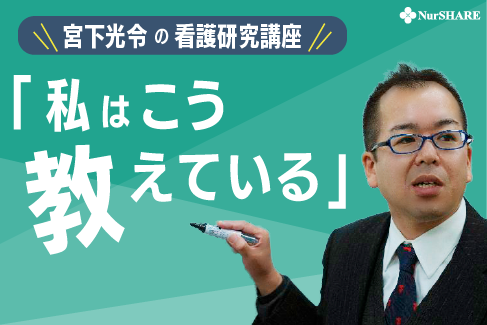CBCを支える理論
第2回ではコンセプト学習についてご説明しましたが、今回はコンセプト・ベースド・カリキュラム(CBC)を支えている理論と枠組みについて考えていきたいと思います。
知識とはなにか、学びとはなにか
その前に突然ですが、皆さんは「知識とはなにか」「学びとはなにか」について考えたことはあるでしょうか?知識とは外界から人に与えられるものでしょうか?それとも人の中で構成されていくものでしょうか?
「知識は人の存在と関わりなく、外界に存在するもの」と考えるのが客観主義(または行動主義)の考え方で、「人と独立して存在することはなく、周りの人やものとの相互作用の中で間主観的に構成されていく」と考えるのが構成主義の考え方です1)。客観主義的な考えは、従来の古典的な教育の基盤となる考え方で「知識がある教員から、知識のない学生へ授業で情報を伝達する」方法をとります。学習者は受け身で、知識を注ぎ込まれる教育の対象として捉えられ、教師が教育の中心人物となります。図1で表現されるように、学び手の空っぽの頭の容器に、教え手が知識を注入することで、知識が満たされるという考え方です。

一方、構成主義の考えでは、教育者は学習者の主体性を重んじます。学習者がすでにもっている既存の知識の上に新しい情報が加わり、学習者が自らそれらとの関連性を発見することで、その知識についての理解が深まり(概念の形成)、結果として異なる状況においてもその学びを転移させる(知識の応用)ことができるようになる2)という前提で教育活動に取り組みます。このとき、教育の中心となる人物は学習者で、教員は学習者に学びが発生するように授業やカリキュラムをデザインしコーディネートする、コーチやファシリテーターの役割を担います。
CBCでは、この構成主義の考えを基にカリキュラムを構築していきます。ですから、まずは教員側のもつ「人はいかにして学ぶのか」という前提を見直していく必要があります。
構成主義はさまざまな学習理論の総称
「構成主義」はまとまった1つの理論ではありません。「違う時代と違う場所、互いに関連の見えないところで独自に発展した理論やモデルを、現代の研究者が「構成主義」というカテゴリーでくくりまとめた、と見なした方がよい」3)と述べられているように、さまざまな学習理論の総称として「構成主義」という言葉が使われています。
実際の教育現場では、構成主義と客観主義の間で、「あれかこれか」といった二者択一の考え方をするのではなく、状況に合わせてうまく組み合わせて活用していく必要があります4)。本校でも、知識注入型の授業と、概念形成型の授業とが混在している状態で、また概念形成型の授業は発展途中なので、必ずしも全てがうまく成果につながっているわけでもないのです。どうすればもっと良い授業にでき、学生の深い学びにつながっていくのかは、日々学生の反応を観ながら、悩み、振り返り、研修と改善を続けています。
リン・エリクソンの考え方
リン・エリクソンも構成主義の考えを基盤にしていますが、著書『思考する教室」の中で、従来のカリキュラムや指導は知識とスキルを焦点にした「2次元モデル(図2左)」で設計されていたが、概念型カリキュラムは知識、スキル、概念の理解による「3次元モデル(図2右)」で設計すると述べています5)。

また、エリクソンは概念型カリキュラムを提唱するうえで、教えることを「知識の構造」(図3のA)と「プロセスの構造」(図3のB)に分けて捉えています。
たとえば本校での「知識の構造」の活用事例としては、入学してすぐに履修する「泉州地域学」があります。学生は5人の地域で活躍されているプロフェッショナルのお話を聴き、それぞれの「教材としての外部講師」の文化的背景を事実として知ります。トピックは「泉州地域で活躍する地元のプロフェッショナル」で、概念は「文化」と「プロフェッショナル・アイデンティティ」です。それぞれの事例から学生はさまざまなパターンを見つけ出し、これらを一般化できる文章を考え出します。たとえば、「人はそれぞれ異なる価値観や信念のもと仕事をし、地域で生活をしている」「個人の文化は価値観や仕事の仕方に影響を及ぼす」「個人の文化的背景や信念を尊重した看護はパーソンセンタードケアにつながる」「看護師は患者の文化的背景を知り尊重することでよいケアの提供につながる」などです。
一方「プロセス(スキル) の構造」では、学生は1人の人(知人や友人、誰でもよい)の文化的背景や価値観を知るためのインタビューを実施する課題に取り組みます。インタビューのプロセスを体験し、コミュニケーションスキルの練習をします。概念は「文化」と「コミュニケーション」です。一般化としては「患者のもつ価値観など文化的背景に焦点を当てながらコミュニケーションを取ることで、その人の希望や何を大切にして病気と向き合っていくのかに気づき、より良い看護を提供できる」、「ただ健康のために必要なことを伝えるのではなく、その人がどう感じているのか、何を大切にして生きているのかを知ろうとする姿勢が看護師には必要である」などの文章が生まれました。これらの一般化を、実際の実習などで活用してみることで、更なる新しい事例(事実)から既存の一般化が強化されたり、改善されたり、新しい一般化が生まれたりします。この循環の中で文化についてのコンセプトが学生の頭の中に形成されていくように設計します。(図3) 。
また、知力を発達させ、学習意欲の向上を図るためには、低次の思考(事実とスキル)と高次の思考(概念)の間で相乗作用を生み出さなければなりません。エリクソンはこの低次と高次の思考の相互作用を引き起こすようなカリキュラムが概念型のカリキュラム(英語ではコンセプト・ベースド・カリキュラム)であると定義しています6)。

点から面を形成し、間違いを修正しながら前進する
日本では、今井が低次の思考を点、高次の思考を面と捉え、低次の思考から高次の思考への変化を「点から面を形成する」と表現しています。ただしこの「面」を作るときに間違えた推論(アブダクション推論)もしながら面を作るので、間違いを修正しながら前進するための足場がけが必要で、これが教師の役割であると述べています7)。
この点から面へのアブダクション推論の精度を上げていくことで概念変化を促進し、高精度のアブダクション推論が可能となっていくような学習環境や教材を提供することが重要です。そのためには学生が自らの失敗や思い込みに気づく機会が繰り返し必要で、教育者は学生の間違いや失敗は学習のチャンスとして捉え、ネガティブな感情で反応せずに、新しい知識へと足場かけをしていくことが重要となります。CBCはこうした理論の上に成り立っており、学生の中にある既存の概念の変化を活用しながら理解を促す、脳科学のエビデンスに基づいたカリキュラム構築方法の1つであるといえるでしょう。
CBCを支える枠組み
CBCは、コンセプト・アプローチと呼ばれる一連の教育的アプローチの中の1要素となります。Giddensが定義するコンセプト・アプローチには、以下の6つの要素が含まれています。これら6つが統合されることでより大きな教育的効果を発揮します8)。
①コンセプト
さまざまなカテゴリーに属しているコンセプトの中からどれをカリキュラムに含めるかは自由で、各学校がそれぞれの教育理念・使命・ビジョンに合わせて選択する
②エグゼンプラー(例示)
コンセプトを説明するために使われる代表的な事例
③コンセプト・ベースド カリキュラム
④コンセプト・ベースド インストラクション
コンセプトを活用した指導
⑤コンセプト学習
学生に発生する概念的な理解
⑥学習の評価
学生の形成評価と総合評価、コンセプト・アプローチの評価、教員の教授方法の評価など
教育理念と教育目標から枠組みを設計する
コンセプトに基づいてカリキュラムを開発するとき、一番初めに話し合うべき内容は、学校の教育理念と教育目標についてです。「時代のニーズに適応しているのか」「本当に我々が目指すものと一致しているのか」「日々の教育実践と理念が乖離していないか」などについて教職員間での共通認識が必要となります。
本校でも、新カリキュラムに向けてディプロマ・ポリシー(図4の「6つのP」)、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーについて話し合い、旧カリキュラムから新しく改定しました。コンセプト・アプローチでは、「何を教えたか」ではなく、「学生が何を学んだのか」というところに焦点を合わせて考えるので、カリキュラム構築時は、卒業時の学生像(=ディプロマ・ポリシーを全て達成した状態)を教職員全員で共通認識し、そこから逆算して授業や実習を配置していく逆向き設計で枠組みを構築します。

コンセプトをカリキュラムに組み込む
次に、「どのコンセプトをどの順番でカリキュラムに組み込んでいくのか」ということを決める必要があります。カリキュラムに組み込むコンセプトを決定する上で重要なのが、コンセプト・カテゴリーと呼ばれるもので、たとえばGiddens(第1回参照)は、①健康と疾病のコンセプト②看護専門職のコンセプト③ケアの受け手のコンセプトの3つのカテゴリーに分類しています8)。一方Pearson(同)では、①生物物理学的②心理社会的③生殖④看護職⑤ヘルスケアの5つのカテゴリーに分類しています9)。
カリキュラムの枠組みの視覚的モデルを作成すると、教員と学生がカリキュラムを理解するのに役立ちます。図4は本校のカリキュラムのイメージモデルで、図5は先行文献で紹介されていたカナダの大学のイメージモデルです。そして、図6はこのカナダの大学のカリキュラムを開発するときに大きな影響を与えた要素を図式化したものです。本校のカリキュラム開発のときとよく似ているので参考に掲載します。


どのコンセプトを何個採用するのかについては、「これが正解」というものは決まっていません。各校の特色に合わせて編成が可能で、世界中に多種多様なコンセプトカリキュラムが存在しています。アメリカの場合では、Giddensの教科書が発行されてから、Giddensのコンセプトが広く活用されましたが、その後Pearsonの教科書に変更している大学もあります。また独自に概念分析を行い、カリキュラムを編成した例も報告されています10)。
このように、各校が独自に学校の地域性や卒業生の主な就職先や、どのようなコンピテンシーをもつ学生を育てたいのかに合わせてカリキュラムに取り入れるコンセプトを選択し、個別性のあるカリキュラムを組み立てることができるのもCBCの魅力の一つといえるでしょう。学生に「正解を求めず自分で考える力」を求める私たち教員自身が、「正解を求めず自分たちでオリジナルのカリキュラムを立ち上げていく」ところから、CBCがスタートするのかもしれません。
1)久保田賢一:構成主義パラダイムの学習理論. 関西大学総合情報学部紀要 情報研究 36:47, 2012
2)H・リン・エリクソン, ロイス・A・ラニング, レイチェル・フレンチ:思考する教室をつくる 不確実な時代を生き抜く力 概念型カリキュラムの理論と実践(遠藤みゆき, ベアード真理子訳), p31, 北大路書房, 2017
3)前掲1), p.44
4)生田孝至, 後藤康志:構成主義的な学習観の教育への展開. 新潟大学教育人間科学部紀要10(1):4,2007
5)前掲2),p.11
6)前掲2),p.15
7)今井むつみ:学力喪失, p.218,岩波新書, 2024
8)Giddens JF:Matering Concept-Based Teaching and Competency Asessment, A GUID FOR NURSE EDUCATORS, 3rd edition, ELSEVIER, 2024
9) Pearson Education: Nursing: A Concept-Based Approach to Learning, Third Edition(1),Pearson Education, 2019
10)Lee-Hsieh J, Kao C, Kuo C, et al.: Clinical Nursing Competence of RN-to-BSN Students in a Nursing Concept-Based Curriculum in Taiwan. Journal of Nursing Education 42(12): 536-545, 2003