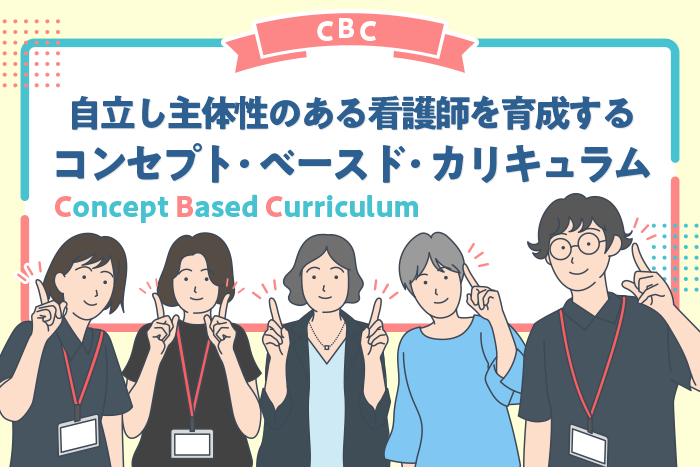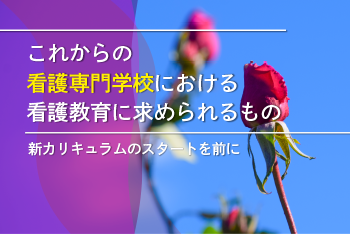泉佐野泉南医師会看護専門学校(大阪府泉佐野市)では、保健師助産師看護師学校養成所指定規則第5次カリキュラム改正を機に、全面的にコンセプトに基づくカリキュラム(コンセプト・ベースド・カリキュラム、CBC)を導入しています。その実装には困難も待ち受けていたものの、教員自身がもう一度「教育とは何か」を振り返る機会となり、「教えつつ学ぶ」組織へと進化し、また学生の主体性も年々高まってきているそうです。ここでは同校が培ってこられたCBCに関する経験や知識・ノウハウを、全6回で共有いただきます。
CBC導入の経緯
原点は創設期の地域への思い
第1回では、まずなぜ本校がコンセプト・ベースド・カリキュラム(以下CBC)の導入に至ったのか、その経緯についてお話しさせていただきます。今回、このような機会を与えていただき、改めてCBCの導入に至った経緯を振り返ってみると、原点は本校の創設者達の地域への熱い思いにあると考えます。
本校は創設期から①地域の看護師不足を改善する、②看護の質の向上により地域医療の質を向上するという強い目的意識を持ち、前身の准看護師養成所を全日制3年課程の看護師養成所に変更して、2002年に泉佐野泉南医師会の先生方と地域の人々の力を借りて創設されました。創設当時から、アメリカでの海外研修、インターネット・ライブで南極やアメリカの人々と学生が直接交流するという国際看護学の授業をはじめ、田植えや畑作業、餅つき、教育キャンプなどのユニークなカリキュラムが豊富で、学生が「看護学校なのに、なぜ?」と驚くような体験学習の機会を提供しつつ、のびのびと明るく元気な学生を育てる校風がありました。初代学校長の谷口定之先生は口癖のように「君たちは僕の太陽だ!」と学生におっしゃっていたことから、同窓会は「IS太陽」(ISは泉佐野泉南の略)と呼ばれ、今では822人の卒業生が入会し、さまざまな現場で活躍中です。いろんな卒業生が毎日のように学校に帰ってきて、何かと学校のお手伝いをしてくれています。
また、創設当初の苦労話として、初代副学校長の今阪洋子先生から、ライブ授業をするためのインターネット回線の設備や高いコンピューター機材などの購入に対して「『あなたは看護の学校ではなくコンピューターの学校を作るつもりか?』といろんな方に反対された」とお聞きしていました。今阪先生は2015年にお亡くなりになりましたが、2020年のCOVID-19 で対面授業が困難となったとき、創設時の先行投資のおかげで、全ての教室でインターネットが使えるWi-Fi環境も整っていたことから、1コマの授業も中止することなくオンライン授業に切り替える事ができました。この経験から私達が学んだことは、「20年先の未来を見据えて学校を運営しなければならないこと」「教育に必要なことは周囲の反対にあっても実践すること」でした。
きっかけは臨床判断ティーチングメソッドの研修
そんな中、2020年12月に開催された日本看護学校協議会の教育研修会「臨床判断モデルの実際と看護基礎教育への活用」に参加しました。講師の三浦友理子先生をはじめとする3人の先生方のお話の内容がとても腑に落ち、すぐに『臨床判断ティーチングメソッド』1)を教員全員で購入して読み始めました。そして、その中で紹介されていた「コンセプト」の考え方に関心をもったことがCBCを導入するきっかけとなりました。
その後、米国のUniversity of Kansas School of Nursingでコンセプトに基づくカリキュラムを先駆的に構築したGiddens博士の“Less is more”2―4)の考え方が示された論文を読み進めることで、自分の頭がパラダイム・シフトして、“新カリキュラムの単位数は増えるが、必ずしも教授時間を増やすのではなく、逆に教育内容や方法を精査して教授時間を減らすことが可能である”と気づいた時に「私たちが次世代の後輩たちに残していくべき内容はこれだ!」という確信に至りました。以下に、導入に至った理由をもう少し詳細に説明させていただきます。
カリキュラム・オーバーロードの回避
ここでの「コンセプト」とは、簡単に言うと概念のことで「メンタルモデル(心的イメージ)」のようなものです5)。CBCでは、科目を領域別ではなくコンセプト別にすることで科目間の重複を減らし、教授時間を削減できる仕組みになっています。実際に、本校の旧カリキュラムで99単位3045時間だったものを、新カリキュラムでは102単位2820時間へと、教育時間を225時間削減することができました。その結果、教育キャンプや海外研修など、本校の特色と伝統の部分を縮小することなく、新カリキュラムでも教科外活動の時間を確保することができ、学生には反転授業で授業以外の時間に事前学習や事後課題などに取り組める自由な時間を提供できるようになりました。
新カリキュラムの地域・在宅看護論は領域横断的視点が必要
新カリキュラムでは地域・在宅看護論が新設されたこともあり、これからの看護師はとくに地域・在宅の視点をもつことが重要かつ必須となります。実際に地域で出会う患者たちは発達段階がさまざまで、領域別ではなく領域横断的な視点が求められます。CBCはコンセプト別に患者を観る力を養っていくので、まさに地域包括ケア時代の看護教育に適していると考えました。
「教える」中心から「学ぶ」中心へ転換
CBCは、人間が本来もち備えているパターン認識能力を使って学生がコンセプトと呼ばれる概念を自分の中で意味づけ、既存の知識と関連付けて学習していく方法です。学生の中での学びの結果として、新しい状況下でその学びの転移が起こるといわれています。CBCは、教員が教えた内容の理解を通して、学生がどう学びを応用できるかに焦点を当てて考えます。ですから、これまでのTeaching中心の考え方から、学生のLearningを中心にするパラダイム・シフトしたカリキュラムで、今の時代に求められている変化を起こせると考えました。
臨床判断能力の促進の効果
臨床判断モデルを構築したタナーの文献の中でもCBL(コンセプト・ベースド・ラーニング)を紹介しており6)、ルーブリックを開発したラサターもニールセンと共同で、学習ガイドを用いたCBLの実施によって学生の臨床判断能力が高くなると述べています7)。先行文献から私達が読み取ったのは、「CBC+臨床推論+ルーブリック評価=臨床判断能力UP」という構造でした。またアメリカの多くの大学でもCBCは採用されており、現地姉妹校の教授からその効果が高いと推薦していただいたことも導入を後押ししました。
教員のチーム力向上の起爆剤
CBCを取り入れるためには、カリキュラムのオーバーロードをなくすために、教員全員でその科目で何を教えているのか、互いの授業の内容を全て情報公開し、教育内容の重複や漏れをなくす必要があります。さらに、担当するコンセプトの科目によっては、これまで自分が教えたことのない領域(たとえば、成人領域の担当教員が小児の呼吸の問題についても講義するなど)も担当することになり、最初は教員間でカオス状況が生じます。本校はこのカオスを好機と捉え、この際全てをフルオープンにして、全員で全部の科目を整理して内容検討し、みんなで授業を再構築していこうと考えました。これまでの教員経験年数や担当領域に拘らず、全員CBC教員1年生として一緒に学ぶ「共同体としての学校」を作るチャンスであると捉えました。
導入に向けての学習
CBCはまだ日本語の教科書がない状況で、英語の原本を翻訳しながら教員間で共有学習を進めていたところ、とある知人から日本で最初にCBCの導入を試みた津波古澄子先生(現京都看護大学大学院)を紹介していただきました。早速、本校の教員研修に来ていただき、CBC導入に向けてのご指導と励ましの言葉とともに、教員の思考につながる“頭作り”に必要な参考図書をたくさん教えていただきました。
津波古先生からは、「学習とは?」「教員とは何をする人なのか?」「学生と関わるときには、何をゴールにして関わるのか?」など、教員としての在り方をまずは振り返る必要があることに気づかされ、さらに定期的にファカルティ・ディベロップメントの機会をいただき、アメリカからのオンライン講演などに教員全員で参加させていただきました。そうして、わからない部分は相談できる心強いメンターのサポートも頂きながら、新カリキュラムの導入に至ることができました。CBC実装のうえではこのような教育ネットワークの必要性を感じています。
おわりに
本校での副学校長就任当時、私には管理者経験がなく、専任教員からいきなり副学校長の職を拝命しました。自分ができないこと、わからないことは他者の力を借りるしかありません。「わからないので助けてください」「経験が浅いので教えてください」という気持ちで臨みました。ですから、これまで教務主任や実習調整者をはじめとする教職員、学校長をはじめとする医師会の先生方、地域の実習施設の方々、在校生と卒業生、外部講師の先生方、地域の患者会や住民の方々、そしてアメリカの姉妹校の先生方にも助けていただきながら創り上げてきた学校教育ということになります。“みんなでつくるから面白い”という創造の喜びもたくさん体験しました。
今では、何より卒業生が教員や実習指導者、病院の管理者、同窓会役員として育ち、時には「ちょっと近くに来る用事があったので」とか「野菜を収穫したから」といって学校に帰ってきてくれることがとても嬉しく、卒業後も本校が卒業生の人生の一部であり続けられることに感謝しています。彼らがさまざまな形で悩み苦しみながらも明るく一生懸命生きている姿を見て、こちらの方が勇気や元気をもらいます。学生や卒業生はまさに学校を照らしてくれる太陽なのです。そういう彼らの姿を見て、看護とは素晴らしいものであり、看護師になるということは人生をより豊かに生きることにつながるのだと実感しています。このことをより多くの学生に理解してもらいたいと願っています。
看護は人々を苦しみから解放し、幸福に導く尊い学問ですし、たとえば、もし国民全員が看護の知識を持てば、国全体の医療費は軽減できるはずです。自分自身の潜在能力を最大限に活かす方法も看護が教えてくれます。CBC導入のための学習の歩みは、そういった看護の本質や教育の本質についても考える機会を私たちに与えてくれました。こうして学びが楽しくなると、人は主体的に学習するようになります。CBC導入期には、「まずは教員自身がHappyであること」そして「学生を信頼すること」というような合言葉が、教職員の中で飛び交っていました。
この後の5回は、本校の教員がリレー方式でそれぞれの視点からCBCについて語りますので、どうぞお楽しみください!
1) 三浦友里子, 奥裕美: 臨床判断ティーチングメソッド. 医学書院, 2020.
2)Giddens JF & Brady D: Rescuing nursing education from content saturation: The case for a concept-based curriculum. Journal of Nursing Education 46(2): 65-69, 2007
3)Giddens JF: Concept for Nursing Practice, 3rd ed, Elsevier, 2021
4)Giddens JF: 概念基盤型学習のアプローチ:根幹は“Less is more”にあり—Giddens教授との対話から(津波古澄子監訳,宮武綾音翻訳). 看護教育: 59(12), 2018
5)遠藤みゆき:近年の世界の教育を捉え直す枠組み コンピテンシーとコンセプト学習. 看護教育 66(3), 307, 2025
6)Tanner C: Thinking like a nurse: A research-based model of clinical judgment in nursing. Journal of Nursing Education 45(6), 204-2011, 2006
7)Lasater K, Nielsen A: The influence of concept-based learning activities on student’s clinical judgement development. Journal of Nursing Education 46(8):441-446, 2009