SLDの概要
今回は限局性学習症(Specific Learning Disorder:SLD)を取り上げて説明していきたいと思います。学習障害(Learning disability:LD)の概念は、1962年にアメリカの教育学者であるサミュエル・カークが教育的な概念として提唱したものです1)。
“学習障害”という語の定義
わが国で用いられる学習障害の定義には大きく分けて2つあります。ひとつは文部科学省が定義した教育用語としてのLD(Learning Disabilities)であり、もうひとつはDSMおよびICD-10に基づく医学用語としてのLD(Learning Disorder)です。文部科学省は学習障害を次のように定義しています。
学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すさまざまな状態を指すものである。学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない2)。
この定義は教育の観点から学習能力に着目したものとなっています。一方で、医学的概念としての学習障害は「読み」「書き」「算数」の3領域に限定した障害として定義されており、聞いたり話したりという部分は含まれていません。つまり、「限局性」という言葉が示すように、全体的には理解力などに遅れはないにもかかわらず、「読み」「書き」「算数」のうち特定の課題の学習に大きな困難がある状態のことを指します。また、DSM-5-TR では「失読症:ディスレクシア(dyslexia)」が読字障害の、「失算症:ディスカリキュア(dyscalculia)」が算数障害の代替用語であると明記されています3)。ディスレクシアは、学習障害の概念よりも古くから報告されており、1896年にイギリスのウィリアム・プリングル・モーガンによって症例報告が行われています。この報告は読字と書字に限定されたものでした4)。
SLDに含まれる主な障害
SLDは、単に「国語の成績が悪い」「数学の問題が難しい」という障害ではありません。さまざまな認知能力、「聞いたことや見たものを処理する能力」の不足が、結果として「読み」「書き」「算数」の苦手さとして現われたものです。年齢によって求められる学習能力の水準が違うため、学年(年齢)が上がるまで明らかにならないこともあります。SLDはADHDと併発することが多く、ADHD児の25-40%はSLDであり、SLDの15-26%はADHDの診断基準に当てはまると考えられています5)。
読字障害(失読症:ディスレクシア)
医学的診断としてのSLDは、対象となる学業スキルとして(1)読字、(2)文章理解、(3)書字、(4)文章記述、(5)数の操作、(6)数学的推論が含まれています。このうち、文字の読み障害があると、結果的に書字の障害も呈するため、ディスレクシアは 「発達性読み書き障害」とも称されます。読み書き障害の背景には、音韻処理困難があり、表記された文字とその読み(音)の対応が自動化しにくく、それを司る脳機能の発達が未熟なことがであるとされています。そのため、正確あるいは流暢な単語認識が困難になり、文字記号の音声化が稚拙になるといった特徴が見られます。他にも、視覚情報処理に問題があり、文字が裏返って見えたり、歪んで見えたりする場合もあります。
ここで留意しておきたいことは、読字障害の子どもは文字が読めないと表現されることがよくありますが、これは誤りだという点です。正しくは読むのが非常に遅い、よく間違えるというものです。文字を読むことに時間がかかり、何度も間違えることがあるといった状態では、読むだけで疲れてしまって、意味を把握する段階まで至りません。そのため、読書に対する拒否感が生じてしまうことになります。結果、語彙や知識が不足して、さらに読むことが困難になっていきます。
書字障害
書字障害は、文字の形を認識したりする視覚情報処理の問題が原因の場合もありますし、読字障害と同じく、音韻処理に問題がある場合も発生します。多くの場合は、読字障害と併発します。英語圏などで使用されるアルファベットは比較的シンプルな文字の形をしていますが、漢字のように複雑な形の文字では細部まで再現するのが難しいことも影響しています。「読み」には問題ないが、「書き」のみに困難が生じる場合、視覚情報処理に関連している可能性があると考えられています。看護学生に読字障害や書字障害があると、レポートや実習記録を書くことが困難になるでしょう。
算数障害(失算症:ディスカリキュア)
算数障害は臨床診断の困難さや障害内容の定義の不一致などもあって十分解明されているとは言えません。算数が多くの認知的処理を要する複雑な作業であることや、さまざまな神経基盤の関与が指摘されていることも病因・病態の特定を難しくしています。現在、算数障害の中核をなす認知障害として指摘されているのが「数量の処理障害」です6)。算数障害のある子どもは2つの数量を比較して大小や多少を判断することが苦手です。多数の物を一見しておよその個数を把握することが難しく、たとえば100個程度の物を見て10000個と答えることがあります。数字を見ても表す量をイメージできず、計算をしても量の変化として掴みにくいことが算数障害の中核にあると考えられています。看護学生に算数障害がある場合、点滴の滴下計算やBMIなどの算出ができないこともあるかもしれません。
SLDを有する学生への対応
では、事例からSLDを有する学生への対応と合理的配慮について考えてみましょう。
Cさんは、18歳の看護系大学に通う1年生です。まじめに授業に取り組んでいますが、レポート課題の提出はいつも期限ぎりぎりになっています。提出されたレポートは、誤字が多く、文法の誤りもしばしば見られます。定期テストもいつも時間いっぱい問題を解いていますが、あまり成績は良くありません。質問すると答えられることもあるので、全く理解が出来ていないわけではないようです。基礎看護実習では、日々の行動計画と振り返りを手書きで書いて提出しなければなりませんが、Cさんの記録は、句読点の位置が違っていたり、文字の大きさが整っていなかったりと、非常に読みにくいものでした。
教員:Cさんの記録ですが、誤字脱字が多いですね。記録を書くのに何か問題がありますか?
Cさん:子供の頃から、書くことがうまくできません。読むのも時間がかかるので、読んだり書いたりすることは避けてきました。
教員:その他に苦手なことはありますか?
Cさん:算数もとても苦手です。あと何分で授業が終わるとかも計算するのが難しくて、いつも友達に教えてもらっています。テストの時も時間配分がうまくできないので、できるだけ早く解こうと思っているんですが、問題を読んでいるとすぐに時間が過ぎてしまいます。
この事例は、読み書きの障害と算数障害のある学生の事例です。Cさんの場合も、「読んだり書いたりするのを避けてきた」と言っていますので、語彙や知識の不足があっても不思議ではありません。口頭試問などで知識があるかどうかの確認を行い、知識が不足していれば、その補強も行う必要があります。SLDの支援は、何度も読ませたり書かせたりというような訓練をすることではありません。UD(ユニバーサルデザイン)書体(図) を使用し可読性を高めたり、パソコンの読み上げソフトや音声入力ソフトを利用して読み書きの負荷を軽減したりするなど、さまざまな工夫をし、少しでも学びづらさを軽減していくことが大切です。

紛らわしい線をなくしたり、線の間に十分なスペースをとることで可読性を高めている。
Cさんへの合理的配慮としては、「C子さんへ文書を渡す場合は、UD書体を使用する」「書類やテストの漢字にはルビを振る」「授業の録音や撮影を認める」「レポートの提出期限を延長する」「テスト時間を延長する」「滴下計算などの計算を要するものについては、電卓の使用を認める」といったことが考えられると思います。
SLDだけでなく、どのような障害でも、当事者の抱える苦手さや生きづらさが軽減されるような支援を考え、当事者が自分を責めたり恥じたりしないような配慮を考えていく必要があります。
1)Kirk SA: Educating exceptional children, Houghton Mifflin, 1962
2)文部科学省: 学習障害児に対する指導について(報告). 特別支援教育について, 1999年7月2日, 〔https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/002.htm〕(最終確認:2024年10月22日)
3)日本精神神経学会(監修), 高橋三郎, 大野裕(監訳)ほか:DSM-5-TRTM 精神疾患の診断・統計マニュアル, p.75-76, 医学書院, 2023
4)Morgan WP: A case of congenital word blindness. British medical journal 2: 1871- 1378, 1896
5)Willcutt EG, Pennington BF: Comorbidity of reading disability and attention-deficit/hyperactivity disorder: differences by gender and subtype. Journal of learning disabilities 33(2): 179-191, 2000
6)Ashkenazi S, Black JM, Abrams DA et al: Neurobiological underpinnings of math and reading learning disabilities. Journal of learning disabilities 46(6) : 549-569, 2013

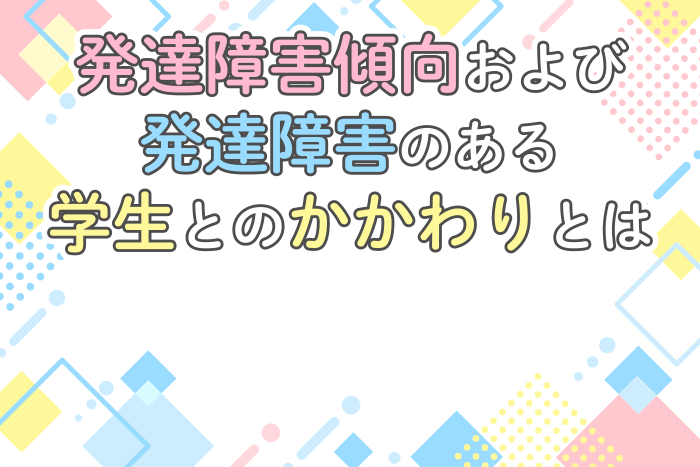


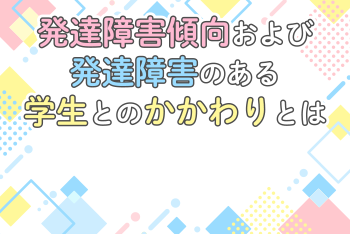
_1687847570403.png)