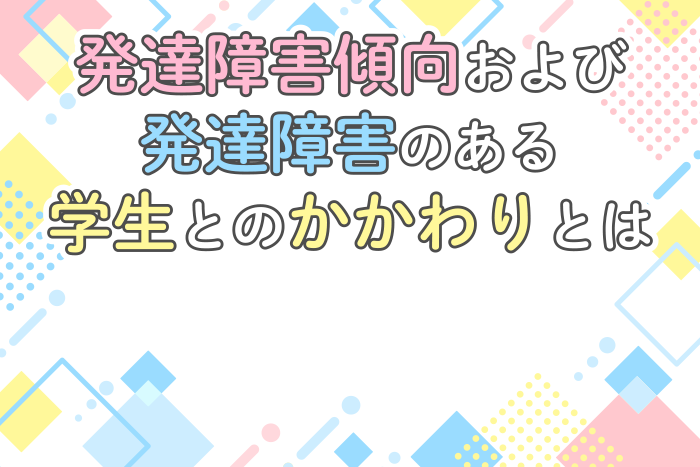コミュニケーションに難しさが生じる要因
今回は、コミュニケーションに困難を抱える学生について解説します。
まず、「コミュニケーション」という言葉の意味についてですが、はっきりとした定義はありません。なぜなら、コミュニケーションは使用される場面によって目的が異なるからです。一般的な定義として、広辞苑(第七版)には「社会生活を営む人々の間に行われる知覚・感情・思考の伝達」と説明されています。また、文化庁では「我々が伝えたい情報や、自分自身の考え、気持ちをお互いに伝え合うこと」とされています1)。これらの定義から、コミュニケーションには思考や感情のやり取りも含まれることがわかります。
こうした思考や感情のやり取りに困難が生じる原因はさまざまです。コミュニケーションの困難さは、主に以下の5つの要因に分類されると考えられます。
1. 神経発達症(発達障害)(例:自閉スペクトラム症、言語症など)
2. 神経学的疾患(例:脳卒中、外傷性脳損傷など)
3. 精神疾患(例:社交不安症、統合失調症など)
4. 認知機能の低下(例:アルツハイマー型認知症、前頭側頭型認知症など)
5. 先天疾患(例:聴覚障害、口蓋裂など)
このように、コミュニケーションの困難さの要因は多岐にわたります。それぞれの要因によって異なる支援が必要となるため、個々の特性に応じた適切な対応が求められます。
看護学生に多いコミュニケーションの困難さの要因
これら5つの要因の中で、看護学生に多いものとして、発達障害と精神疾患が挙げられます。発達障害に関連するコミュニケーションの困難については、これまでに解説した自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如多動症(ADHD)に加え、言語症や語音症、児童期発症流暢症(吃音)、そして社会的(語用論的)コミュニケーション症も原因となることがあります。言語症は、語彙や構文、話法の理解や表現に困難があり、会話の意味や構造を正しく理解したり、適切に伝えたりすることが難しい状態です。語音症は、発音に困難があるため、言葉をはっきり発することができません。また、吃音は、会話の流暢性に問題があり、言葉が詰まったり、繰り返されたりすることが特徴です。さらに、社会的(語用論的)コミュニケーション症は、言語を適切に社会的文脈で使用することが難しく、会話の順序や相手に応じた発言ができない状態を指します。
次に、精神疾患が原因となるコミュニケーション障害について考えてみます。統合失調症では、思考の混乱や言葉のまとまりの欠如があり、会話の流れや意味がうまく伝わらないことがあります。気分障害のうつ状態では、発話が減少したり感情表現が乏しくなり、会話が不明瞭になる場合があります。躁状態では、過度に活発な会話や、意味不明な言葉の繰り返し、話の脱線などが見られることがあります。社交不安症では、人前で話すことへの強い恐怖や不安から、コミュニケーションを避ける傾向があります。場面緘黙では、特定の場面で言葉を発することができなくなることがあります。また、PTSD(心的外傷後ストレス障害)が原因で、特定の場面や状況においてコミュニケーションの障害が生じることもあるかもしれません。
コミュニケーション障害に対する支援は、各原因に応じた適切な対策を講じることが必要です。学生が困る場面はさまざまありますが、どのような支援を行うにも、まずはそれが何故起きているのかのアセスメントは欠かせません。
発達障害のある学生へのコミュニケーションの支援
自閉症スペクトラム症
自閉スペクトラム症(ASD)では、視覚的なサポートを活用することが有効です。スケジュールや指示を視覚的に提供し、学生が理解しやすいように工夫します。また、会話の流れを学ぶためのロールプレイや模擬患者との練習が効果的です。
ADHD
ADHDの学生は、衝動性や集中力の低下によって、会話や報告、患者とのやり取りにおいて困難を感じることがあります。とくに、衝動的に発言したり、会話の流れが途切れたりすることがあり、これがコミュニケーションにおける障害となります。ADHDの学生に対する支援として、会話の際には、発言のタイミングを意識させることが必要です。具体的には、順番に話すことを守り、学生には自分の意見を述べる前に他者の発言を十分に聞くよう促します。また、誰の発言の順番かが見て分かるように発言順序カード(図1)などの視覚的手がかりを活用することで、会話の順番を明確にし、衝動的な発言を防ぎます。加えて、短いセッションでの会話を心掛けることで、学生が集中力を持続しやすくなり、より効果的にコミュニケーションを取ることができます。

言語症・語音症
言語症の学生には、語彙や構文の理解を助けるために繰り返し学習を行い、簡潔で明確な指示を提供します。学生が言語構造を理解しやすいよう、図や色分けを活用した資料などの視覚的なサポートを提供することが効果的です。
語音症には、発音の練習を繰り返し行うことが大切です。具体的には、発音のコツを教え、学生が静かな環境で集中して練習できる場を提供します。また、言語聴覚士と連携していくことも大切です。
吃音
吃音の学生には、発話の流暢性を高めるために、リラックスした環境で練習を行い、会話のペースを意識的にゆっくり目にして、学生が落ち着いて話せるようサポートします。また、吃音は緊張や不安を増すことで悪化するため、リラックス法(深呼吸やリラクセーションエクササイズ)を取り入れ、発話時のストレスを軽減することも効果的です。
社会的(語用論的)コミュニケーション症
社会的(語用論的)コミュニケーション症では、自閉スペクトラム症と同じく、会話のルールを明確に指導し、会話の順序や適切な発言のタイミングを練習します。ロールプレイやシミュレーションを活用して、実際の場面でどう応答するかを体験させると効果的です。
精神疾患のある学生へのコミュニケーションの支援
精神疾患を原因としてコミュニケーションに困難を抱える場合、まずはその原因疾患の治療が必要となります。訓練や本人の努力だけで改善されるものではないため、受診を勧め治療と並行して支援していくことが大切です。
統合失調症
統合失調症の場合、思考が混乱しやすいため、簡潔で明確な指示を出し、視覚的なサポートを使うことで、学生が理解しやすくなります。また、長時間のセッションよりも短いインタラクションを繰り返し行い、学生が自分のペースで学べるようにサポートします。
うつ状態
うつ状態の学生は、エネルギーの低下や自己評価の低さから、積極的に発言したり活動したりすることが難しいことがよくあります。このため、支援方法としては、ポジティブなフィードバックを積極的に与えることが重要です。たとえば、学生が簡単な質問に答えたり、発言をしたりした際に、「よくできました」や「素晴らしい考えですね」といった肯定的なフィードバックを提供します。このように、小さな成功にも肯定的な反応を示すことで、学生は自信を取り戻し、少しずつ前向きな気持ちを持てるようになります。
また、具体的かつ学生が達成可能な小さな目標を設定することも効果的です。目標を小さく分けて達成感を感じさせることで、学生は一歩ずつ自信を回復し、さらに前向きに取り組むことができます。学業や実習の中で、できるだけ負担の少ない範囲で学生が成功体験を積むことが、うつ状態の悪化を防ぎます。
躁状態
躁状態の学生は、過度に活発で、衝動的に発言したり行動したりすることが多いです。これに対しては、会話や行動を適切に管理するための支援が求められます。まず、短く区切った会話を推奨し、学生が一度に多くの情報を扱わないようにします。長時間会話したり一度に複数のトピックを扱うと、学生が集中できなくなり、話が脱線する恐れがあります。したがって、会話はシンプルで明確な内容にし、学生が集中しやすいようにします。
また、冷静に話すことを促すことも重要です。躁状態の学生は、話すスピードが速くなったり、感情的になったりすることがあるため、学生には意識的に「ゆっくり話す」「落ち着いて発言する」といった指示を与えます。リラックスした状態で話すよう促すことにより、会話がスムーズに進み、学生が落ち着いた状態で意見を述べることができるようになります。
さらに、環境の調整も欠かせません。躁状態の学生が過度に活発にならないように、静かな環境や落ち着いた場所での学習や会話を進めます。周囲の刺激を減らし、集中できる空間を提供することで、学生の過剰なエネルギーをコントロールしやすくなります。
社交不安症のある学生の事例
ここでは、精神疾患のなかでも社交不安症をとりあげ、事例を交えてどのような対応を取ることがよいのか考えていきます。
Aさんは、看護系大学の3年生で、実習中の患者とのコミュニケーションに強い不安を感じていました。とくに、患者に質問をしたり、自分の意見を述べたりすることに極度の不安を感じており、実習が進むごとにその不安が増していました。患者と話すときには、自分がどう思われるか、相手にどう見られるかを常に気にしてしまい、話すことができませんでした。実習が進むにつれて、その不安は次第に強くなり、他の学生と比べて自分だけがうまくできていないのではないかという恐怖が広がり、実習に参加すること自体が苦痛に感じるようになっていました。
教員:「Aさん、実習の中で患者とのコミュニケーションについてどう感じましたか?」
Aさん:「正直、すごく不安でした。患者さんに何を聞けばいいのか分からなくて…。それに、うまく答えられなかったらどうしようって思って、結局話しかけられませんでした。言葉が出てこないというか、どうしても怖くて…。他の学生は普通に話しているのに、自分だけできないような気がして、すごく焦ってしまいました」
教員:「患者さんに質問をするのが怖かったのですね。もし話すことができた場合、どんなことが一番不安ですか?」
Aさん:「もし患者さんが私の質問を変に思ったらどうしようとか、自分が変だと思われたらどうしようってすごく怖いです。そう考えると、どうしても声が出せなくなって…」
Aさんのように社交不安症を抱える学生に対する支援では、コミュニケーションの自信を高めることが重要です。以下の方法で支援を行うことが効果的です。
小さな成功体験を積む
最初は簡単な質問や短い会話から始め、徐々に自信を高める支援を行います。ポジティブなフィードバックを通じて、学生が自分の発言に自信を持てるようにします。合理的配慮として、発言が苦手な学生には、発言する時間を十分に与え、他の学生と比較することなく、個別にサポートします。
ロールプレイや模擬患者との練習
実際の患者とのやり取りに近い形で練習を行い、学生が不安なく実習に取り組めるようにします。模擬患者との練習は、実際の場面での不安を軽減する助けになります。合理的配慮として、学生が不安を感じやすい状況では、最初に個別練習の機会を設け、安心して練習できる場を提供します。
定期的な振り返りとサポート
実習後に学生が感じた困難を振り返る時間を設け、次回に向けた具体的なアドバイスを行います。これにより、学生は自信を持って次に進むことができます。合理的配慮として、振り返りの時間を延長したり、学生が一度に多くのことをこなしたりする負担を減らすように配慮します。
環境調整
学生が安心して発言できる環境を整え、他の学生と比較しないよう配慮します。コミュニケーションはなるべく静かな場所で行うことを提案して、他者から見られる不安を感じにくくするサポートを行います。また、実習の前に事前に予測される状況について説明をし、安心感を与えることも重要です。
ストレス管理とリラクセーション
ストレスを軽減するためのリラクゼーション法を学ぶことで、実習中に不安を感じる場面でも落ち着いて対応できるようになります。たとえば、深呼吸やリラックスする時間を取り入れると効果的です。実習前にリラックスできる時間を提供することや、自己管理できる方法を教えることが有効です。
セルフ・アドボカシーの支援
学生が自分の不安や支援が必要な点を理解し、積極的に支援を求められるようにサポートします。自己理解を深めることで、必要な支援を伝えやすくなります。合理的配慮として、学生が自分の不安を教員や他のスタッフに伝えやすいように、支援を求めるスキルをロールプレイやシミュレーションを通じて学んでもらうと良いでしょう。
セルフ・アドボカシーの重要性
セルフ・アドボカシーとは、自分の権利やニーズを理解し、それに対して適切に主張する能力です。どのような人にとっても、自分が持つ特性や苦手なことに対して適切な支援を求めることは重要です。とくに看護の分野では、セルフ・アドボカシーは欠かせない能力だと考えます。なぜなら、看護師自身が自分の特性を理解し、必要なサポートを適切に求めることができてこそ、チーム医療の中で円滑な連携が可能となり、患者に対してより良いケアを提供することができるからです。
また、看護師は患者のアドボケート(代弁者)としての役割も担っているため、自らのアドボカシー能力を高めることは、他者のニーズを理解し代弁する力にもつながります。その意味でも、セルフ・アドボカシーは、看護実践を行う上で非常に重要な能力の一つであるといえます。
セルフ・アドボカシーを育成するためには、以下の方法が有効です。
- 自己理解を深める:学生に自分の強みや弱みを認識させるために、定期的に自己評価を行います。自己理解が深まることで、学生は自分に必要なサポートが何であるかを明確に認識できるようになります。
- 支援を求める練習:学生が支援を求めるスキルを学ぶために、ロールプレイやシミュレーションを用いて練習します。学生に対して、「どのように支援を求めるか」「必要なサポートをどのように伝えるか」を実際に体験させます。
- フィードバックを通じた指導:学生に対して、支援を求める際の具体的な方法を教え、フィードバックを通じてそのスキルを向上させます。実習中に自分の特性やニーズを説明する場面を設けると、セルフ・アドボカシーの意識が高まります。
おわりに
コミュニケーションに困難を抱える学生に対する支援は、発達障害や精神疾患に関連する具体的な障害に応じた方法で行うことが求められます。適切な支援を提供することで、学生は自信を持って患者とのコミュニケーションを取ることができるようになります。コミュニケーションがうまく取れない学生は、孤立感や排斥感を感じることも少なくありません。学生の自信を喪失させないようかかわっていくことが大切です。
1)文化庁:Ⅲ 言葉遣いの中の敬意表現.国語施策・日本語教育,〔https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kakuki/22/tosin02/11.html〕(最終確認:2025年3月27日)