ASDの概要
今回は自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder:ASD)を取り上げて説明していきます。ASDの概念が出てくる前は、早期幼児自閉症、小児自閉症、カナー型自閉症、高機能自閉症、非定型自閉症、特定不能の広汎性発達障害、小児期崩壊性障害、アスペルガー症候群といったさまざまな障害がそれぞれ別のものであると定義づけられていました。
たとえば、カナー型自閉症は、知的障害を合併し、言葉の発達の遅れ、コミュニケーションの障害、対人関係・社会性の障害、パターン化した行動、こだわりを特徴とする障害です。アスペルガー症候群は、知的障害と言葉の発達の遅れがなく、コミュニケーションの障害、対人関係・社会性の障害、パターン化した行動、こだわりを特徴とする障害です。両者の最も大きな違いは、知的能力と言葉の発達ですが、それを除いた他の特徴は非常に似通っています。イギリスの精神科医であるローナ・ウィングは、自閉症とアスペルガー症候群を区別することに臨床的有用性も科学的妥当性もないと考え、両者を同じ特性を持つ連続体(スペクトラム)として捉え、ASDの概念を提唱しました1)。
ウィングらの定義によると、ASDとは、社会性、コミュニケーション、イマジネーション(想像力)の3領域に質的な違いが発達期から存在する障害であると特徴づけられます(ウィングの三つ組み)2)。さまざまな研究の結果、今まで区別していた障害群は明確に区別できるものではなく連続的であることが分かってきたため、ASDの概念は広く受け入れられるようになました。そして、DSM-5(第2回参照)の改訂で、ASDは早期幼児自閉症、小児自閉症、カナー型自閉症、高機能自閉症、非定型自閉症、特定不能の広汎性発達障害、小児期崩壊性障害、アスペルガー症候群と呼ばれていた障害を包括した、下位分類のない単数形の診断概念となったのです。
ウィングの三つ組みにおける3領域
社会性の質的な違い
社会性の質的な違いとは、他者に興味や関心を抱かなかったり、相手の感情や思いに配慮する共感能力がほとんど欠如していたりと、対人関係を築くのが困難というものです。とくに問題となることが多いのが、共感能力の欠如の部分です。
たとえば我々が他者と言葉を交わすとき、相手の心情を推察しながら言葉を選んでいきます。しかし、他者への共感能力が欠落しているならば、その言葉はしばしば一方的なものになるでしょうし、言ってはいけないことであっても口に出してしまうでしょう。“空気が読めない”というのは、ASDの方がよく言われることですが、それは他者に対する共感能力が不足していると起こりやすくなります。看護学生であれば、患者の心情を理解することが実習では必要になりますが、ASDがあるとこのようなことが難しくなってしまいます。
コミュニケーションの質的な違い
コミュニケーションの質的な違いとは、あいまいな表現や比喩などが理解できなかったり、「適当」「多めに」「もう少し」など日常生活でよく使われる幅のある曖昧な表現の解釈が困難であったりというような、言葉の受け取り方や使用が特異的なことです。さらに、視線を合わせること、身振り、体の向き、会話の抑揚といった非言語的コミュニケーションの使用が不適切で、中でも視線が合わないことはよく認められます。
看護師であれば、我々は患者と会話しているとき、目を見たりうなずいたり笑顔になったりと、その時の状況に合わせて非言語的なコミュニケーションを駆使していますが、これらがうまく行えないことになります。看護学生がASDを有する場合、患者の目を見て話さない、教員から注意されていても体の向きが違う方を向いているなど、会話をしていても本当にちゃんと向き合って聴いてくれているのか分からなくなることがあります。
イマジネーション(想像力)の質的な違い
想像力の質的な違いとは、物事を同じ手順通りにしなければ気が済まなかったり、反復的に同じ動作をしたりする特徴のことです。たとえば、特定のものを覚えることを強く好んだり、乗り物のなかでいつも同じ場所に座らないと気が済まなかったりといったことが見られます。どれだけ効率が悪くても一度覚えたやり方でやらないと気が済まない、どんな相手でどんな場面だろうが自己紹介する時には氏名だけではなく好きな食べ物を続けて言うなど、一度定着してしまったものを変えることが困難になります。
これは学校で習ったことを臨床に適応させたり、さまざまな出来事に臨機応変に対応したりすることが困難ということです。我々看護師は患者の状況に合わせて、とっさに対応しなければならないこともありますし、患者の状態は日々変わっていくため毎日同じ業務ということはありません。同一性への固執という特性が強く出ているASDを有する方は、看護師の業務が非常に困難になることがあります。
ASDを有する人がもつその他の特徴
その他の特徴として、感覚過敏、中でも聴覚過敏をもっていることがあります。聴覚過敏があると、遠くの小さな物音でも大きく聞こることがあり、周りの音が多いと苦痛を感じてしまうことも少なくありません。そのため、教員の説明や指示などが周りの音の中に埋もれてしまい、教員の話が聞けていないということが起こる場合もあります。教員の指示がうまく通らなかったりすることもあるでしょう。
ASDの3つの型
ウィングは、ASDのタイプとして、3つの型があると言っています2)。一つ目は孤立型で、他者に対して無関心であり、親愛の感情を示さないタイプです。二つ目は受動型で、人とのかかわりを受け入れることはできますが、自分からは他者とのかかわりを求めません。従順で人に従うタイプと言えます。三つ目は、積極-奇異型で、自分から積極的に他者にかかわろうとしますが、そのかかわり方が一方的であり、相手の状況を無視するタイプです。
このように同じASDであっても特徴の強さも違えば、振る舞い方もさまざまです。ASDや発達障害を有する方と接するときは、診断を気にしすぎるのではなく、人を見るという視点が大事になってきます。
ASDを有する学生への対応
では、実際の事例からASDを有する学生への対応と合理的配慮について考えてみましょう。
B君は21歳の看護系大学の3年生です。同級生とあまり話したり遊んだりしている様子はなく、授業中や休み時間も一人で行動しています。B君は成人看護学実習において、大腸がんの化学療法を行っている80代の女性患者を受け持ちました。この受け持ち患者さんから教員に「B君はいつも言葉が堅苦しくて、私に対する質問しか会話がありません。先日は性に対する考え方や性の満足感を聴かれましたが、看護の勉強に本当に必要なのですか。質問ばかりの会話はしんどくなるので、大変申し訳ないのですが、受け持ちを辞めてもらうことはできますか」と、受け持ちを外して欲しいとの訴えがありました。
教員:さきほどB君の受け持ち患者さんから、質問ばかりされるのが疲れるので受け持ちを外してほしいと要望がありましたが、B君はどのように質問していたのですか。
B君:私は患者さんの情報収集をするために、ゴードンの機能的健康パターンに沿って質問していました。
教員:そうなのですね。質問ばかりだと患者さんは苦痛だと言われていますが、それについてB君はどう思いますか。
B君:適切な看護を行うためには、情報収集が重要だと授業で学びました。適切な看護のために質問していますので、患者さんに我慢してもらえば良いと思います。
ASDを有すると共感能力の欠如から、一方的な会話をすることが多くなります。この事例で、B君は情報収集しなければならないと、ゴードンの枠組みに沿って質問を重ねていました。しかし患者さんにとっては、まるで尋問されているかのように感じられたのではないかと思います。このことについて、B君と振り返ってみても、B君は患者さんの心情については何も言及せず、自分の論理だけで患者に我慢してもらえば良いと言っています。他者の心情を読み取ることが難しいのはASDの特徴です。そのため、患者さんの心情について振り返ってみても、このように自分の論理でしか考えられません。
この場面においてB君への支援としては、具体的な質問の仕方を指導することが良いと思われます。患者の苦痛を軽減させることも看護であり、できる限り患者に苦痛を与えない方法で情報収集することが看護においては必要であることを説明しましょう。そして、口頭で説明するだけでなく、実際に目の前で教員が看護師役を演じることや、学生とロールプレイを行い、不適切な振る舞いを具体的に指摘していくと良いでしょう。あいまいな言葉が多くなるとASDのある人は理解が難しくなっていきます。そのため、質問だけを連続して3つ以上するのは止めるなど、やってはならないことのリストを作り渡すといったような、教育方法を工夫することが必要になります。このような課題を実施するための支援も合理的配慮となります。
ASDを有する学生が問題になりやすいのは、やはりこうしたコミュニケーションにかかわる部分です。我々教員は、多くの学生を指導する中で“普通”や“通常”という感覚を自らの中に作り上げてしまうことも少なくありません。そうした時に、その“普通”や“通常”と考える部分についてしっかり説明しないでいると、ASDを有する学生はうまく行動ができず、自分勝手と見られる行動を取ってしまうことがあります。ASDを有する学生へ説明する時や指示を出すときは、その説明や指示が「誰が聞いてもはっきりわかる具体的なもの」となっているかを考える必要があります。
1)Wing L: The history of ideas on autism: Legends, myths and reality. Autism 1(1):13-23, 1997
2)Wing L, Gould J: Severe impairments of social interaction and associated abnormalities in children: Epidemiology and classification. Journal of autism and developmental disorders 9(1): 11-29, 1979

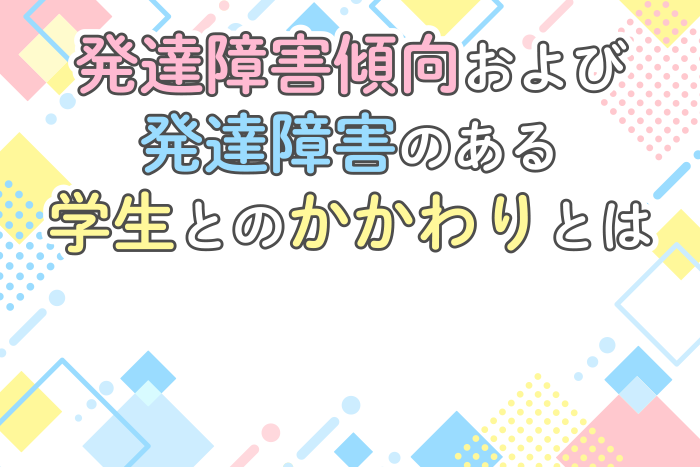


」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)
」サムネイル2(画像小)_1655700691661.png)