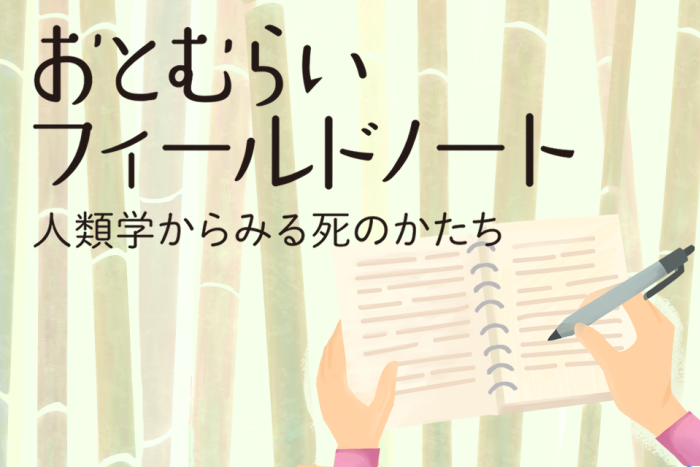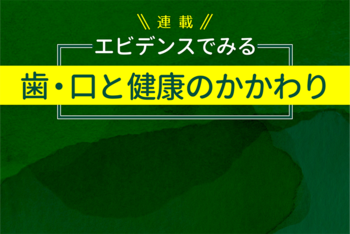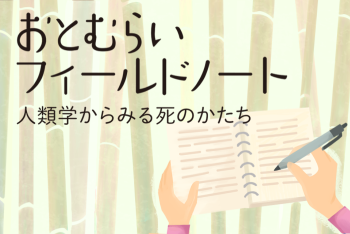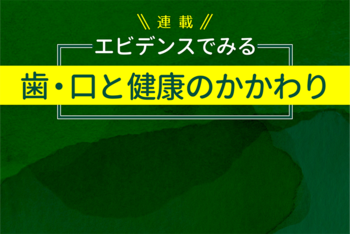まずは、元日に発生した能登半島地震によって今も困難の渦中にある方々に心からお見舞いを申し上げます。多数の大切な命が失われたことに思いを馳せると胸が痛みますが、そんなこともあって「年明け早々から、おとむらいの話は縁起が悪い」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。ただ、こういう時こそ亡き人を弔うことを考えるのは意義があるとも言えるのではないでしょうか。というわけで、このコラムはこれまでと同様に平常運転で進めていくことにしたいと思います。
それに、実は昔からお葬式の夢は吉と言われているだけでなく、一説では初夢の定番にして縁起物の代表格でもある一富士・二鷹・三茄子の続きはなんと「四葬式」という言い伝えもあるほど。このコラムを年明けからご覧いただいてもまったく問題ありませんし、私としても大惨事から始まってしまったこの一年が少しでも良い方向に進めば……という願いを込めて、今回のコラムをお届けしています。
ところで葬送や看取りをめぐる文化や民俗には、このように普通ならば凶とされている出来事を吉として語ったり、日常とはあえて反対のふるまいをしたりするというケースがよく見られます。この、言わば「逆転の発想」についてはまた機会をあらためてじっくり論じたいと思いつつ、ごく一例を挙げてみると……たとえば霊柩車を見かけたときに皆さんはどうしますか? そんな問いかけから、今回は私自身も少しばかり思い入れのある「霊柩車」にまつわる話をご紹介しましょう。
親指隠しのおまじない
私が子どものときは、歩いていようが自転車に乗っていようが、霊柩車を見ると真っ先に親指を隠していました。あっ、自転車のハンドルを握りながら親指を隠すのは危険ですから、令和のおともだち(「大きなおともだち」を含む)はマネをしないようにね! それはさておき、ではなぜそうしていたかというと「あのクルマを見たら縁起が悪く、親指を隠さないと親が早死にするか、もしくは親の死に目にあえない」という思いが心のどこかにあったからです。

個人的な話で恐縮ですが、私は幼いときに父親が他界したので、この上さらに母親までいなくなったら……という気持ちも強かったのかもしれません。ただし、友人たちも同じようにギュッと親指を握りしめていましたから、私だけの個人的なおまじないというわけでもありませんでした。それに今日では洋型霊柩車と呼ばれるズッシリと重厚ながら華美な装飾を排したタイプが圧倒的な主流ですが、私が子どもだった昭和の時代はまるで車の荷台に日光東照宮でも乗っているかのような、いわゆる宮型霊柩車がほとんどを占めていましたから、その一種独特なデザインは子どもならずとも不穏で禍々しい雰囲気をちょっと感じそうではありますよね。

また、30年ほど前にはなりますが民俗学者の常光徹さんが1995年の時点で大学生230名にアンケートをとったところ、霊柩車に出合った際に親指を隠すと回答したのは約6割に該当する137名だったとのこと1)。つい先ほど、私も近くにいた数人ほどの学生諸君に尋ねてみたところ、その内の4割が「そうしていた」「今でもそうしている」「自分はしていないが聞いたことはある」のいずれかに当てはまるという結果になりました。どうやら、若い世代にもまだまだ「霊柩車を見かけたら親指を隠す」というおまじないは健在と言ってもよさそうです。
幸運の黒いクルマ
ところが、これとはまったく逆に霊柩車を見かけるのは縁起が良いという方々も結構いることをご存じでしょうか。とりわけ「勝つか負けるか」を決するような、たとえばスポーツの試合や賭け事などに臨むときは、勝利をもたらす前触れとされているのだとか。またまた個人的な話を持ち出すと、私は競馬場と競艇場と火葬場と墓地がほぼ同一エリアにあるという、悲喜こもごもの人間の一生を凝縮したような大変に素晴らしい地域ですくすくと育ちまして、赤鉛筆をペロリと舐めながら競馬新聞に印をつけているオジサンたちが「さっき霊柩車を見たから、こいつぁきっと万馬券だ!」とうれしそうに馬券売り場へと向かうのを何度か見かけたことがあります。
さらに、タクシーの運転手さんにも同じような言い伝えがあるそうな。先ほど登場した常光徹さんによれば、その場合は「霊柩車が前から来たらその日一日よいことがある。後ろから来て追い越されるとその日一日不幸。後ろから来るのがわかったら角を曲がるとよい」とされているのだそうです2)。タクシーの運転手さんにとって、良いお客さんに出会って順調に稼げるかどうかというのも、ある意味では当たり外れのどちらに転ぶかを賭けるようなものではありますから、縁起を担ぎたくなる気持ちもわかります。
……というわけで今回は私の大好きな霊柩車の名誉を守るためにも、霊柩車が人びとから縁起の悪いクルマとされている一方で、実は幸せの黄色いハンカチならぬ「幸運の黒いクルマ」でもあるのだという話を持ち出してみました。人が亡くなる、そして亡き人を弔うというのはもちろん悲しいことですが、その光景のなかでは「生と死」や「日常と非日常」、そして「ハレとケガレ」といった互いに相反するモノゴトが表裏一体になっていて、単純な意味づけや価値づけができないものでもあります。霊柩車は、そんな弔いの文化の本質を象徴しているのかもしれません。そして今日もどこかでその弔いを受けとめ、支えている人がいます。もしも皆さんが霊柩車を見かけたら、そんなことも心のどこかで思い出してくれるとうれしいですね。
1)常光徹:親指と霊柩車〈歴博ブックレット14〉,p.63,歴史民俗博物館振興会,2000
2)前掲書1),p.70