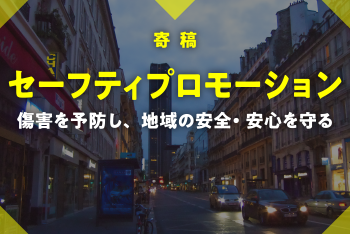DC NETWORK呼吸チームは、在宅での人工呼吸器管理や、在宅酸素療法などの呼吸ケアが必要な家族のケアと育児をしている人を支援の対象としているチームです。呼吸器疾患の方や、呼吸器疾患以外でも在宅で人工呼吸器管理を必要としている方をケアしている家族(ケアラー)の支援を想定しています。
2023年4月1日現在までに2回のDC café(詳細は第1回記事を参照)を開催して、ご参加頂いたケアラー当事者と一緒に時間を過ごしながら、普段の生活の中で感じていること、困っていること、誰かに聞いて欲しいこと、などなど共有する時間を持ちました。こんなご時世でしたので、DC caféはいずれも、残念ながら対面ではなく非対面のZoomでの開催でした。でも、Zoomであれば、多忙なケアラー当事者がわずかな時間を見つけて参加できるというメリットもあります。
ダブルケアラーは身近にいる
さて、先ほど、「想定している」と書いたのですが、これは呼吸チームのDC caféに参加してくださったケアラー当事者が、まだひとりのみだからなのです。うれしいことにその方は、2回連続で呼吸チームのDC caféに参加してくださいましたが、もっと他にも支援を必要としている人がいると思います。
ある日、知り合いの酸素ボンベ業者さんに、「呼吸ケアが必要な患者さんを家族に持つダブルケアラー」支援についての話をすると、「ダブルケアってなんですか?」という言葉が返ってきました。説明したあとも、なかなか、「育児と介護の両方を同時に担う」ということがピンとこない様子でした。育児というと、乳幼児だけを連想し、介護というと寝たきりや、何らかの身体的な介助が必要というケースだけを連想しているようでした。
「ダブルケア」について、まだまだ聞き慣れない方も多い気がします。ここで、呼吸チームが支援を対象としているケアラーさんについて、事例を通して具体的に説明してみます。
今日子さん(仮名)は40代で、夫、小学生(2年生、6年生)との4人暮らしです。週に3日パートで仕事をしています。夫は仕事が多忙で、平日は家事や育児を今日子さんが担っています。小6の子どもは、週に2回塾に行き始めました。暗い道を通るので、帰りはお迎えに行っています。塾が終わるのは20時です。夫が帰宅していない場合は、小2の子どもを連れてお迎えに行きます。
今日子さん家族の自宅から車で10分程度離れたところに、実父(70代)が住んでいます。実母は数年前に他界し、実父はひとり暮らしです。実父は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)のため在宅酸素療法(HOT)をしていますが、日常生活動作はひとりで行うことができています。今日子さんは必要以上に干渉しないようにはしていますが、週に何日かはおかずを多めにつくり子どもたちと一緒に届けに行き、実父の体調を確認しています。またCOPDの実父にとって、風邪などの感染症は命取りになりますので、今日子さんはもちろんですが、夫、子どもたちも風邪をひかないように注意して生活しています。
ある日、夫は仕事へ行き、子どもたちが学校へ行く支度をしていると実父から電話がきました。いつもはひとりでバスに乗って受診している実父ですが、この日は車で送って欲しいと頼まれました。なんだか息も苦しそうです。今日子さんは、子どもたちに、実父の病院へついて行くことや、入院になると帰宅が遅くなるかもしれないことを伝えて、学校へ送り出しました。その後、実父の病院に付き添いました。幸いにも入院には至らず、帰宅することができました。
これって、身近にありそうな話だと思いませんか? えっこれが介護なの? ダブルケアなの? と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
世話だけではなく、気にかけることもケアの局面
介護というと、多くの方は、身体的な介護を連想するかもしれません。しかし、日常生活の中での、「ちょっとこれ買ってきて」や「あそこに行くからついてきて」なども、筆者らは介護に含まれると考えます。
経済学者のヒメルヴァイト(Himmelweit S)は、ケア労働には2つの局面があると論じています。ひとつは、世話をすること(caring for)、そしてもうひとつは、気にかけること(caring about)です。身体的な世話をするわけではないけれども危険がないか気を配ったり、そばにいて時間を過ごすことも、ケア労働に含まれるということです1)。先ほどの事例でいうと、今日子さんは、実父の身体的なケアをすることはありませんが、おかずを届けることや、実父の体調を悪化させないように今日子さん家族の健康にも気を遣って生活しています。そして子育てもしています。まさに、今日子さんはダブルケアラーです。
とくに、呼吸ケアが必要な患者の家族(私たちDC NETWORK呼吸チームの支援対象者)は、日ごろから、患者に息苦しさはないか、機器の使用方法が誤っていないかなど、「気にかける」ことを行っていると思います。また、先ほどの事例以外にも、呼吸器疾患の配偶者と子どもの面倒をみている人もいるかもしれません。身体的なケアをしていないと、それがケアであると認識しづらく、知らず知らずのうちに担っている人もいるように思います。
私も、先ほどの酸素ボンベ業者さんとお話ししているときに、「そういえば、あの人はダブルケアラーだ」と思い起こすことがありました。育児や家族を気にかけることは、日常的に行ってしまっているため、本人も当事者ということを意識せずに過ごしているように思いますし、周囲の人たちも、家族の面倒をみることを当たり前のように感じているのではないでしょうか。「ダブルケア」という言葉を普及させていくことで、ケアラー当事者への支援も広げていくことができると思います。
読者のみなさまも、臨床や教育における実践の中で、ダブルケアラーに関する支援を意識してくださるとありがたく思います。
1)相馬直子・山下順子:ひとりでやらない育児・介護のダブルケア, ポプラ新書, 2020

_1678352052803.png)
_1679454042387.png)
_1678352053026.png)
_1678352053026.png)