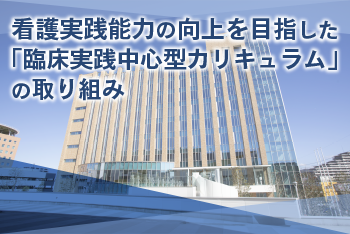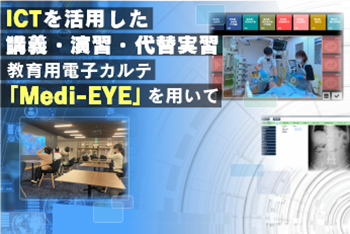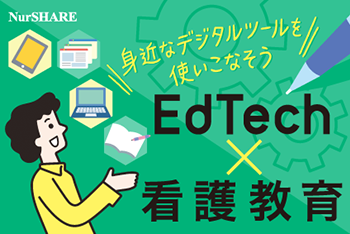はじめに
前編では「Adobe Premiere Pro」を使って、動画コンテンツのシーケンスを作成し、素材を入れるまでの具体的な方法を紹介した。後編では「Adobe Premiere Pro」の動画編集の具体的なテクニックと、YouTubeでの配信方法について紹介する。ぜひこれから説明する内容を参考にして、動画の編集スキルと配信方法について身につけていただきたい。
「Adobe Premiere Pro」動画編集テクニックの5つのポイント
動画をより魅力的なコンテンツに仕上げるためには、編集テクニックとして下記5つのポイントを押さえておくと、より視聴者を引きつける動画に仕上げることができる。
「Adobe Premiere Pro」動画編集テクニックの5つのポイント
ポイント1 動画の色調・明るさ調整
ポイント2 トランジションの使い方
ポイント3 音楽・音声の編集
ポイント4 字幕やテロップの付け方
ポイント5 動画の書き出しの仕方
前編で解説した動画コンテンツのシーケンスを土台に、ポイント1~4に沿って動画の細部や雰囲気を作りこんでいく。またポイント5(動画の書き出しの仕方)は、でき上がった動画がより鮮明に・美しく表現されるように、書き出し形式を確認し、必要に合わせて設定を変更するものである。撮影した素材や土台を確認しながら、想定するコンセプトから外れることのないよう動画編集を進めていこう。
「Adobe Premiere Pro」ポイント1 動画の色調・明るさ調整
撮影した動画を「全体的に暗いため明るくしたい」や「おしゃれにセピアやモノクロに色調を変えたい」といったように、編集作業を行っていると動画の色調や明るさの補正を行うことが多くある。
そこで、「Adobe Premiere Pro」で色調等を調整する方法として、初心者でも簡単にできる「Lumetri(ルメトリ)カラー」という機能について説明する。
「Lumetriカラー」とは?
「Lumetriカラー」とは、素材のカラーを調整するツールである。色調補正や明るさ調整を行う際に必須の機能であり、下記の6つの項目に分類されている。これらの機能をそれぞれ組み合わせて作業する。
「Lumetriカラー」の6つの機能
1.基本補正
明るさや色調を補正する基本の機能
2.クリエイティブ
フィルターをかけるイメージで全体のカラー調整を行える
3.カーブ
色の3要素(光の3原色)である「RGB」をR(レッド)・G(グリーン)・B(ブルー)の各カーブを利用して色調補正できる
4.カラーホイールとカラーマッチ
複数の素材の色調をうまく馴染ませることができる
5.HSLセカンダリ
フレーム全体ではなく、指定した特定の色だけをカラー補正するときに使用する
6.ビネット
フレーム周辺のサイズ・形・明るさなどを調整できる
「Lumetriカラーパネル」を表示する
①「ウィンドウ」をクリックして開く
②「Lumetriカラー」をクリックする
③「Lumetriカラーパネル」が表示される
.png)
「Lumetriカラーエフェクト」を追加するには?
カラーを調整したいクリップを選択し「Lumetriカラーパネル」のパラメーターを変更すると「Lumetriカラーエフェクト」が適用される。
カラーを調整したい「クリップ」をクリックして選択する
.png)
今回は、動画の色調・明るさ調整の基本操作として、「Lumetriカラー」の「1.基本補正」と「2.クリエイティブ」の機能を紹介する。
「Adobe Premiere Pro」ポイント1(動画の色調・明るさ調整)-1 基本補正
「カラー」には色温度・色かぶり補正、彩度、など主に色調補正に関する機能がまとめられている。また、「ライト」には露光量、コントラスト、ハイライト、シャドウ、白・黒レベルなど明るさに関する機能がまとめられている。
基本補正では色調補正を行う際に重要なパラメーターがまとめられており、調整時は自動で選択しているクリップにタイムリーに反映されるため、実際の色調・明るさを確認しながら編集することができる。基本補正で色調を調整することで、各場面に合った(春夏秋冬の季節感や早朝・夕方の時間帯など)演出が可能となるだろう。
①「基本補正」をクリックしてパラメーターを開く
.png)
②「基本補正」のパラメーターが開いたら、「カラー」や「ライト」を編集することができる
③各パラメーターのスライダーを、右・左にマウスの左クリックを長押ししながら動かすと色調を補正できる
_1668041211669.png)
「Adobe Premiere Pro」色調補正の各パラメーターについて
色調補正を行う「基本補正」の項目には、大きく分けると「ホワイトバランス」「トーン」「彩度」の3つがある。それぞれの詳細について紹介しよう。
1.ホワイトバランス
「ホワイトバランス」は、白を基準に素材シーンの色補正を行うことができる機能で、(1)WBセレクター、(2)色温度、(3)色かぶり補正、の3つからなる。
(1) WBセレクター
「WBセレクター」では、スポイトマークをクリックし、プログラムパネル内の白い部分を選択することで、基準となる白い部分を選択することができる。
①スポイトマークをクリックする
②カーソルがスポイトマークに変わったら、基準となる白い部分をクリックする
③自動で「色温度」と「色かぶり補正」が調整される
.png)
基準となる白い部分を選択すると、選んだ部分を「白」と判断して自動的に他の部分の色補正を行う。
(2) 色温度
「色温度」は、素材シーンを温かく見せるか、冷たく見せるかを決めるための機能である。補正の方法は「“+”に調整するとオレンジ(暖色)系」「“-”に調整するとブルー(寒色)系」に調整できる。
(3) 色かぶり補正
「色かぶり補正」は、変色している白色部分を補正することができる機能である。補正の方法は「“+”に調整するとマゼンタ(紫)系」「“-”に調整するとグリーン系」に調整できる。
2.トーン
「トーン」とは、素材シーンの明るさを調整して色補正する機能で、(1)露光量、(2)コントラスト、(3)ハイライト、(4)シャドウ、(5)白レベル、(6)黒レベル、の6つからなる。
(1) 露光量
「露光量」は、光の量を調整するための機能である。補正の方法は「“+”に調整すると光の量が多くなり明るく」「“-”に調整すると光の量が少なくなり暗く」調整できる。
(2) コントラスト
「コントラスト」は、明るさのギャップを調整するための機能である。補正の方法は「“+”に調整すると明るさのギャップが大きくなりメリハリがつく」「“-”に調整すると明るさのギャップが小さくなりメリハリがなくなる」よう調整できる。
(3) ハイライト
「ハイライト」は、明るい部分のみを調整するための機能である。補正の方法は、「“+”に調整すると明るい部分がさらに明るく」「“-”に調整すると明るい部分が暗く」調整できる。
(4) シャドウ
「シャドウ」は、暗い部分のみを調整するための機能である。補正の方法は、「“+”に調整すると暗い部分が明るく」「“-”に調整すると暗い部分がさらに暗く」調整できる。
(5) 白レベル
「白レベル」は、白色部分のみを調整するための機能である。補正の方法は、「“+”に調整すると白色部分が明るく」「“-”に調整すると白色部分が暗く」調整できる。
(6) 黒レベル
「黒レベル」は、黒色部分のみを調整するための機能である。補正の方法は、「“+”に調整すると黒色部分が明るく」「“-”に調整すると黒色部分が暗く」調整できる。
3.彩 度
動画を色鮮やかにするための機能である。たとえば、空や海を撮影した動画であれば、彩度を上げることで青が強調され、全体的に美しく仕上げることが可能となる。 補正の方法は「“+”に調整すると鮮やかさのギャップ が大きくなりより鮮やかになる」「“-”に調整すると鮮やかさのギャップが小さくなりくすみが強くなる」よう調整できる。
「Adobe Premiere Pro」ポイント1(動画の色調・明るさ調整)-2 クリエイティブ
「クリエイティブ」では、既存のプリセットを適用して、色調・明るさを調整することができる。また「Look」からプリセットを適用すると、まるで映画のワンシーンのような色合いやヴィンテージな雰囲気のモノクロ調などに調整することができる。
①「Look」をクリックしプリセットを開く
.png)
②プリセットが開いたら、好みのプリセットをクリックして適用する
.png)
③選択したプリセットが左のクリップにタイムリーに反映される
.png)
パネルの下部では、「Look」を適用する強さを変更したり、その他「フェード」や「彩度」などの調整を行ったりすることもできる。
“微妙な色調”を指定するには?
たとえば「シャドウ部の色合いを青っぽく」や「ハイライト部の色合いを赤っぽく」といった“微妙な色調“にも調整することができ、イメージに合った“雰囲気のある動画”に仕上げることができる。試してみよう。
シャドウやハイライトの色相補正を「+」をカーソルで動かすことで調整できる
.png)
「Adobe Premiere Pro」ポイント2 トランジションの使い方
「トランジション」とは、メディア(動画や画像など)間に、アニメーションリンクを作成するために追加される「エフェクト」のことである。たとえばシーン中の、あるショットから次のショットに移動する場面に、ショットとショットとの境目がわからないような仕様でつなげたり、複数のショットを徐々に重ねながらつなげたりすることができる機能をさす。
「Adobe Premiere Pro」トランジションの挿入方法
「エフェクト」ウィンドウ内の「ビデオトランジション」を開く。
①「ウィンドウ」をクリックして開く
②「エフェクト」をクリックする
_1667523915503.png)
③「エフェクトパネル」を開く
.png)
④「ビデオトランジション」を開く。このあと用いたいエフェクトを選ぶ。ここでは「クロスディゾルブ」という「エフェクト」を選ぶことにする
⑤「ディゾルブ」を開き「クロスディゾルブ」を選択する
.png)
⑥「クロスディゾルブ」を、トランジションを適用させたいクリップとクリップの切れ目にドラッグ&ドロップして配置する
.png)
「クロスディゾルブ」が反映されたかどうかはプレビュー画面上で確認できる。
「トランジション」の種類はほかにもいろいろあるが、筆者のオススメは「クロスディゾルブ」である。前の動画が暗転すると同時に次の動画が浮かびあがり、自然に場面転換することができる。
「トランジション」は、場所から場所への移動の間や、季節の移り変わりなどを表現したりする一種の演出手段といえる。すべての動画の間に入れてしまっては、演出としての意味が薄れ、観ている側にも意図が伝わりづらくなるため、「トランジション」は頻繁には使わず、限られた場面で明確な理由をもって使うようにしよう。
「Adobe Premiere Pro」ポイント3 音楽・音声の編集
前編で音楽(BGM)の挿入方法について説明した。ここではBGMの編集として、①クリップの長さの調節、②フェードイン/フェードアウト、③音量の調整方法、について説明する。
クリップの長さの調節
プロジェクトに読み込んだ音楽ファイルをドラッグ&ドロップで、画面下のタイムライン「A2」のラインに挿入する。いらない部分は動画ファイルと同じ方法で短く編集し、動画ファイルの長さと合わせる。
①クリップを短く切るには「レーザー」ツールを使う。「レーザー」ツールをクリックし有効にする
②動画クリップの長さに合わせ「レーザー」ツールで切断する
_1668041292985.png)
③不要なクリップを左クリックして選択し「delete」を押して削除する
.png)
フェードイン/フェードアウト
音楽ファイルの最後を短く編集したため、再生すると最後に唐突に「ブツっ」と音が切れてしまう。そうならないために、フェードアウト効果をつけて音を滑らかに終わらせるひと手間をかけてみよう。
タイムラインの高さを広げ「キーフレーム編集ツール」を出す。「キーフレーム編集ツール」では「キーフレーム」(タイムライン上にあるポイントをマークしたもの。たとえば2点のポイント間の音声ボリュームを調整する機能がある)の追加・削除が可能となる。「キーフレーム編集ツール」をクリックしてBGM音楽の最後の付近で真ん中のラインを左クリックし「キーフレーム」を追加する。
①「キーフレーム編集」ツールをクリックする
②「クリップ」の再生位置を示す青いバーを「キーフレーム」の追加をしたい位置にずらす
③青いバーと音量のボリュームを表す黒いバーの交差する箇所を見つける。この交差する点をクリックすると青い点が表示される。これが「キーフレーム」である
.png)
④「キーフレーム」は始まりと終わりの2点で打つ必要があるため、③と同様の方法で2点目の「キーフレーム」を打つ
⑤2点目の「キーフレーム」にカーソルを当てて左クリックを長押ししながら底辺の位置に置く
.png)
⑥BGM音楽の最後に音が少しずつ小さくなるフェードアウトが適用される
.png)
音量の調整方法
「オーディオトラックミキサー」で音量を調整する方法について説明する。
「オーディオトラックミキサーウィンドウ」を表示させるために、「ウィンドウ」から「オーディオトラックミキサー」をクリックする。
①前項の要領で、BGM音楽の最後に音が少しずつ小さくなるフェードアウトを適用する
②「オーディオトラックミキサー」をクリックする
.png)
③「オーディオトラックミキサー」が開く
.png)
それでは次に、タイムライン「A1」の動画ファイルの音声を消して、BGM音楽のみが聞こえるようにしてみよう。
④いちばん左の「A1」のつまみボタンをいちばん下に下げる
⑤赤くなった場合は音量を少し下げる
⑥全体の音量を一括で調整できる「ミックス」も使おう
.png)
音量が大きすぎると音が割れる
音量を大きくしすぎると音が割れて聞こえることがある。その場合、ミキサーではその音源が真っ赤に表現される。もし赤くなった場合は音量を少し下げよう。
オーディオトラックミキサーのいちばん右に「ミックス」がある。この「ミックス」のつまみを調整すると、このシーケンス全体の音量を一括で調整することができる。
「Adobe Premiere Pro」ポイント4 字幕やテロップの付け方
「Adobe Premiere Pro」には自動文字起こし機能が搭載されている。作業が大幅に効率化されるため、ぜひ使ってみよう。
自動文字起こし機能の使い方について
「Adobe Premiere Pro」の自動文字起こし機能の使い方は簡単である。テキストパネルを表示して「文字起こし開始」を押すだけでAIが自動で字幕を挿入してくれる。
オーディオを含んだシーケンスを選択する
オーディオを含んだ音声またはビデオシーケンスを選択した状態で作業を行う。
ウィンドウメニューから「テキスト」を選択する
自動文字起こしはテキストパネルにて行う。メニューバーにある「ウィンドウ」を選択し、
その中の「テキスト」を選択してテキストパネルを表示する。
①「ウィンドウ」をクリックして開く
②「テキスト」をクリックする
.png)
③「文字起こし」タブをクリックする
④「シーケンスから文字起こし」をクリックする
.png)
⑤「文字起こし」のオプションを設定する
⑥言語は「日本語」に設定し、オーディオ分析は「トラック上のオーディオ」を設定する
⑦複数の話者が話している場合は「様々な話者が話しているときに認識する」にチェックを入れる
⑧「文字起こし開始」をクリックする
.png)
自動文字起こしのあとは、必要に応じて文章を修正する(たとえば文字変換の誤字脱字を修正する)。
キャプションの作成
テキストの修正が終わったら「キャプションの作成」を押して一括でキャプション化を行う。この際、キャプションの「プリセット」「形式」「文字の最大長さ」など細かなスタイルを指定することができる。
⑨「キャプションの作成」をクリックする
.png)
⑩キャプション化を行うとタイムラインに合わせてキャプションが挿入される。タイミングも音声に合わせてくれる
.png)
自動文字起こしで作成したキャプションはあとから変更したり、フォントやサイズを変更したりすることができる。場面に合わせて変更してみよう。
「Adobe Premiere Pro」ポイント5 動画の書き出しの仕方
最後に、動画の書き出し方法を説明する。書き出しを終えて初めて編集作業が完了する。早速、書き出しの仕方をみてみよう。
①「書き出し」のタブをクリックする
.png)
②「ファイル名」をわかりやすいものに編集する
③クリックして「保存場所」を指定する
④保存場所が決まったら「保存」をクリックする
.png)
⑤「保存形式」は「形式」から選択できる
.png)
⑥書き出し範囲は「ワークエリア」を選択することで、作成した動画の「最初から最後まで」の全体を書き出すことができる
⑦設定が完了したら「書き出し」をクリックする
.png)
書き出し形式いろいろ
TwitterやInstagram、YouTubeに投稿するための動画なら、形式はMP4を勧める。書き出し形式を「H.264」にすることで、MP4での書き出しができる。
動画の素材には、写真やアニメーションを作成して取り込んだもの、iPhoneで撮影したもの、さらにカメラで撮影したものなどさまざまあるが、素材によって適した書き出し形式が異なることがある。
動画は、複数の素材を組み合わせて作成するのが一般的であり、書き出し時に、すべての素材を統一した書き出し形式にて行われることになるが、書き出し形式が素材と合っていないときには、書き出し後の動画がぼやけて見えたり、「かくかく」していたりといった事象が起こりうる。
たいていは「H.264」を選択することで解決するが、場合によっては「MPEG4」を選択して解決することもある。書き出し後の動画に問題がある場合は、いろいろな書き出し形式を試してみるとよいだろう。
「Adobe Premiere Pro」で作った動画を配信してみよう
動画が無事に完成した後は、①動画をYouTubeに配信する方法、②配信動画の周知に役立つQRコードの作成方法、についてみてみよう。
「Adobe Premiere Pro」ポイント6 YouTubeでの配信方法
YouTubeのアップロードには容量制限と時間制限があり、128GB以内かつ12時間以内である。どちらかでも制限範囲を超えてしまうと投稿できなくなるため注意が必要である。たとえば、128GBの動画は、フルHDだと一般的に約20時間前後のアップロード時間を要する(なお解像度によって異なる)。長時間の動画や4K動画を投稿する場合には、制限範囲を超えないかチェックしよう。
①「動画をアップロードする」アイコンをクリックする
.png)
②アップロードするファイルを直接ドラッグ&ドロップをするか、「ファイルを選択」を選択する
.png)
③タイトルを設定する
④説明を入力する
.png)
⑤動画の内容に合わせて「子ども向け」かどうか選択する
⑥「次へ」をクリックする
.png)
⑦また「次へ」をクリックする
.png)
⑧さらに「次へ」をクリックする
.png)
⑨動画の公開設定をする
.png)
動画の公開範囲を設定しよう
動画の公開設定は、下記のように公開範囲を考えて行う。
「公開」とは?
「公開」に設定した動画は誰でも閲覧可能となる。「公開」に設定した動画は自分のチャンネルに表示され、YouTubeの検索結果にも表示される。
「限定公開」とは?
「限定公開」に設定した動画は動画のURLを知っていれば閲覧可能となる。チャンネルには表示されないため、一般のユーザーはチャンネルを見ても動画があるのかどうかを知ることができない。動画のURLを知っているユーザーが他のユーザーにURLを教えれば、教えられたユーザーも動画を閲覧することが可能となる。他のユーザーによって動画が公開再生リストに追加されないかぎり、YouTubeの検索結果には表示されることはない。
「非公開」とは?
「非公開」に設定した動画は、自分と許可したユーザーしか閲覧することができない。チャンネルにも表示されず、またYouTubeの検索結果にも表示されることはない。
「Adobe Premiere Pro」ポイント7 QRコードの作成方法
最後にYouTubeで配信した公開設定動画、限定公開設定動画(非公開設定動画についてはURLからアクセスできない)のQRコードを作成し周知する方法について紹介しよう。YouTubeに限らずGoogle検索から開いたページは、以下の方法で簡単にQRコードを作成することができる。
①動画リンクをコピーして検索窓に貼り付けて検索するか、動画リンクをクリックしてアップロードされた動画を開く
.png)
②YouTubeのページ上(動画上ではなく余白上)で右クリックする
③「このページのQRコードを作成」をクリックする
④QRコードが作成できたら「ダウンロード」をクリックする
.png)
ダウンロードしたQRコードはパソコンのダウンロードフォルダに収納されている。周知用のポスターや配布資料等に貼り付けて使用することができる。
おわりに
エピソード11「映像編集の達人になる! Adobe Premiere Proで本格的な動画教材を作成する方法」(後編)は、本格的な動画編集のテクニックから動画配信までを一挙に紹介した。後編はとくに盛りだくさんな内容となったが、前編・後編を通して紹介した内容は「Adobe Premiere Pro」以外の動画編集ソフトを使用する際にも活用できる知識である。
広報用動画や教育用動画の作成に取り組む際には、何かしらの動画編集ツールを用いてクォリティーの高い動画制作にチャレンジしてみてはいかがであろうか。