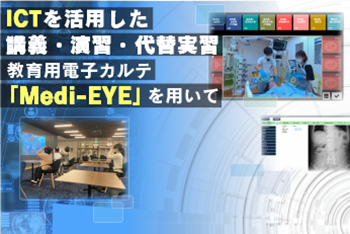ミッションタウンって何?
ミッションタウン*とは、看護の対象が住むデジタル仮想の町である。小児から高齢者まで、全領域の対象となりうる仮想の住民が、在宅、病院、施設などに分かれて生活をしている。住民それぞれにキャラクターがあり、高齢者であれば幼少期からの人生年表(ライフヒストリー)や糖尿病など疾病の発症時期、家族構成などが細かく設定されている。
学生はパソコンやスマートフォンを操作しながら、それぞれのアバターとなって町に住む患者のもとをケアして回る。まるでロールプレイングゲームのように、患者に対して行うべきケアを与えられた選択肢のなかから選び、受け持ちの患者さんにいかに適切なケアを提供できるかをあれこれ考える。遊びとの境目があいまいともいえるが、むしろそのために、学生が高い動機をもって取り組めるシミュレーション教育の環境を実現することができている。

*ミッションタウンってどんな町?
ミッションタウンは、人口約6万人のA市の中央に位置する町。タウン内にはJRの駅があり、県内最大の政令市に電車で約20分という利便性から、朝夕は多くの通勤・通学の利用者がいる。駅周辺には、交番や銀行、スーパー、飲食店があり、その周辺には、一戸建てや集合住宅が立ち並んでおり、 市役所・保健センター、病院・診療所、薬局、看護大学、高校・中学校・小学校、幼稚園、保育所、工場や会社、 教会などもある。ミッションタウンの高齢化率は22%。健康診断の結果において、メタボリックシンドロームが年々増えてきている。(福岡女学院看護大学HPより引用)
*ミッションタウンの主人公は?
はじめまして!私の名前は徳永あい、看護大学の2年生です。私は、隣の市から看護大学に通っていて、現在は、父・母・弟の4人で生活しています。看護大学に入学して、とにかく毎日楽しく過ごしています。私が通っている看護大学では、キリスト教の精神に基づいた教育、 そしてシミュレーション教育、多言語医療に関する教育が行われています。1年生のときからボランティアサークルに所属していて、メンバーと一緒にミッションタウン内の 住人を対象とした健康測定会や健康教育に取り組んでいます。
最近、大学での海外短期留学にも参加したくて、駅前のパン屋さんでアルバイトも始めました。忙しい毎日だけど、ときどき仲良しのまいちゃん・ゆいちゃんとショッピングや映画を見に行ったりして、気分転換をしています。これから、ミッションタウンの住人の生活や健康をチェックしながら、看護を学んでいきます!(福岡女学院看護大学HPより引用)

レポートを提出すると“お得なポイント”がもらえる?
さらに学習の動機づけの工夫として、レポート提出ごとに、学生は相当の“ポイント”を受け取ることができる。“ポイント”はミッションタウン内で通用する仮想の“お金”である。学生は“お金”を使ってアバターを着飾る洋服やユニフォームを購入したり、聴診器を購入したりすることができる。聴診器も実習で使うものがあったり、希少価値のある“伝説の聴診器”があったりと、教員が楽しみながら作りこんだことも功を奏し、楽しさが学生に伝わって、学習に取り組む姿勢はより熱心なものへと変化している。
ミッションタウンは学年や領域の壁を越える
学生は大学4年間を通し、各領域共通で同一のミッションタウンに住む住民で授業や演習、シミュレーション学習を行う。学生のアカウントには4年間の履歴——つまり課題の進捗状況や提出したレポート実績が積み上がっていくが、各提出物には評価が加えられているため、自分の学習の軌跡と成長(評価の向上)を見渡すことができるしくみとなっている。また1年生であっても4年生がミッションタウンでどのような取り組みを行っているかをのぞき見ることができ、学年の壁を超えて学習の幅を広げられるのもミッションタウンの魅力である。先輩のハイレベルな取り組みに刺激を受け、憧れの気持ちも交えながら、近い将来、自分がどのような学習を行い、どのように成長するかをおおまかに見通せるというわけだ。
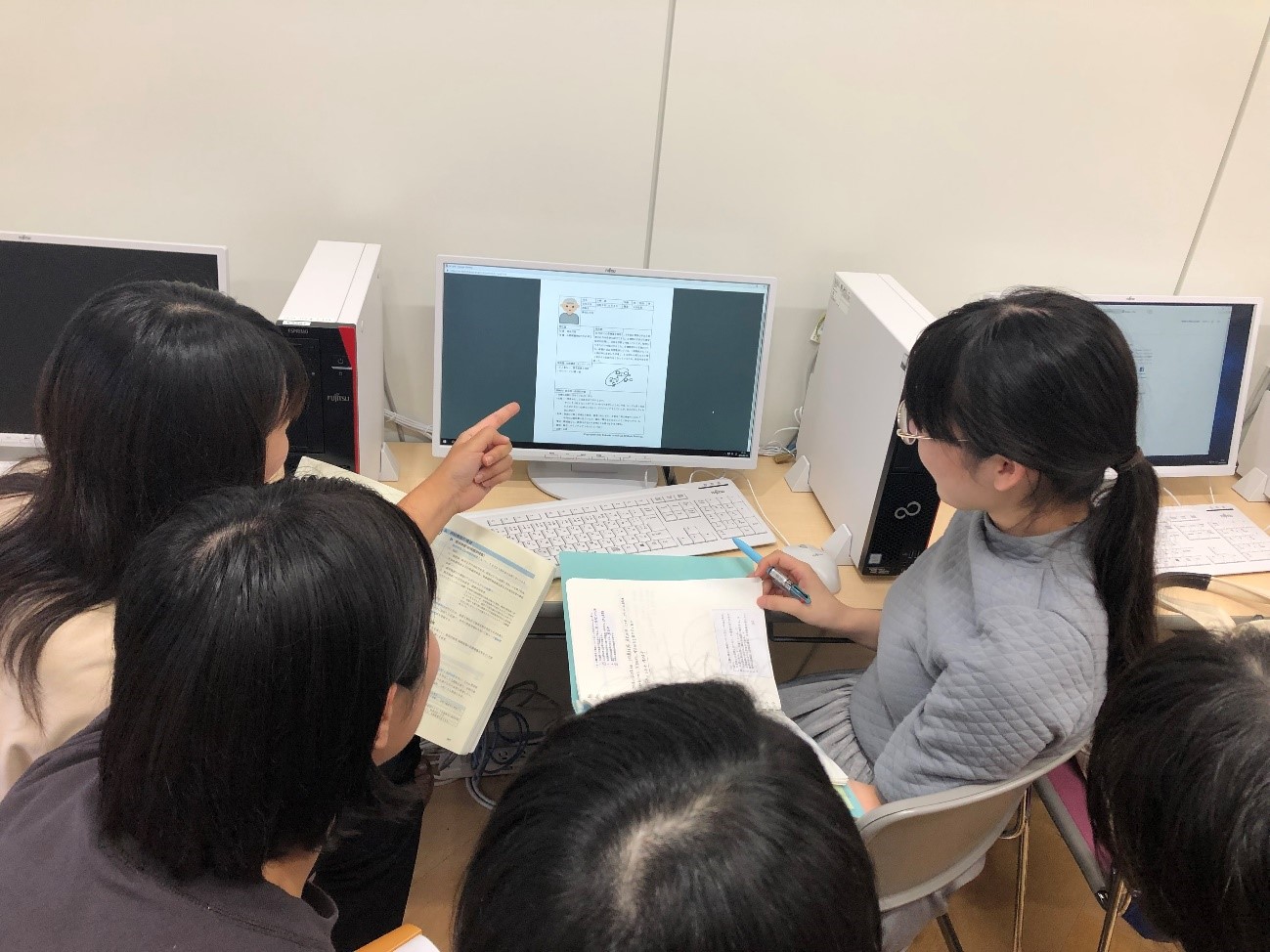
うれしい成果とおもわぬ成果
ミッションタウンの取り組みにより、学生の動機づけを高め看護の力につながる多くの成果を得ることができたが、学外でも多くの評価をいただくことができた。たとえば学会などで発表するといつもたくさんの問合せを受けたし(皆さま,ありがとうございます)、2019年には日本Eラーニング大賞 厚生労働大臣賞を受賞することもできた(記念に書籍も刊行しました。よろしければ皆さん手にとっていただけると嬉しいです。☞参考文献1)。
ただ成果はそれだけではない。思わぬ副次的な効果として、教員らにとっても分野・領域を超えたコミュニケーションの機会を与えてくれたのである。ミッションタウンという領域横断の場をつくるというのは、当然領域間の相互理解なくして達成できない課題である。このプロセスのなかで他領域の教員と膝を突き合わせて「ああでもない、こうでもない」と議論しながら交流したことは結果としてとても有意義な時間であり、それぞれの専門領域のこだわりを知るとともに、他の領域で教授している教育内容を理解することができた。ミッションタウンをつくるという課題だけでなく、それ以外も含めた教育現場全般によい影響を与えていると実感できる。
まずは小さく始めてみよう―大きく育たなくても意味がある
ここまで読んでいただいた教員の皆様のなかには、とてもじゃないけどうちの学校ではまねできない、と思われた方がいらっしゃるかもしれない。しかし、私自身もミッションタウンがここまで規模・質ともに発展するとは思っていなかった。
開発から5年間のプロセスは、「領域の垣根を超えてまずは1事例を皆で共有しよう」というささやかな課題解決のためにはじまったのである。それをきっかけに教員たちの間で「さらにこんな事例があるといいね」「町の雰囲気はもっとこういう風にしよう」「Web教材にしてこんな機能を加えるといいね」と構想を語りながら、そのなかから少しずつ機能を実現させて、段階的に発展してきたのである。
気づけば規模も大きくなりまたデジタル機能を備えるに至ったが、あくまで始まりは小さく、「領域を超えてシミュレーションの事例を共有できれば、学生の思考も点ではなく線としてつながっていくのでは?」という発想をきっかけに,まずは小さな行動を起こしたにすぎない。
次回少しくわしくミッションタウン発展の歴史(プロセス)を紹介するが、われわれがたどったICT化の過程だけでなく、その根っこにある“共有とつながりの過程”のなかにも,看護教員の皆さまがそれぞれの看護教育の現場で発展させうるヒントがあると信じている。
1) 片野光男編:福岡女学院看護大学が開発した「第四の看護教材」ミッションタウンへようこそ,クオリティケア,2020
2) 藤野ユリ子ほか:領域をこえて活用できるシミュレーションシナリオづくり「ミッションタウン」プロジェクト.看護教育58(10):822-828,2017
3) 藤野ユリ子:学内全領域をつなぐミッションタウンと,地域にひらかれたシミュレーション教育センター.看護教育60(8):656-664,2019
4) 福岡女学院看護大学:ミッションタウンへようこそ.https://m-town.fukujo.ac.jp/guest/description,アクセス日:2021年12月14日


_1640752719189.png)