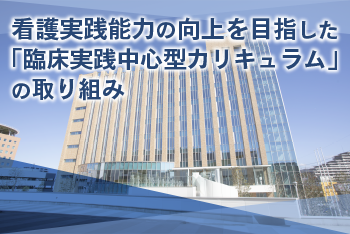現代の若者は、生まれたときからスマートフォンが存在する環境で過ごしています。看護師養成所においても、ほとんどの学生が使っているのではないでしょうか。私の子どもたちには、共働きであったこともあり、小学生の低学年からキッズ携帯を持たせていました。緊急時の連絡が取れるように、またどこで遊んでいるかわかるようにと考えてのことです。
子どもが中学生になったときには、わが家にもスマホがやってきました。子どもたちが勝手に触るので、よく怒っていました。しかし、それ以前からわが家にはパソコンがあり、子どもたちはインターネットとはすでに触れ合っていたため、スマホには私より早く馴染んでいました。このような背景をお持ちのご家庭は多いのではないでしょうか。
情報モラルや倫理観が未熟な学生とどうかかわるか
みなさまも感じられているように、スマホの急速な広まりによって危惧されているのは、情報モラルが未熟な学生が多いということです。情報モラルに限らず、倫理観が未熟な学生も時折見受けられます。電子カルテを撮影する、実習記録を撮影する、授業の動画を撮影するなど、枚挙にいとまがありません。悲しい現状ではありますが、彼らとかかわったからには、私たちには育てる責任があります。
教育に携わる先生方は、さまざまな工夫をされていることと思います。例として「実習科目のガイダンス時、過去に起こったスマホに関するトラブルの事例を紹介し、根拠を示してどうすべきかを説明する」「禁止行為を行ったら減点する」「課題作成時の生成AIの使用禁止を明示する」など、多様な取り組みがあると思いますし、教員間でもよい取り組みは共有したいと思います。しかし、望ましくない行為はたくさん起こっており、教員が対応しきれなくなっているという側面もあります。
今、私が学生とのかかわりの中で行っていることは、「彼らがやろうとしていることの影響を予測する」ということです。予測した結果、倫理的に問題ない、よい結果が得られそう、と思われる場合は学生にやらせてみるのです。これは、看護の場面で、看護師の思考として常にあるものではないでしょうか。患者さんにこれをこのように実践していいのか、実践したら患者さんにどんな影響があるのか、という思考です。
このような考えに至ったのは、私がシミュレーション教育をよく用いているからです。私は、シミュレーション課題を経過を追うように設定します。また、授業にはタブレットやPCの持ち込みを許可しており、デブリーフィング時にはインターネットで検索しながら話し合わせています。すると、「これからどうなる」とか「こうすればこれがわかる」などと、これまでの経過からわかったこと、検索して得た情報などを交えて話し合いながら、デブリーフィングが深まっていくのです。このことは、学生が検索した知識を使って考え、判断できているからだと思っています。
「影響を予測する」という考え方を育てることを中心におき、学生にも同様にさせてみると、情報社会の中での生き方も育てられ、同時に看護師の臨床判断能力も育成できるのではないかと考えます。
情報活用能力が養われている「スマホ世代」
スマホの問題点がクローズアップされやすい面はありますが、20歳前半の自分の子どもたちや学生たちを見ていると、スマホを使わない教育を考えることは不可能であり、無理があると思います。看護教育にどう使うかを考える必要があります。文部科学省はGIGAスクール構想を立ち上げ、第2期の「1人1台端末の整備・利活用」というフェーズに進んでいます。「少子高齢多死社会」だと頭でわかっていても、組織は「人」ありきで業務や教育を考えがちですが、教育現場の教員不足も深刻な今、私たちはデジタルなどを上手に使っていく必要に迫られています。しかし、デジタルなどが苦手な教育者も多く、改革は進んでいないのが現状です。
スマホ世代の若者を捉えてみると、インターネットを自由に使いこなすデジタルネイティブであり、SNSなどの情報源からリアルタイムで情報を得ています。これを情報の”検索”ではなく、情報の”つまみ食い”ととらえる方たちもおられると思いますが、まずは情報を得ようとする行動が大切だと思います。
また、若者は、メッセージアブリなどを使って上手にコミュニケーションをとっています。欲しいものがあるときは検索し、比較検討して購入します。衝動買いせず、吟味する傾向にあり、私自身買い物のときなどは子どもたちのこの能力を頼りにしています。スマホには依存や情報過多による影響、健康被害や情報モラルの問題もある一方で、生活の場で活用され、人々にとってなくてはならないものになっています。
学習指導要領にはこういった「情報活用能力」の育成が挙げられており、学習の基盤となる資質・能力と定義されています。情報を得て、整理・比較すること、得られた情報をわかりやすく発信・伝達すること、情報を保存・共有することを指導しているのです。これは、研究におけるプロセスクリティークと同じだなあと思いますし、私たちが日頃教育している課題解決学習(PBL教育)と同じだなあと思います。小学校では、PBLの実践として、課題を設定し、情報収集、整理・分析、まとめ・表現という授業の展開をされているようで、その報告をインターネットでいくつも検索できます。学生は、情報を収集し、比較・検討し、吟味することができますから、看護教育にもすぐに取り入れられそうです。苦手意識は誰しもありますし、私自身「この年になって新しいことを覚えるの?」という思いも無きにしも非ずです。まずは生成AIやさまざまなコンテンツを、周囲にSOSを発信しながら使ってみようと思います。
ITを駆使して看護職を育てる時代へ
すでに、スマホを学習ツールとして、e-learning、オンライン学習、学習記録の可視化、学習アプリなどで活用されている学校も多いと思います。しかし、小学校から情報活用能力を養う教育を受けている学生たちですから、それを基盤として私たち看護教育者が看護に必要な能力をどのように育成するかを考えねばならないと思います。そのために、看護教育の世界の者たちだけでなく、インターネットなどを駆使し、広い世界にアイデアや取り組み事例を求め、活用していきたいと考えています。そして、取り組み事例を組織の中で共有し、現代の教育に合った看護教育ができる柔軟な組織を目指したいと思います。

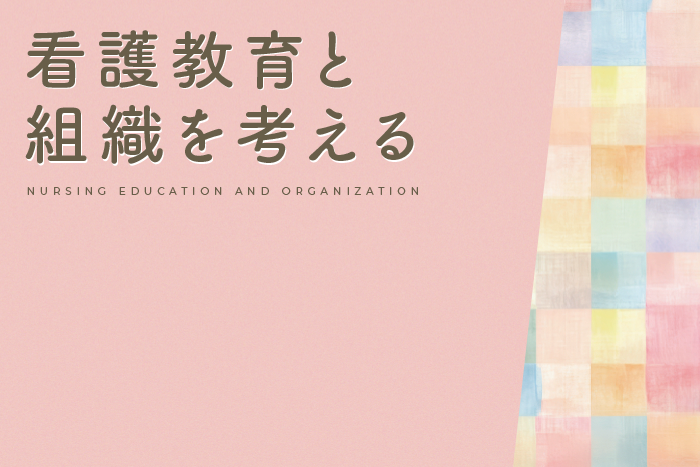

」サムネイル2(画像小)_1650874098963.png)