今回、南江堂さまより私のこれまでの看護教育に携わった経験を振り返る機会をいただくこととなりました。私のつたない経験をお伝えすることで、同じような経験をした方には「そうそう」と共感していただけるような場になればと考えています。また、悩んでいる方には少しでも勇気やヒントが得られるような場になればとの願いを持ち、連載させていただきます。お付き合いいただければ幸いです。
私が私らしく看護教員を続けていくために大事にしていることは、「解らないことを具体的に解らないと言うこと。そしてそれを知りたい、解りたいと伝えること」です。「解らない」と言うことは勇気が必要ですし、「解らない」は「知りたい」の同意語ではないのです。今回は、このように気付いた経緯についてお伝えします。
平均化した姿から、自分の「知りたい」の追求へ
看護教員になり30年以上経過しましたが、教員になったときは、ゼロからのスタートという気分でした。その時の私が反省すべきことは、それまでの経験を「捨てる」ような感覚を持ってしまったことです。看護師として、新人看護師の育成や実習指導を行い、患者のアセスメントには若干の自信を持っていました。それを「捨てる」感覚だったのです。
その理由は、着任した学校の風土でした。教員としての服装や態度を一から教えられ、上司である教務主任への報告ではたびたび叱責され、同僚の教員と気軽に話ができる環境ではなかったのです。「ここは看護の世界とは違う」と感じた自分は、当時の看護教員としての平均化した姿を求められていたのだと思います。
どの組織にも、組織風土や組織文化があり、その組織の平均化した姿があるのではないでしょうか。その当時の看護教員として平均化した人物像と、教員になったばかりの私自身の姿は乖離しており、教員として1年が過ぎたとき、自分らしくない別人のようになっていました。とても苦しかったことを記憶しています。
教員となり2年目を迎えるとき、教務主任が人事異動により替わりました。しばらくしてその教務主任から心理学の講師と授業の打ち合わせをするように言われ、講師の職場にうかがいました。講師は、カウンセラーでした。当時の私は、看護教育について解らないことがあるのに、周囲に聞いたりヒントを得たりすることができず、解決できないことにすごくフラストレーションを感じていました。講師は授業のことをきっかけに、そんな私の話を聞いてくださいました。そのようなことが3回あり、教務主任が私にカウンセリングを受けさせたのだと気づきました。
その後、教務主任から「何が解らないのか」と聞かれました。私は、看護診断や看護過程をどのように教えていいのか解らず困っていることを伝えました。そして、「解らないことをどうしたいのか」と聞かれ、「解りたいのだ」と具体的に伝えました。すると、教務主任は、さまざまな研修に私を連れていき、その分野で書籍を執筆している方を紹介してくださり、個別に教えを乞うことができました。私は、解らないことが解る経験をすることができ、色のついた世界が目の前に広がるような感覚でした。そして、看護師としての経験を「捨てる」感覚で捨て去ったものを「拾い」、統合・整理しました。その後私は、夜間は大学に通いながら教員を続けることとなりました。
このような経験から、学ぶことの楽しさを知り、人を育てる教員として「解らないことを具体的に解らないと言うこと。そしてそれを“知りたい、解りたい”と伝えること」を実践しながら教員を続けていくことになりました。そしてその道程に、たくさんの人との出会いがあったことは大切な要因です。
チェンジモンスターと改革者
1人目に出会った教務主任は、自分の価値観により形成された教員の姿を私に求めていたのでしょう。その教務主任は、組織変革の世界でいうところのチェンジモンスターだったのではないかと考えます。ジーニー・ダック氏は著書「チェンジモンスター―なぜ改革は挫折してしまうのか?」1)で、組織の変革を阻害するのには、そこに関与している人々の意識や感情といった心理的な要因があると書いています。「自分の世界に閉じこもって外部とかかわろうとしない」人や「内側からの評価ばかりに興味、関心を向け、外部には目を向けない」人、「できない理由ばかり述べて行動に移さない」人などが組織の変革を阻害するそうです。
2人目に出会った教務主任は、さまざまな人との交流を持ち、客観的データを示しながら話をする人で、独特の世界観を持ち、周囲の目を気にする人ではありませんでした。チェンジモンスターと真逆な人です。学ぶということに関しては、貪欲で厳しい人で、部下を育てることで組織を改革しようとしたのではないでしょうか。
この方は、レビンの変革モデルの、「3つの過程(解凍→変革→再凍結)」を推進することができるダイナミックな人物です。現状の均衡を破り、行動の変化を導くような支持的・教育的な環境を整えることを実践できる人物です。だからこそ、誰かの価値観に従った人物になることにストップをかけ、私の知りたいという欲求に支持的・教育的な環境を整え、私が学び・変容していく姿を組織内に示し、組織を変革していっていたのではないでしょうか。
実は、3度目の人事異動で、5年ぶりにこの方と同じ看護学校で勤務することになりました。その時もまた、私の知りたいという欲求から、研究指導をしていただける教授をご紹介いただき、論文を1本書き上げることができました。また、東京に1年間の研修に行かせてくださいました。相変わらず、支持的・教育的環境を整えてくださる人でした。私が管理職となってからは、この方のように部下の知りたい欲求に対してよい環境を整えることができるよう心がけています。
組織変革とこれからの社会を生き抜く鍵
現代の社会は、不安定で、不確実で、複雑です。また、少子高齢多死社会で、どの組織も人材不足です。そのような中では、柔軟な組織のあり方が、現代社会を生き抜いていく鍵となるのではないでしょうか。今回このような機会をいただき、自分の過去を振り返り、自分自身の考えや意識を捉えることとなりました。また、組織変革には、管理職がどのような意識を持っているか認識することが大事だと再確認する機会となりました。管理職である自分は、組織の均衡を破り、再生させることができる柔軟な存在でありたいと思います。
そしてこれからも、学ぶことの楽しさを知り、人を育てる教員として「解らないことを具体的に解らないと言えること。そしてそれを知りたい、解りたいと伝えること」を実践しながら教員を続けていきたいと思います。
1)ジーニー・ダック:チェンジモンスター-なぜ改革は挫折してしまうのか , 東洋経済新報社,2001

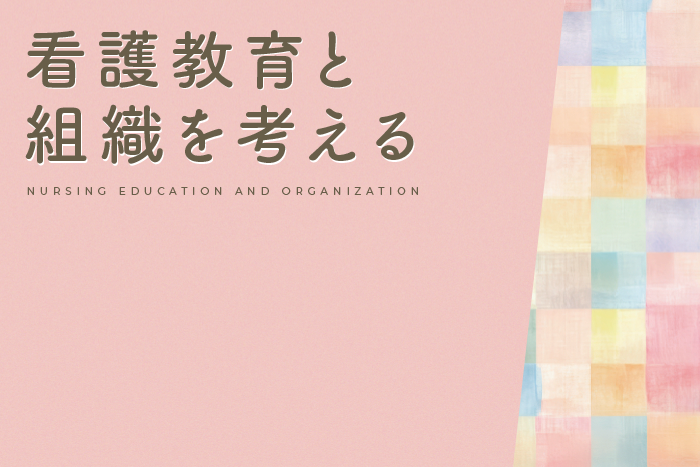


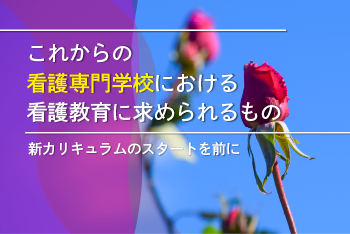
_1640305747860.png)
_1701994343947.png)