はじめまして。医学部看護学科で教員をしております「坂コー」と申します。大学附属病院のICU・CCUなどクリティカルケア領域を中心に15年の臨床を経て、現在は教員3年目です。
この連載では、駆け出し看護教員の日常を、心に移りゆくよしなし事をとりとめもなく綴っていきます。同じような若手の先生方には「それ、あるあるだね!」と共感的に、ベテランの先生方には「ああ、若い頃はそんなふうに悩んだな」と少しノスタルジックに読んでいただけたら嬉しいです。いつまで続けられるかはわかりませんが、どうか生あたたかい目で見守っていただければ幸いです。
「生きる意味」を考え、たどり着いた看護職への道
今回は初回ということで、自己紹介を兼ねて教員になった経緯を書いてみます。
私は小学校から高校までずっと野球部でした。頭を丸坊主にして甲子園を目指す体育会系男子でした。私がお世話になった先生方はみな楽しそうに働いていましたし、『3年B組金八先生』や『スクール☆ウォーズ』のような熱い教員が出てくるドラマに影響された私は、「将来は中学校の先生かな」とぼんやり考えていました。人はいつか必ず死を迎える。動物は子を残すよう頑張りますが、霊長類の長たる人間はそれだけでいいのか?自分が人に影響を与え、その人たちがまた何かに影響を与えていく。そうすればきっと自分が生まれた意味がある。そんな中二病っぽいことを真剣に考えていたのです。まぁ、ほんとに中学2年生くらいでしたしね。
しかし、高校3年生の夏、野球の大会が終わり進路を本気で考えたとき、「教員の“専門性”って何だろう。教えるだけなら誰でもできるのでは?」とふと立ち止まって考えてみました。そこでひらめいたのが、古今東西万人に共通するテーマ、生老病死にかかわる仕事です。最初は救急救命士を思い浮かべましたが、看護師の母から「それ、看護師でもできるよ」と教えられ調べてみると、看護は“人間の反応を扱う専門職”であることを知りました。自分や周りの人間の生活や人生に具体的な影響を与えられる――そう考えてこの道を選び大学に入りました。まさか母校に教員として戻るとは、そのときは思っていませんでしたが……。
看護師は患者の物語の岐路に立ち会っている!
卒業後、新人としてICUに配属されました。当時は今より男性看護師が少なく、1,000人以上の看護師がいる病院で男性看護師は手術室に3人しかいませんでした。緊張してICUに向かった私に、当時の診療部長が「君を待っていたよ」と温かく迎えてくださったことは今でも忘れません。最近では、男性看護師が病棟にいるのが当たり前になりましたね。
新人時代の忘れられない出来事があります。術後の患者さんが「そろそろ帰ろうかな」と突然言い出し、私は「今は無理です」と正論で押しとどめました。するとだんだん患者さんが興奮しだして、「いい加減にしてくれ、もう帰る、どけー」と暴力的になり、鎮静と抑制が必要に……。患者さんが何を体験しているか、患者さんの側から世界を見ることができていなかった私は、結果としてせん妄を助長するかかわりをしていたのでした。苦い後悔が今も残っています。
そんな私も3年ほど経つと、看護師としてできることが増え、BLSやACLSのインストラクターとして蘇生教育にも励んでいました。ICUは最後の砦。モニター、数値、手技――患者さんの身体面にばかり注目し、「ここまではできて当たり前」と自分にも後輩にも高い基準を課していたイケイケで勘違いな時期でした。
そんなある日、予後の厳しい状況にある長期入室中の重症患者さんを受け持ったとき、ベッドサイドにその方が元気な頃の旅行写真が飾られているのを見て、私の中で衝撃が走りました。目の前の「患者」は“その他大勢”ではない。一人ひとりに物語があり、今、その物語の岐路に私は立ち会っている――。そこから見え方が変わりました。身体的なことは当然のこととして、患者さんの体験そのものに寄り添う看護を志すようになりました。その後、働きながら修士に進学し、現場の問いを大学院で深め、実践につなげていきました。そうした過程を通じて、クリティカルケア領域の看護にはまだ不明確な部分が多く、自分が実践するだけでなく、領域全体として高めていく必要があると感じるようになりました。ICUのベッドサイドの写真についての研究も発表しました1,2)。
また、新人時代からのメンター的な集中治療医とともに、JINGR(Jikei ICU Nursing Group for Research)という研究グループを立ち上げ、臨床と研究の行き来をみんなで楽しみながら取り組みました3)。やがて母校からのお誘いを受け、「臨床と研究の橋渡しがしたい」「CNS教育にもかかわりたい」という思いから教員になりました。昔からの“生きる意味=誰かや何かに影響を与える”という考えは、かたちを変えつつ今に続いています。
手探りで歩み始めた教員人生
そんなこんなで教員になりましたが、1年目はなかなか大変でした。臨床ではベッドサイドを離れられずトイレに行くのも一苦労でしたが、教員はそうではない反面、授業・会議以外の時間を自分でデザインする必要があります。「今日は何をすればいいですか?」って、周りも聞かれて困ると思いますが、ほんと最初はそんな感じでした。覚えなきゃいけない細かいものもいっぱいあります。コピー機の使い方から研究費の使い方、教室の予約からZoomの設定などなど、知らない“当たり前”が山ほどありました。「この時期は湿気でコピー機詰まりやすいから、時間にゆとりを持ってやらないとダメだよ」なんて言われて、「べ、勉強になります!」といった具合でした。ゼロから複数の講義資料をつくること、学生のレディネスを見極めること――どれも手探りでした。
そんな感じの教員スタートでしたが、周りの先生方の温かいご支援のおかげで、何とか3年目を迎えられています。ありがたいことに初年度・2年目と「Faculty of the Year Award」をいただくこともできました。学生や先生方に支えられながら、まだまだ手探りのなかでも全力で取り組んできたことが形になったのだと思うと、本当に励みになりました。この経験を糧に、まだまだ発展途上ではありますが、これからも学生や先生方に少しでも役立てる教員でありたいと思っています。
長々と自分語りをしてしまいましたが、初回は「あなたは誰?」をクリアにする回ということでお許しください。次回からは、臨床から教育の場に移ったときに味わった戸惑いや苦労なんかを掘り下げてお話しできればと思います。そこから得た気づきや、教育ならではの楽しさ・やりがいも。
拙いところも多々あるかとは思いますが、どうぞよろしくお願いします。
1)坂木孝輔,高島尚美:ICU入室中の患者家族にとってのベッドサイドの写真の意味.日本クリティカルケア看護学会誌 14:57-65,2018
2)坂木孝輔,高島尚美:ICUにおける看護師にとってのベッドサイドの写真の意味.日本クリティカルケア看護学会誌 13(3):11-20,2017
3)坂木孝輔,山口庸子:特集「看護研究」を問い直す “現場主体の質改善”を目指すマネジメント コラム・インタビュー-【コラム】JINGRのすすめ-臨床と研究のギャップを埋めよう-東京慈恵会医科大学附属病院ICUの取り組み.看護管理 29(3):208-208,2019



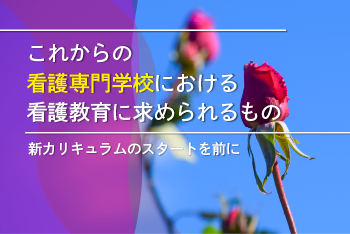

_1701994343947.png)
